



ソフィアと直接交流があったのは『ヴァージン・スーサイズ』を撮る前。その頃フォトグラファーとして頻繁に日本に来ていて、その頃ぼくが在籍していたCUTという雑誌で仕事を頼んだりしていました。そんな流れでビースティ・ボーイズのライブに彼女の親友のステファニーと三人で一緒に電車に乗って行ったりしましたね。1996年のとどろきアリーナ……もう20年前か!(苦笑)。
実際のソフィアは、お嬢様というよりも、たまたまハリウッドで生まれ育った普通の女の子って感じ。無口ってほどではないけど、余計なお喋りもしない。むしろ日本人っぽいというか、まっとうな感覚の子だと思ってました。レッド・クロスっていうバンドの元ドラマーで、後にエールにも参加するブライアン・レイツェルがソフィアの映画のサントラを監修し続けていますが、彼はステファニーの長年のパートナーで、今も旦那さんですね。その頃ビースティ・ボーイズの取材でLAに行ったときは彼らに遊んでもらったりして、ソフィアとステファニーで立ち上げたブランドのMILK FEDのオフィスにもおじゃましたりしましたよ。懐かしいなぁ(遠い目)。
その暫く後、ソフィアが初めてメガフォンを撮った映画『ヴァージン・スーサイズ』を観たときは驚きました。それまでのいわゆるハリウッドが作る青春映画が、いかにもな売れ線ヒット曲と若手スターを並べてマーケティングの臭いぷんぷんだったのに対して、普通の女の子の感覚をそのままトレースしたようなナイーブな青春映画で、めちゃくちゃ新鮮でした。でも同時にどこか懐かしい感じもするし、胸を掻きむしられるような独特な余韻が残る。登場する女の子たちも、みんな可愛いんだけど、割と普通で。キルステン・ダンストはいまでこそ大スターですけど、当時は“女の子から見た可愛い子”で、逆に新鮮でした。ハリウッド映画にありがちな、現実感のない美少女をキャストするんじゃなくて、「女の子が素直にかわいいと思う女の子を撮る」のが抜群にうまかった。それはフォトグラファーとしての彼女のスタイルそのままですね。当初、映画はアメリカではヒットしなかったけれど、日本から火がついたというのは、きっとソフィアが当時の東京のカルチャー(写真ブーム!)にもしっかり触れていて、日本人的な感性をもっていたからな気がします。
で、音楽の話ですよね(笑)。『ヴァージン・スーサイズ』では、HEARTや10CCといった70〜80年代の名曲を集めたカセットテープみたいな選曲に、エールという当時の最旬グループに超スイートなオリジナルテーマ曲をミックスして、その抜群のセンスと自身のフランス好きの片鱗を覗かせていました。幽閉された主人公たちに向けて、男の子たちが電話越しでレコードを流していたシーンでは、トッド・ラングレンの「ハロー・イッツ・ミー」が、まさに彼らが彼女達にむけたラブレターとしての役割を担ってましたね。
そして、続く第2作の『ロスト・イン・トランスレーション』。これで一気にアメリカでもブレイクを果たすわけですが、あれだけ頻繁に日本を訪れていたソフィアの「トーキョー時代」を昇華させるという意味で、避けて通れない一本だったと思います。自分が元夫のスパイク・ジョーンズたちと東京に来たときに、定宿だったパークハイアットで感じた孤独や心象風景がうまく映像化されていました。サウンドトラックがまた冴えていて、中でも長らく活動休止中だったマイ・ブラディ・ヴァレンタインのケヴィン・シールズが新曲を提供したということで、音楽業界をも驚かせました。ブライアンがケヴィンと友人で、普通に頼んだら気軽に受けてくれたそうですね。当時大人気だったデス・イン・ヴェガスやスクエアプッシャーをきちんと押さえながら、はっぴいえんどの名曲「風をあつめて」が入ってるあたりは流石。
一転して第3作目の『マリー・アントワネット』では、ソフィアのフランス趣味が爆発しましたね。といいつつ、音楽はスージー・アンド・ザ・バンシーズやアダム・アンド・ジ・アンツをはじめとするUKニューウェーブだらけで、特にフランスでの上映当時は、いろいろ物議を醸したみたいですね。ソフィアのアタマの中ではきっと「オーストリアからフランスという未知の世界に飛び込む14歳のマリー・アントワネットの目に映るバブルガム的なポップな世界では、バウ・ワウ・ワウの『I Want Candy』がかかっていたんじゃない?」という妙な確信があったのでは(笑)。そのへんのセンスは、ソフィアならではのぶっ飛び方というか、でもいま思うとアリな気がします。そこにやはりセンチメンタルで新しいエールやストロークスを絶妙にミックスさせることで、ソフィアならではのオルタナティブな青春映画のサウンドトラックの流れを継承していたと思います。結果的に今あの映画はとても評価されているし、やっぱり彼女は間違っていなかった(笑)。
『SOMEWHRE』は、唯一サントラ盤が出てませんね。僕はあの映画を見ながら、なんて無音な時間が長いのだろうと思った。そう、あえて無音な時間をたくさん作ることで空間的なミニマリズムを構築したアート映画の一作なんだなと。とはいえ、そんな静かな空間にエル・ファニングのスケートシーンでグウェン・ステファニが流れたり、フー・ファイターズがさり気なくかかるように、そのときの旬な音楽を絶対に逃さない。
現実に起きた事件を映画化した最新作の『ブリングリング』では、M.I.A.にカニエ・ウエストと、実際に登場人物たちが聴いていたであろうSNS世代のリアルなサウンドが、ヒップホップを中心に描き出されていました。僕はこの選曲をソフィア自身の感性というよりも、あえて一世代下がったときの最旬へとスライドさせたという意味で、ブライアンのディレクションが忠実に反映されたトラック集だと思っています。
振り返ると、その時代のとびきり旬な音楽とエバーグリーンな懐かしい音楽と共に新しい青春映画を撮り続けること。それが彼女の一生の使命な気がしますね。






雑誌「EYESCREAM」編集長。1969年大阪府生まれ。早稲田大学第一文学部哲学科卒業後、シンコーミュージックに入社。販売営業、編集部を経て、1993年ロッキング・オンに転籍する。邦楽誌「ROCKIN’ON JAPAN」に在籍後異動し、邦楽誌「bridge」、カルチャー誌「H」の創刊に立ち会う。後にカルチャー誌「CUT」に異動、副編集長に就任。洋楽誌「rockin’on」副編集長を務めた後、勤続10年を機に退社。2004年4月より月刊カルチャー誌「EYESCREAM」を創刊。2011年にファッション&ジャーナル誌「SPADE」を創刊。2015年にアイドルカルチャー誌「UPDATE girls」を創刊。
http://www.eyescream.jp

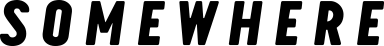
「SOMEWHERE」
ロサンゼルスにある有名人御用達の高級ホテル「シャトー・マーモント」で、フェラーリを乗りまわし、酒と女を愛する自堕落な生活を送っていた売れっ子俳優のジョニー・マルコ。ある日部屋に戻った彼を待っていたのは、別れた妻と暮らしているはずの11歳の娘クレオだった。
ジョニーを演じたスティーヴン・ドーフも見事なハマり役ながら、まだあどけなさを残すクレオ役のエル・ファニングがすばらしい。父親の抱える闇を一掃するかのようにまっすぐと力強い光を放ち、本作にフレッシュな印象を与えている。父と娘が仲睦まじく暮らす様子は、やはり映画監督である父、フランシス・フォードと共に幼い頃からホテル暮らしをしていたソフィア・コッポラの個人的な思い出が反映されているという。
この作品で第67回ヴェネチア映画祭でグランプリの金獅子賞を受賞し、コッポラは名実ともに世界を代表する映画監督となった。審査員長を務めたクエンティン・タランティーノは「満場一致だった。われわれは最初の試写からこの作品に魅了されていた」とその理由を語っている。
text:aggiiiiiii

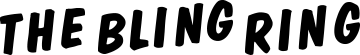
「ブリングリング」
2008年から2009年にかけてハリウッドで実際に起きた事件を元にした、ソフィア・コッポラ初の実話の映画化。これまでのガーリー路線とは一転してサウンドトラックにヒップホップを多用するなど、ひとところに納まろうとしない彼女の新たな挑戦の跡が見られる。
セレブの私物をチェックし、買い物感覚で彼らの家に盗みに入る高校生の窃盗集団。自宅もスケジュールも、コツさえあれば簡単に調べられるらしい。パリス・ヒルトンやオーランド・ブルームは実際に彼らによって数百万から数億円の盗難被害にあった。そんな偽セレブであるはずの「ブリングリング」は、しかし世間の注目を集めて次第に人気者となっていく。
セレブに憧れ、高価なモノを身につけてSNSにアップすることで自尊心が満たされる今どきの若者たちを追うコッポラの視点はドライで、これははじめて彼女が「わからない」ことを描こうとした作品でもある。被害にあった自宅を嬉々として撮影場所に提供したパリス・ヒルトンのとんちんかんさも可笑しい。
text:aggiiiiiii