検索結果
-

PROGRAM/放送作品
映画『アリス・イン・ワンダーランド』公開記念特番! ジョニー・デップ来日の舞台裏
映画『アリス・イン・ワンダーランド』で来日予定のジョニー・デップ。来日キャンペーンの裏側に迫る
4月17日より劇場公開予定のティム・バートン監督、ジョニー・デップ主演ファンタジー・アドベンチャー『アリス・イン・ワンダーランド』。この話題作の見どころと主演ジョニー・デップの来日キャンペーンの裏側に迫る特別番組。
-

COLUMN/コラム2017.12.09
12月8日(金)公開『オリエント急行殺人事件』!なんでもできる人・ケネス・ブラナーがこのクラシックにどう挑むか!?
原作者の曽孫も賞賛する、ブラナー版『オリエント急行殺人事件』の独自性 ひとつの難事件を解き終え、イスタンブールからイギリスに向かうべく、オリエント急行に乗り込んだ名探偵エルキュール・ポアロ(ケネス・ブラナー)。そこで出会ったアメリカ人の富豪、ラチェット(ジョニー・デップ)に身辺警護を頼まれるが、ポアロはあっさりと断ってしまう。だがその夜、雪崩のために脱線し、立ち往生を食らったオリエント急行の客室で、刺殺体となったラチェットが発見される……。「マルチキャスト」「オールスター」「アンサンブル共演」etcー。呼び名は多様だが、主役から端役に至るまで、登場人物すべてをスター級の俳優で固める映画というのは、ハリウッド・クラシックの優雅なスタイルだ。時代の趨勢によってその数は縮小されていったが、それでも夏休みや正月興行の花形としてときおり顔を出すのは、それが今もなお高い集客要素を包含しているからに相違ない。 そんなマルチキャスト方式の代表作ともいえる『オリエント急行殺人事件』は、ミステリー小説の女王として名高いアガサ・クリスティの原作のなかで、最も有名なものだろう。これまでに何度も映像化がなされ、とりわけシドニー・ルメット監督(『十二人の怒れる男』(57)『狼たちの午後』(75))による1974年のバージョンが、この偉大な古典の映画翻案として多くの人に「衝撃の結末」に触れる機会を与えてきた。 今回、ケネス・ブラナーが監督主演を務めた新生『オリエント急行殺人事件』は、そんなルメット版を踏まえ、徹底した豪華スターの共演がなされている。しかしどちらの作品も、マルチキャストは単に集客性を高めるだけのものではない。劇中におけるサプライズを成立させるための重大な要素であり、必要不可欠なものなのだ。ありがたいことにミステリー愛好家たちの努力と紳士協定によって、作品の命といえるオチに関しては「ルークの父親はダース・ヴェイダー」よりかろうじて秘密が保たれている。なので幸運にして本作の結末を知らない人は、この機会にぜひ「なぜ豪華キャストでないとオチが成立しないのか?」という驚きに触れてみるといい。 とはいえ、モノが徹頭徹尾同じであれば、長年愛されてきたアガサの原作にあたるか、最良の映画化であるルメット版を観れば事足りるだろう。しかし今回の『オリエント急行殺人事件』は、過去のものとは一線を画する価値を有している。 そのひとつとして、ブラナー監督が同時に稀代の名探偵である主人公ポアロを演じている点が挙げられるだろう。『愛と死の間で』(91)や『フランケンシュタイン』(94)など、氏が主役と監督を兼ねるケースは少なくない。しかしアガサ・クリスティ社(ACL)の会長兼CEOであるジェームズ・プリチャードによると、このアプローチに関し、今回は極めて強い正当性があるという。いわく、「ポアロという人物はこの物語の中で、登場人物全員を指揮している立場であり、ある意味で監督のような仕事をしている存在です」とーー。 かつてさまざまな名優たちが、ポアロというエキセントリックな名探偵を演じてきた。しかしこの『オリエント急行殺人事件』におけるブラナーのポアロは、プリチャードが指摘する「物語を指揮する立場」としての役割が色濃い。列車内での殺人事件という、限定された空間に置かれたポアロは、乗客たちのアリバイを事件と重ね合わせて検証し、理論づけて全体像を構成し、犯人像を浮かび上がらせていく。確かにこのプロセスは、あらゆる要素を統括し、想像を具象化する映画監督のそれと共通している。だからこそ、役者であると同時に監督としてのスキルを持つ、ブラナーの必要性がそこにはあるのだ。 さらにはブラナーの鋭意な取り組みによって、この『オリエント急行〜』は原作やルメット版を越境していく。完全犯罪のアリバイを解くだけにとどまらず「なぜ容疑者は殺人を犯さなければならなかったのか?」という加害者側の意識へと踏み込むことで、この映画を犯罪ミステリーという立ち位置から、人が人を断罪することへの是非を問うヒューマニティなドラマへと一歩先を行かせているのだ。シェイクスピア俳優としてイギリス演劇界にその名を馳せ、また監督として、人間存在の悲劇に迫るシェイクスピアの代表作『ヘンリー五世』(89)や『ハムレット』(96)を映画化した、ブラナーならではの作家性を反映したのが今回の『オリエント急行殺人事件』最大の特徴だ。ブラナーが関与することで得られた成果に対し、プリチャードは賞賛を惜しまない。 「ケネスは兼任監督として、ものすごいリサーチと時間と労力をこの作品に注いでくれました。映画からは、そんな膨大なエネルギー量が画面を通して伝わってきます。『オリエント急行殺人事件』はアガサの小説の中でも、もっとも映像化が困難な作品です。しかしケネスの才能あってこそ、今回はそれをやり遂げることができたといえるでしょう」 ブラナー版の美点は、先に挙げた要素だけにとどまらない。密室劇に重きを置いたルメット版とは異なり、冬場の風景や優雅な客車の移動ショットなど、視覚的な攻めにも独自性がみられるし、『ハムレット』で実践した65mmフィルムによる撮影を敢行し、マルチキャスト同様にクラシカルな大作映画の優雅さを追求してもいる。 『忠臣蔵』や『ロミオとジュリエット』のような古典演目が演出家次第で表情を変えるように、ケネス・ブラナーの存在を大きく誇示する今回の『オリエント急行殺人事件』。そうしたリメイクのあり方に対する、原作ファンや観客の受け止め方はさまざまだ。だが殺人サスペンスという形式を用い、人の愚かさや素晴らしさを趣向を凝らし描いてきた、そんなアガサ・クリスティのマインドは誰しもが感じるだろう。 古典を今の規格に適合させることだけが、リメイクの意義ではない。古典が持つ普遍的なテーマやメッセージを現代に伝えることも、リメイクの切要な役割なのである。■ © 2015 BY EMI FILM DISTRIBUTORS LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
-
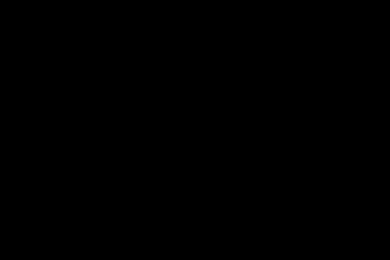
PROGRAM/放送作品
映像で地球を考える~アースデイ2010~
映画『アース』放送にあわせた特別番組。映像を通して私たちの地球を一緒に考えよう
4月22日は“アースデイ”。地球環境について考え、行動する日だ。地球のために私たちに何ができるのか?何をしなければならないのか?フリーダイビングなど自然での活動を通し、環境に対するメッセージを数多く発信している、女優の益戸育江(旧名:高樹沙耶)と一緒に考える、オリジナル特番。
-

COLUMN/コラム2017.11.30
個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年12月】にしこ
監督自身、アイルランドからアメリカへ移住し、自らの夢を叶えた人物。作中の様に、奇跡の様な飛び道具キャラクターの存在は実際あったかわかりませんが、当時の自分と家族のもがきを懐かしく、そして同じ様な経験をしたであろう、多くの他国からアメリカへやって来た人たちへの暖かく愛しい目線で描かれる名作です。2人の娘、クリスティとアリエルを連れてカナダ経由でアメリカにやってきたジョニーとサラ夫妻。入国規制が緩いカナダ経由でNYに入ろうとした冒頭から緊迫感が漂います。なぜ彼等はアイルランドからニューヨークへやってきたのか。言葉では言い表せない喪失をなんとか心機一転に変えるためにやってきたその理由は、作中で明かされます。小学校高学年の長女クリスティは長女らしいしっかり者。いつもハンディカムを回して家族を撮影しています。それは彼女が家族を俯瞰で観察し、必要とあればその均衡あやうい絆のバランスを保つため。物語は彼女の目線で語られていきます。一方幼い妹のアリエルは、その天真爛漫さで、新天地であるニューヨークの生活を子供ならではの柔軟性で楽しみ、家族を和ませます。そんな2人と対照的に、両親であるジョニーとサラは、まだぬぐいきれない喪失感と日々の生活の苦しさに余裕のない毎日。サラはジョニーに言います。「幸せなフリをして。子供たちのために。お願い」と。どんなに愛し合っていても、それだけでは超えられない悲しみがある。人には人それぞれの悲しみがあり、それを肩代わりすることはできないから。そんな生活の中、ヤク中患者の巣窟の様なニューヨークの治安の悪い地域のマンションに住む家族は、ハロウィンをきっかけに、謎の隣人マテオと出会う事になります。アリエルが「トリック・オア・トリートをやってみたい!」と言い出した事がきっかけ。これは、アイルランドからやってきた家族、というところに重要な意味が有ります!なんとアイルランドはハロウィン発祥の地でありながら「トリック・オア・トリート」がありません!これは、アメリカで生まれた独自の風習。アイルランド本国ではハロウィンは精霊や妖精が集うお祭りなので、日本でいうとねぶた祭りみたいに、でっかい山車が街を凱旋する。みたいなお祝いの仕方をします。(アイルランド在住1年。ザ・シネマ編成部にしこ体験談。)謎の隣人マテオははたして何者なのか?何者かどうかはさておき、彼との出会いで家族の運命が変わっていきます。学校の課題でハロウィンのコスチュームを作る事になった姉妹。姉のクリスティが「秋」の仮装をしたことを指摘された時に、「autumだね!」という母に「fall」よ!といいます。アイルランドでは秋の事を「オータム」と、アメリカでは「フォール」と言う。こういった文化の違いに子供たちが日々学び、格闘している姿をさらっと描くところも名匠の手腕。そして、クリスティ、アリエル姉妹を演じた実際の姉妹であるボルジャー姉妹。彼女達の純度の高いあの日々しか撮りえなかった瞬間を収めたというだけで、この作品には価値があると思います。クリスティが学校の学芸会で「デスペラード」を独唱するシーンの尊さ。アリエルの底抜けな純真さ。あえていいたい。この作品の主役は彼女達です。この作品の脚本は、監督のジムと娘の共同で書かれたもの。苦しく、懐かしく、そして輝かしかった日々であったことが、この作品を観ればわかります。必見です。■ © 2003 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
-
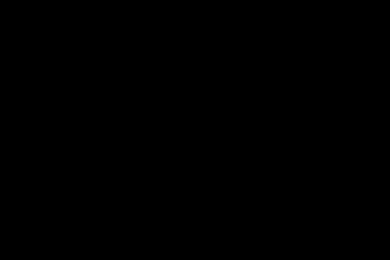
PROGRAM/放送作品
世界のクロサワ 栄光と挫折からの復活
-
“海外から見た黒澤明”をテーマに、「世界のクロサワ」の誕生からハリウッドでの活躍と挫折、監督引退の危機とその後の復活を、映画評論家・品田雄吉氏のインタビューを織り交ぜながらお届けします。
-

COLUMN/コラム2018.02.26
個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2018年3月】にしこ
知ってるよ!という感じかと思いますが、ダブリンというのはアイルランド共和国の首都であり、一番の大都市であります。そりゃあ華やかで、賑わっているだろうと想像されると思いますが、東京のターミナル駅と比べるとずっこけるくらい小さいです。メインストリートであるオコンネルストリートは15分くらいあれば端から端まで余裕で歩けます。そんな街角で二人の男女が運命的な出会いを果たすわけですが、実際のオコンネルストリートを歩いた私は「ほぼ毎日ここでギター弾いて歌ってたら、誰でも顔を覚えるだろうな」という感想を持つのであります。ネガティブな意味ではなく、この映画の主役二人が出会うのはまさしく「街角」という言葉がふさわしい、そんな場所だというイメージをしていただきたいのです。「ケルトの虎」と言われた時代(1995年から2007年まで続いたアイルランドの経済成長を指す表現。Wikipediaより)。EU各国から好景気に沸くアイルランドに出稼ぎに来る人々でダブリンは多国籍な街に。主人公の女性も生活の為に、家族を母国のチェコに残して出稼ぎに来た女性。故郷ではピアニストだった彼女。オコンネルストリートでギターを弾く男性主人公に声をかけたのは、必然だったのかもしれません。男と女は音楽という共通言語であっという間に距離を縮めていきます。男は、最後のチャンスに賭けるつもりでロンドンのレーベルに持ち込むデモテープを一緒に作ってくれないか、と女に協力を求めます。日々の生活に追われていた女は、自分が愛するピアノに触れる事で、どんどん生き生きとした表情と取り戻します。当然のごとく惹かれあう二人。しかし女には祖国に夫がいます。お互いに惹かれる気持ちを昇華させる為に、二人は曲を作ります。音楽が引きあわせた2人。音楽で二人の気持ちを形にしようとするのは自然な事なのかもしれません。二人が最後に出した答え。その答えにこそ涙してください。こんなに泣けて、すがすがしい恋もあるのだと。映画史に残る素晴らしいエンディングをお見逃しなく。アメリカでたった2館からの公開だったのが、口コミの素晴らしさから140館にまで公開館数が伸びた事が話題になっていたその頃、私はアイルランドの田舎町の片隅の、バイト先の洋服屋さんで毎日ラジオから流れる主題歌の「Falling Slowly」を聞いていました。お客さんがいない店内で、何度も口ずさんだ曲。思い出すたび甘酸っぱいっす!!■ © 2007 Samson Films Ltd. and Summit Entertainment N.V.
-
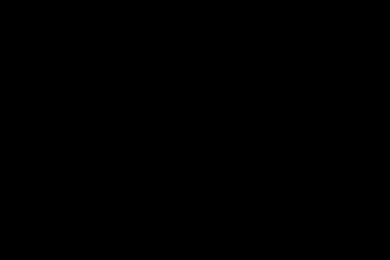
PROGRAM/放送作品
「スパルタカス」スペシャル
話題沸騰のTVドラマ・シリーズ『スパルタカス』の見所をいち早く紹介!
今年全米で高視聴率を記録したTVドラマ・シリーズ『スパルタカス』をスター・チャンネルでは7月から独占日本初放送!その見所を紹介する特番。ザ・シネマ放送のキューブリック監督の名作『スパルタカス』も必見!
-

COLUMN/コラム2018.02.26
個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2018年3月】うず潮
韓国で100万人以上が酔いしれた、殺人を請け負う企業に勤める殺し屋の葛藤を描くクライムアクション。韓国で最も有名な俳優、ソ・ジソブが主演。彼が演じる完璧主義のクールな殺し屋が魅せる、そのキレッキレのガンアクションや殺陣は必見!惚れ惚れするようなカッコ良さを魅せてくれます!そんな彼が本作への出演を決めたのは、脚本を読んで殺し屋が普通の会社員のように働く設定に惹かれたとのこと。そのため、会社員のように振る舞う殺し屋を演じるため、スーツの下に着るシャツは白いで統一するなど普通っぽく見せる工夫もしたそう。ストーリーが進むにつれ、完璧主義者の殺し屋から、守るべき存在ができた男へと変わっていく姿も見どころのひとつ。ソ・ジソブファンはもちろんのこと、男性も是非見てほしい1本。キレッキレのアクション繋がりで、キアヌ・リーヴスのキレッキレのガンアクションが冴えわたる『ジョン・ウィック』(3月ザ・シネマで放送)と見比べしても面白いかも! ©2012 SIMMIAN AND SHOWBOX/MEDIAPLEX ALL RIGHTS RESERVED.
-
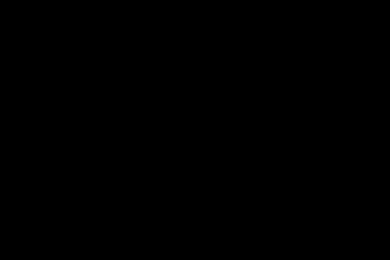
PROGRAM/放送作品
ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 特番
驚異のメガヒットシリーズの3作目をとことん楽しむための案内番組
13歳になったハリーを待ち受けるのは、かつてない危機と驚愕の真実。今まで見えなかったものが見え始め、わからなかったことがわかり始める第3章。その謎と魅力に迫るミニ番組。
-

COLUMN/コラム2018.02.04
なぜ人は『悪魔の棲む家』にかくも惹かれるのか!? 長男による家族惨殺事件と、虚実入り乱れた土地にまつわる伝説と、売名疑惑のスキャンダルが混然一体となった底無しの深淵「アミティヴィル・ホラー」とは!?
‘70年代オカルト映画ブームの起爆剤となったのが『エクソシスト』(’73)、ブームの頂点を極めたのが『オーメン』(’76)だったとすると、そのトリを飾ったのが『悪魔の棲む家』(’79)だったと言えるかもしれない。『エクソシスト』同様にアメリカで実際に起きた悪霊事件の映画化。ジェイ・アンソンが執筆した原作ノンフィクション『アミティヴィルの恐怖』は全米ベストセラーとなり、日本でも翻訳出版されて、それなりに話題を呼んでいたことを、当時小学生だった筆者も記憶している。いわば鳴り物入りの映画化であって、全米興行収入ナンバー・ワンの大ヒットもある程度は想定の範囲内だったに違いない。とはいえ、その後40年近くに渡って、非公式を含む続編やリメイクが延々と作られ続けることは誰も予想しなかっただろう。しかもその数、現在までに合計で18本!『エクソシスト』関連作が6本、『オーメン』関連作が5本であることを考えると、他よりもケタ違いに多いのである。 なぜそこまで、『悪魔の棲む家』シリーズに人々は惹かれるのか。まずはそこを振り返ることから始めた上で、その原点である’79年版の見どころを解説していきたい。 ことの発端は1974年11月13日。ニューヨーク州ロングアイランドの閑静な町アミティヴィルで、一家6人が射殺されるという惨劇が発生する。犯人は一家の23歳になる長男ロナルド・デフェオ。当初はマフィアの犯行を主張していた(実際、デフェオ家はマフィアに関りがあったとされる)ロナルドだったが、警察に証言の矛盾点を指摘されたことから、自分が両親と4人の弟や妹をショットガンで殺害したことを認めたのである。 それから1年余り経った1975年12月19日、惨劇のあったアミティヴィルの家にラッツ一家が移り住んでくる。ジョージ・ラッツと妻キャシー、そしてキャシーの連れ子3人だ。夫婦はいわくつきの物件であることを承知した上で、8万ドルという破格の安さに惹かれて家を買ったのだが、しかし彼らが引越しをして以来、家では様々な怪現象が発生したという。それは日に日に深刻となっていき、移り住んでから28日後の1976年1月14日、ラッツ一家は着の身着のままでアミティヴィルの家を逃げ出す。以上が、事件の大まかなあらましである。 ラッツ一家にとっては、これで一件落着したかに思えた悪霊騒動。しかしその後、マスコミや霊能者、心霊学者など大勢の人間が彼らの周りに寄って集まり、怪現象の真偽を巡って全米が注目する一大論争へと発展してしまうのである。 もともと世間に公表するつもりなどなかったというラッツ夫妻。だが、ある人物によって記者会見を無理強いされたと生前のインタビュー(夫婦共に故人)で主張している。それが、ロナルド・デフェオの弁護士ウィリアム・ウェバーだ。夫婦から相談を受けていたウェバーは、どうやらラッツ夫妻を自らの売名行為に利用しようとしたらしい。当時デフェオ事件の回顧録を執筆していたというウェバーは、一家の体験を自著に盛り込もうと提案したそうなのだが、夫婦はこれを断ったらしい。だからなのか、ジェイ・アンソンの著書がベストセラーになると、ウェバーはその内容を自分がラッツ夫妻に入れ知恵した創作だと雑誌「ピープル」で告白し、そもそも一連の悪霊騒動は家を購入した時点から夫婦が計画していた金儲けのペテンだとまで証言している。もちろん、どちらの主張が正しいのかは分からない。 さらにことをややこしくしたのが、超常現象研究家でヴァンパイア研究家を自称するスティーブン・キャプランだ。当時ラジオにたびたび出演して知名度のあったキャプランは、ラッツ夫妻から屋敷の調査を依頼されたという。しかし、その結果を世間に公表すると断ったところ、ためらった夫妻が調査依頼を撤回したことから、キャプランは悪霊騒動がインチキであると考え、それ以降テレビや雑誌、自著などでラッツ夫妻を激しく非難するようになる。これまた双方の主張に食い違いがあるのだが、いずれにせよキャプランによるラッツ夫妻への批判活動が、悪霊騒動に世間の注目を集める要因の一つになったと言えよう。 一方、ラッツ夫妻の主張を支持する人々も現れる。その筆頭が、映画『死霊館』シリーズのモデルとなったことでも有名な霊能者ウォーレン夫妻だ。そのあらましは『死霊館 エンフィールド事件』の冒頭でも描かれているが、彼らはテレビ局やラジオ局の取材クルーなどと共に屋敷を調査し、凶悪な悪霊が家に取り憑いていると証言している。また、テレビの心霊番組ホストとしても知られる超心理学者ハンス・ホルザーも、霊能者エセル・マイヤーズと共に屋敷を調査しており、ロナルド・デフェオは土地に取り憑いた先住民の幽霊に憑依されて一家惨殺の凶行に及んだと主張している。ただし、彼の場合は弁護士ウィリアム・ウェバーの依頼で調査を行ったという事実を留意しておくべきだろう。つまり、ロナルド・デフェオ裁判の不服申し立ての根拠として利用されようとした可能性があるのだ。 このようなメディアを巻き込んだ論争の最中、1977年に出版されたのが『アミティヴィルの恐怖』。出版社から推薦されたノンフィクション作家ジェイ・アンソンに執筆を任せたラッツ夫妻は、自分たちの主張を一冊の本にまとめることで、一連の騒動や論争に終止符を打つつもりだったのかもしれない。これが真実なのだと。とはいえ、ラッツ夫妻を含む関係者の全員に、何らかの売名的な意図が垣間見えることも否めない。まあ、ラッツ夫妻やウォーレン夫妻らの主張を完全に否定するわけではないが、しかし疑いの余地があることもまた確かだ。同じことは反対側の人々に対しても言えるだろう。結局のところ真相は闇の中。そうした周辺のゴタゴタ騒ぎや、土地にまつわる虚実入り乱れた伝説と噂、実際に起きた血なまぐさい一家惨殺事件の衝撃が混然一体となって、「アミティヴィル事件」に単なる悪霊騒動以上の興味と関心を惹きつけることになったように思える。それこそが、今なお根強い『悪魔の棲む家』人気の一因になっているのではないだろうか。 で、そのノンフィクション本『アミティヴィルの恐怖』を映画化した’79年版『悪魔の棲む家』。これは劇場公開時から指摘されていることだが、ドキュメンタリー的なリアリズムを重視するあまり、とても地味な映画に仕上がっていることは否めないだろう。あくまでも娯楽映画なので、いくらでも派手な脚色や誇張を加えることはできたはずだ。しかしそうしなかったのは、やはり『暴力脱獄』(’67)や『マシンガン・パニック』(’73)、『ブルベイカー』(’80)などの、骨太なアクション映画や社会派映画で鳴らした名匠スチュアート・ローゼンバーグ監督ならではのこだわりなのだろう。ゆえに、『エクソシスト』や『オーメン』のショッキングな恐怖シーンを見慣れた当時の観客が、少なからず物足りなさを覚えたことは想像に難くない。劇場公開時にはまだ小学生で、なおかつソ連在住という特殊な環境にあったため、物理的に見ることのできなかった筆者などは、いわゆるスプラッター映画全盛期の’80年代半ばに名画座で初めて本作を見たので、なおさらのことガッカリ感は強かったと記憶している。 ところが、である。それからだいぶ経って久しぶりにちゃんと見直したところ、意外にもガラリと大きく印象が変わった。要は、古典的な「お化け屋敷」映画として、非常に完成度の高い作品なのだ。中でも、悪魔に魅入られた父親が徐々に狂っていく過程は、下手に悪魔やモンスターがバンバン飛びだしてくるよりも、よっぽど観客の精神的な不安感や恐怖感を盛り上げて秀逸。まるで目のような窓が2つ付いた家の不気味な外観もインパクト強いし、ハエのクロースアップなどの何気ない描写の積み重ねがまた、地味ながらも確実に不快感を煽る。確かに派手な特殊メイクやSFXは皆無に等しいものの、全編に漂う禍々しい雰囲気は捨てがたい。それこそ、『呪いの家』(’44)や『たたり』(’63)の系譜に属する正統派のゴーストストーリーだと言えよう。 なお、限りなくラッツ夫妻の主張する「事実」に沿った本作だが、しかしそれでも一部にドラマチックな変更はなされている。その代表例が、ロッド・スタイガー演じるデラニー神父のエピソードであろう。モデルとなった神父は、お払いの際に悪魔のものらしき声を聞いただけで、ハエの大群やポルターガイスト現象に襲われたという事実などはないし、ましてや後に失明してしまったわけでもない。あくまでも脚色だ。ちなみに、なぜハエの大群なのかというと、新約聖書に出てくる悪魔ベルゼブブがヘブライ語で「ハエの王」を意味するから。キリスト教に疎い日本人にはちょっと分かりづらいかもしれない。 先述したように、その後も延々と続編が作られて長寿シリーズ化した『悪魔の棲む家』。個人的には、デフェオ一家惨殺事件をモデルにした『悪魔の棲む家PART2』(’82)も、イタリア映画界の革命世代を代表するダミアノ・ダミアーニ監督らしい「反カトリック教会」精神が貫かれていて、とても興味深く感じる作品だった。また、本作とは真逆のアプローチで、派手な残酷描写やショックシーンをふんだんに盛り込んだ、リメイク版『悪魔の棲む家』(’05)も、本作と見比べると非常に面白い。昨年全米公開されたばかりのシリーズ最新作『Amityville: The Awakening』は、なんとジェニファー・ジェイソン・リーとベラ・ソーンの主演。日本での劇場公開に期待したいところだが、ん~、やっぱりビデオスルーになるのかなあ…。■ AMITYVILLE HORROR, THE © 1979 ORION PICTURES CORPORATION. All Rights Reserved