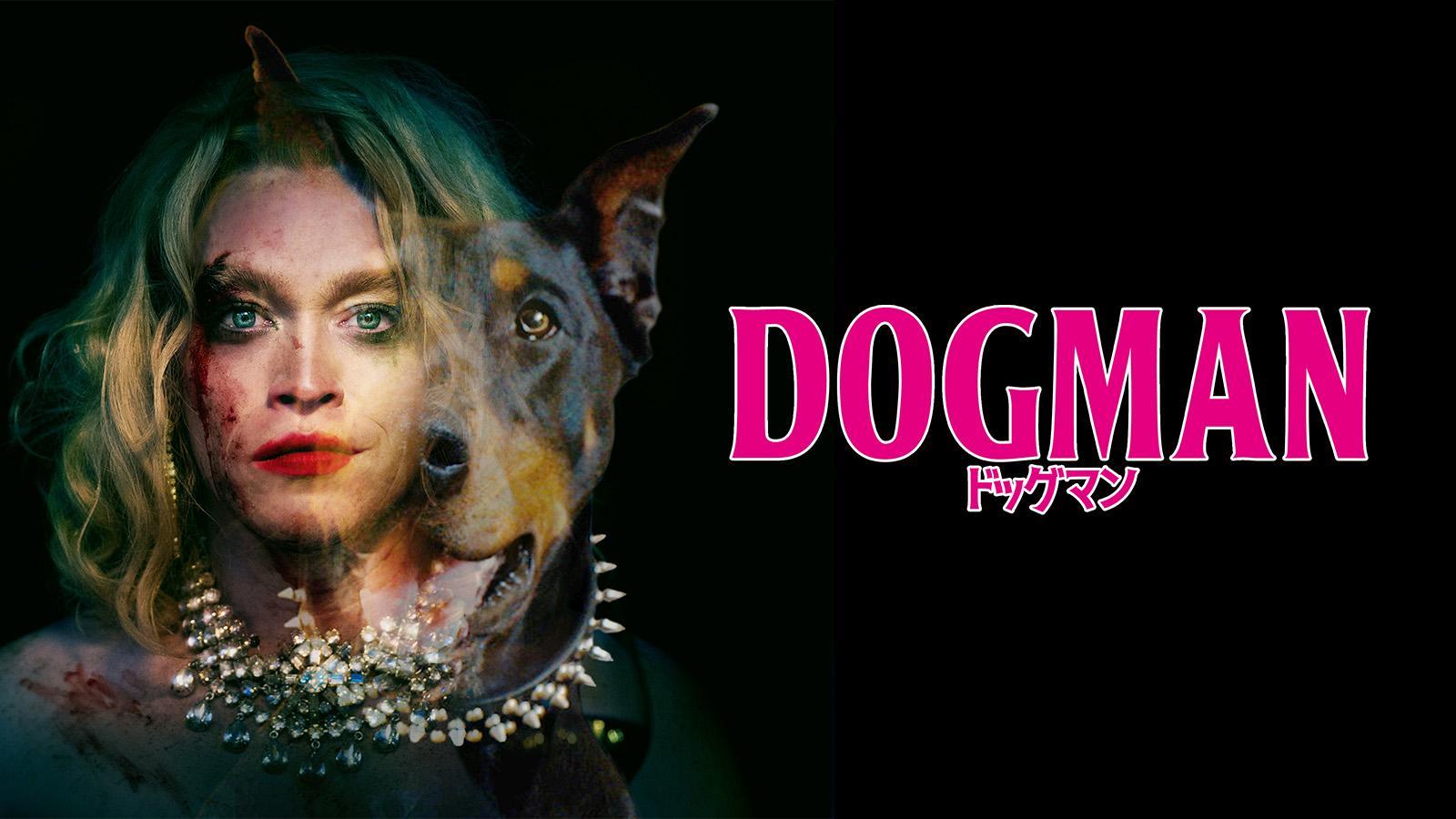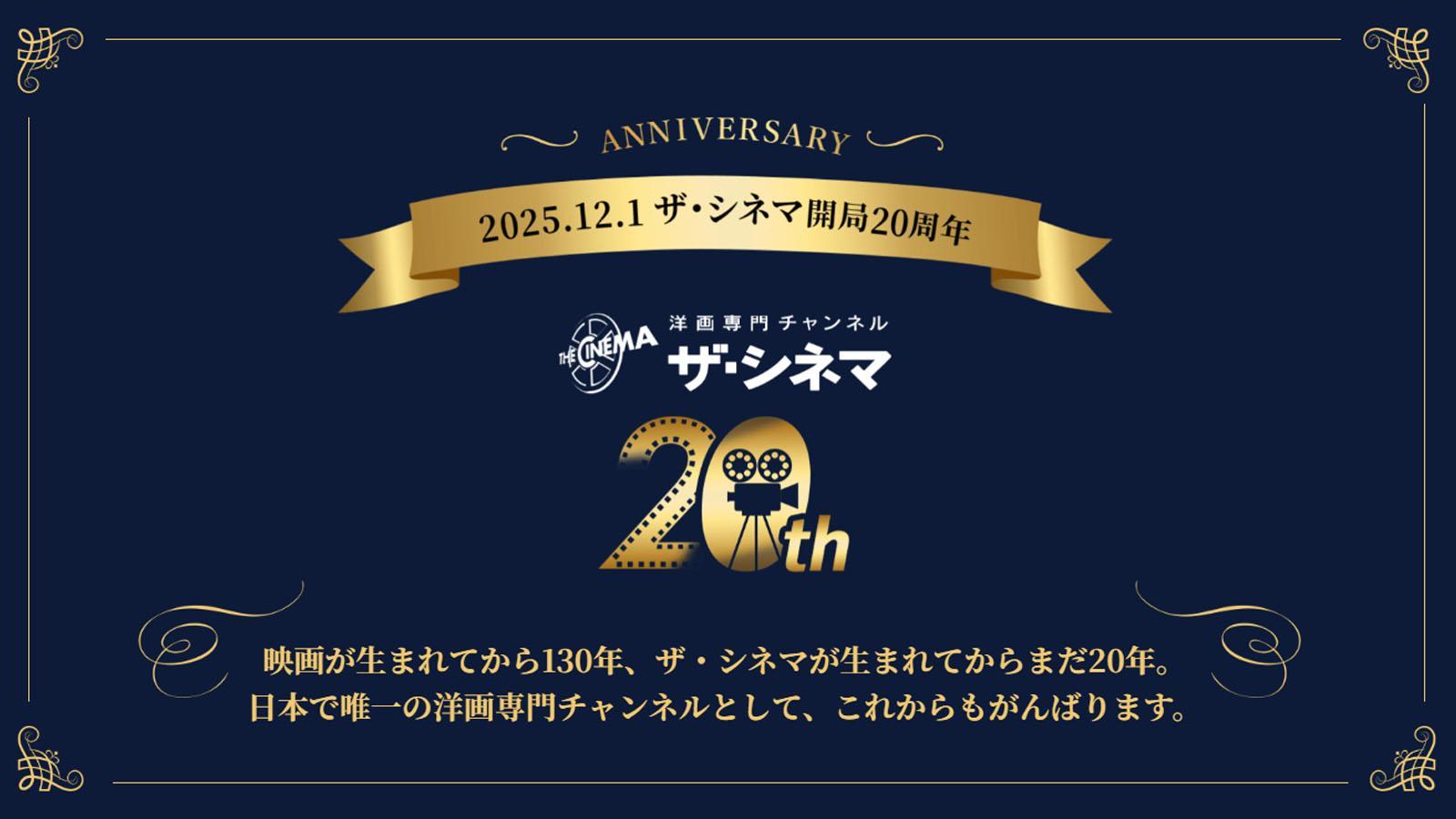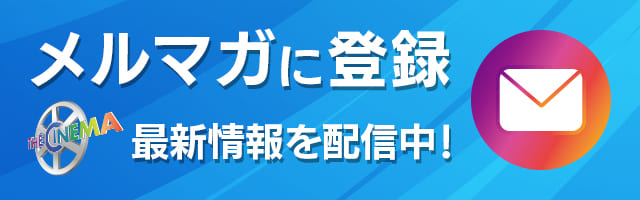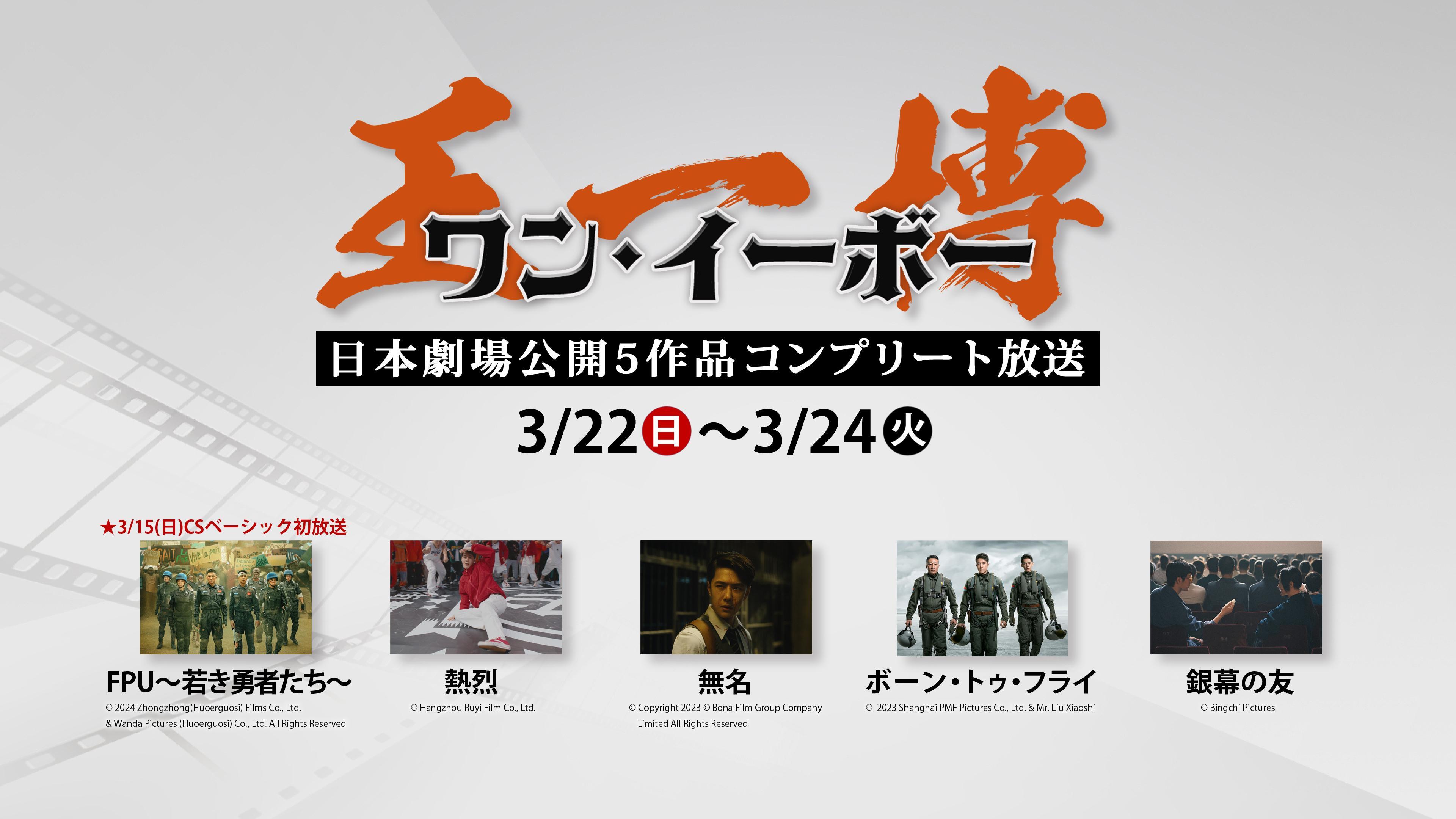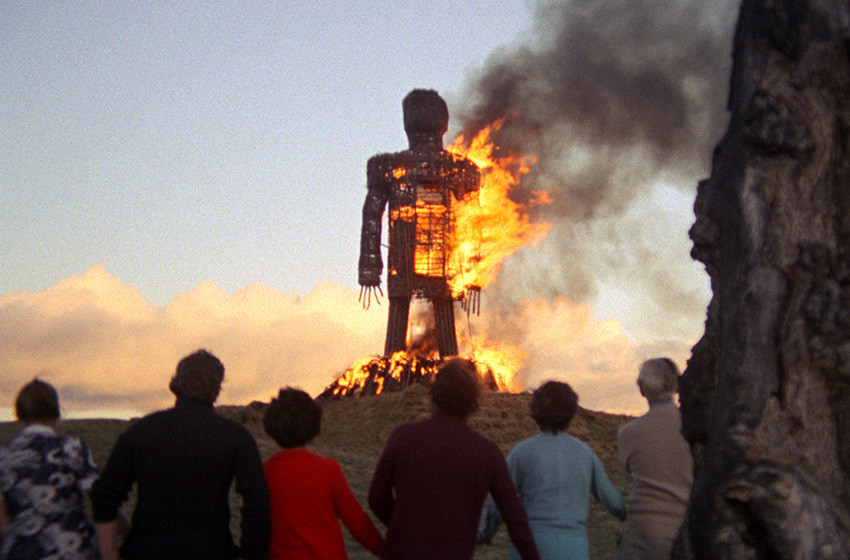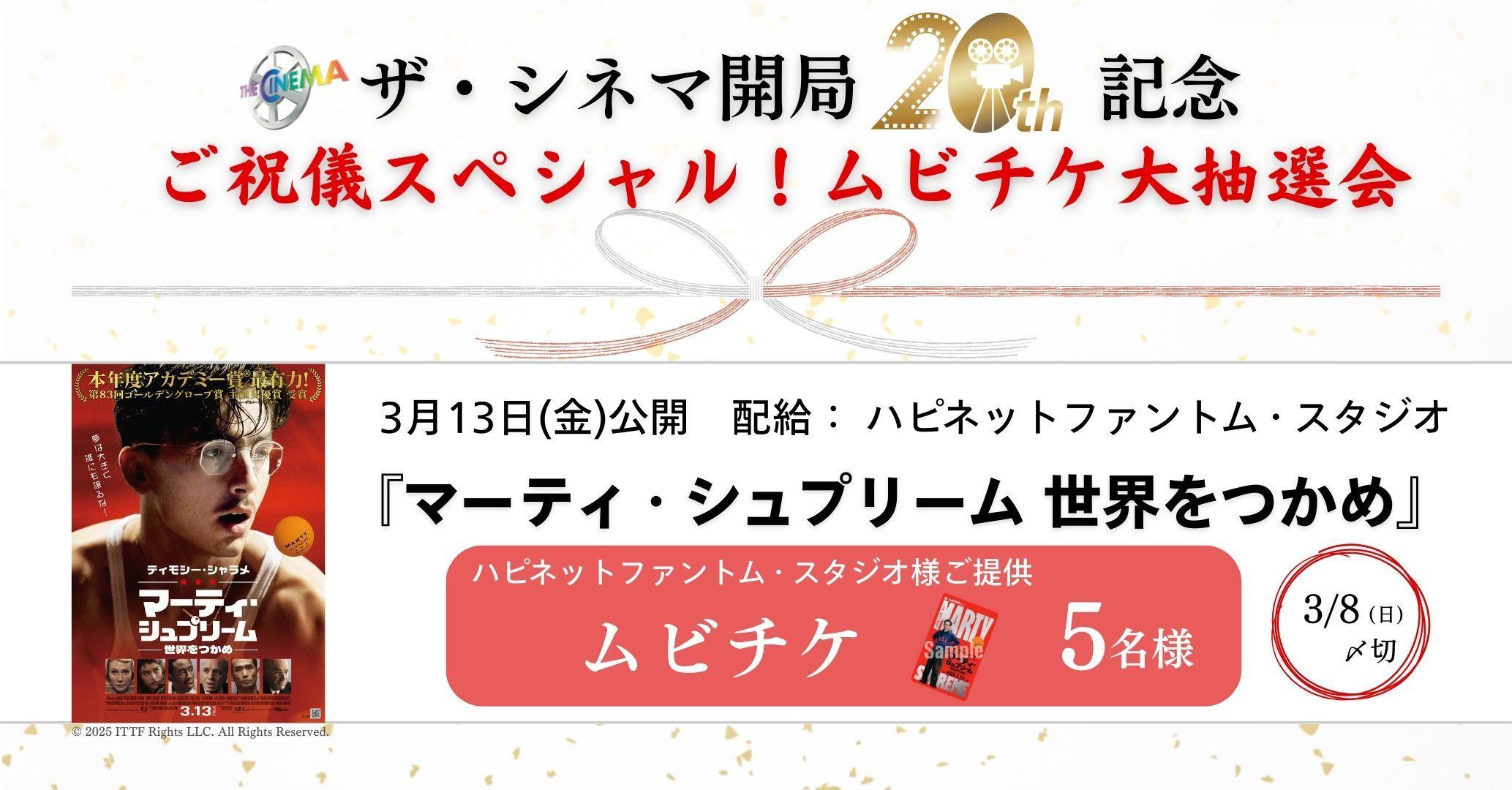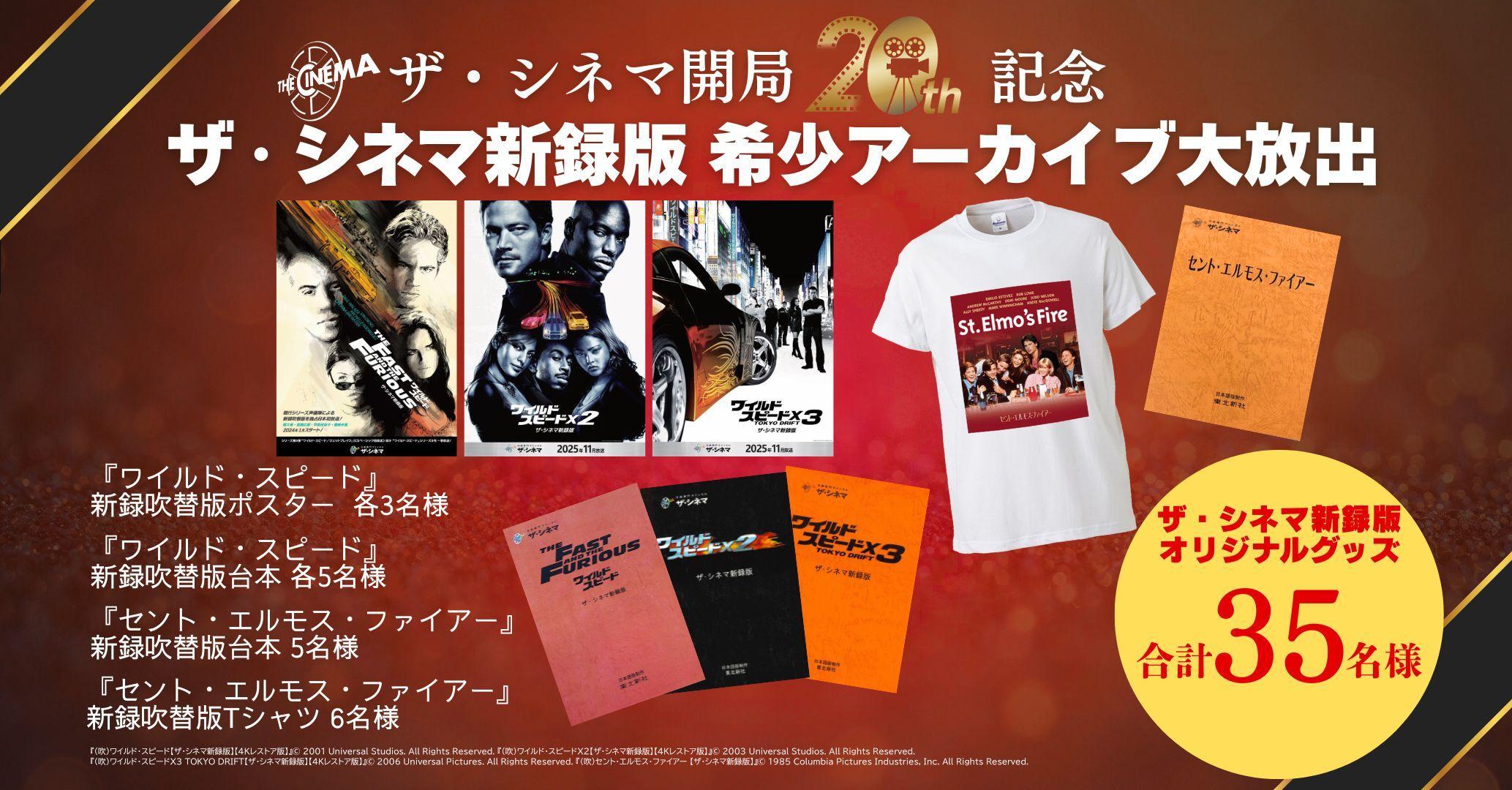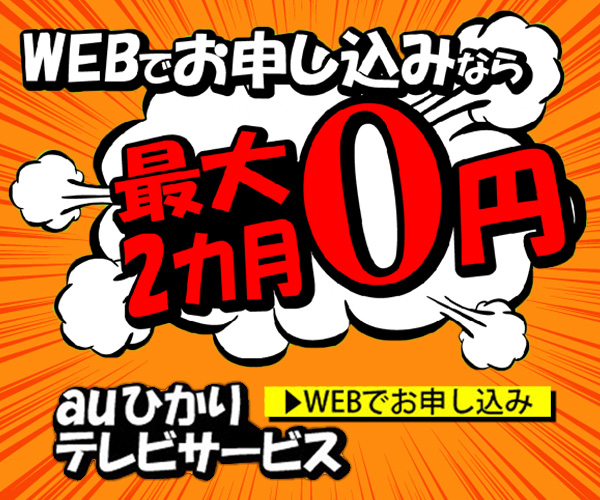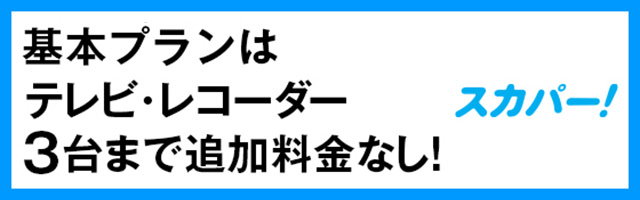RANKING
人気のページをチェック!
INFORMATION
インフォメーション
-
2025.11.27
-
2025.09.18
【ザ・シネマ】『ワイルド・スピード』新録吹替続編制作決定&シリーズ全11作一挙放送!高橋広樹、浪川大輔、川島得愛ほか新録吹替キャスト収録後コメントも到着!
-
2026.01.21
-
2025.12.17
-
2025.08.19
-
2025.08.19
-
2024.06.19
-
2020.09.01
-
2020.09.01