

『スクリーン』1979年2月号
アメリカン・ニューシネマが隆盛から衰退を迎え、革命児スティーヴン・スピルバーグが登場し、「スター・ウォーズ」が映画史を塗り替えるヒットを記録した。ものすごく大雑把にいうとそれが1970年代の映画界の大きな流れかもしれない。
そんな時代に映画ファンになった自分はなんてラッキーなんだろうと思うこともある。まだ人間が人間の映画を作っていて、古い才能と新しい才能が入り乱れていた時代に、リアルタイムで青春期を送った最後の証言者のような気分になることがあるからだ。今ではわずかにしか残っていない“名画座”も人気番組がかかれば超満員だったし、地方の映画館では二本立て興行が普通だった。いまのようなシネコンなど存在せず、ロードショー大劇場の華やかな雰囲気と、安価で名作を見られる名画座の空気を満喫して栄養補給し、さらには毎日どこかの局が放映していた洋画番組を山ほど見て育つことができたのだから。
誰でもそうかもしれないが、映画を見始めたころに出会った作品の数々は、それが傑作でもつまらなかった作品でも、ずっと忘れることができない。私の場合も特に70年代の映画は、時々BSやCS放送で見かけると、懐かしくてついつい最後まで見てしまうものだ。この度、ザ・シネマが特集する「バック・トゥ・ザ あの頃/70年代編」などはまさにそんな私のツボにはまりまくりだ。そのラインナップを見ていくと……

『小さな恋のメロディ』
『小さな恋のメロディ』は、最初は日曜洋画劇場で見た。翌日の教室は小さなヒロイン、トレーシー・ハイドの話題で持ちきりだ。自分たちとあまり年の変わらないイギリスの男の子と女の子が、当たり前のように結婚宣言する衝撃的な内容なのに、映画自体はビージーズの爽やかな名曲に彩られ、英国の学校らしい制服やロンドンの街並みと、夢のような風景が繰り広げられ、日本の思春期の少年少女のハートをわしづかみにしたものだ。この映画に流れる抒情というべきものは、日本でしかヒットしなかったという逸話を納得させるほど、日本人の心理にぴったりだ。

『スクリーン』1977年4月号
『がんばれ!ベアーズ』のテータム・オニールもまるっきり同世代。少年野球チームで紅一点の彼女がものすごいスピードボールで男の子バッターたちを次々空振りさせる勇姿に、男子が萌えたのはごく自然。私は当時、テータムと同い年のライバル?ジョディー・フォスターの方が好きだったが、テータム旋風は凄まじく、その頃読んでいた“スクリーン”でもあっという間に人気女優1位の座に。
『がんばれ!ベアーズ』は77年正月映画だったが、同じ77年正月の恋愛ものとして公開された『ラストコンサート』も日本では大ヒットした。いまも“難病もの”というジャンルは存在するのかもしれないが、このイタリアと日本の合作は(日本らしさはかけらもないが)、ヒロイン、パメラ・ビロレッジのキュートさと、そんな彼女が愛するのが中年のオヤジ(元大物ピアニストだけど)という変わった設定で、男女ともに観客の心を捉え、美しい主題歌、世界遺産モンサンミシェルの幻想的な風景と相まって、夢のような悲恋物語を優しいオブラートで包みこんだ。

『ラストコンサート』
難病・悲恋ものといえば代表作は『ある愛の詩』だ。これもフランシス・レイの甘美なメロディと雪のセントラルパークといった抒情的な名場面がすぐに思い浮かぶ。これも初めて見たのはTV(たしか水曜ロードショー)だったが、アリ・マッグローの声を山口百恵、ライアン・オニールの声を三浦友和という当時のゴールデン・コンビが演じて話題になったことも懐かしいかも。
またこのころのアメリカのヒット作は、本国で公開されてから、半年~一年後に公開されるのも多かったので、やはり“スクリーン”のような映画雑誌は情報源として貴重だった。冒頭で書いた『スター・ウォーズ』は全米77年夏の大ヒット作だが、日本では78年夏公開で、映画ファンの好奇心を一年間煽りまくった。同じ77年全米大ヒット作『サタデー・ナイト・フィーバー』の日本公開も「SW」と同時期の78年夏。『土曜の夜はフィーバーしようぜ』という宣伝文句が浸透し、フィーバーが流行語になったのは有名な話。そしてジョン・トラヴォルタがミラーボールきらめくディスコホールで踊るシーンは、まだアメリカン・カルチャーに限りない憧れを持っていた時代の若者たちに火をつけて大ヒット。『小さな恋のメロディ』同様、ビージーズがまたまた『ステイン・アライブ』他のナンバーで、その年のミュージック界を席巻した。

『グリース』
本作で一躍時の人となったトラヴォルタが、勢いに乗って主演したのが青春ミュージカル『グリース』。共演は当時人気ナンバーワンの歌姫オリヴィア・ニュートン・ジョンで、二人の歌う「愛のデュエット」が記録的セールス。結局「サタデー…」と「グリース」がその年の全米サントラ売上1位と2位を独占したが、そのメロディはいま40~60代の人なら知らないはずがない。もちろん日本でもお正月映画として大ヒットで、私の地元(千葉)の映画館では、通常ロードショー作も二本立てなのに、この映画は一本立て公開で、毎回超満員だった気がする。
大ヒットした『スター・ウォーズ』や『サタデー・ナイト・フィーバー』が全米公開された年、アカデミー賞を獲ったのはウッディー・アレンの小品ロマコメ『アニー・ホール』だったが、同作で主演女優賞を獲ったダイアン・キートンも時の人になった。彼女がやはり同じ年に主演して、ちょっとしたセンセーションを呼んだのが『ミスター・グッドバーを探して』。
年頃の女教師が夜な夜なバーに通い、セックスの相手を探すという内容。このころ、ハリウッドは女性映画ブームというムーブメントもあって、ジェーン・フォンダの『帰郷』『ジュリア』、ジル・クレーバーグの『結婚しない女』、シャーリー・マクレーンの『愛と喝采の日々』など女性が主役の秀作が数多く誕生していた。「ミスター…」もそんな中の一本と言われたが、たしかにこの時代のアメリカ映画は、まだ大人向けの優れた人間ドラマが多かったと思う。
だから当時の映画雑誌にも大人の香りが漂っていた。中高生の映画ファンがちょっと背伸びして、外国のスターや文化のことを覗き見る──そんなことが、周りの友人たちより自分を少し大人びていると感じさせてくれたような気もする。70年代の“スクリーン”には女優たちのヌードグラビアも平気で載っていたし、ポルノ映画の紹介もあったから、学校に持っていくと男の友人たちに『貸して、貸して』と取り上げられ、回し読みされたものだった。まさか自分がそんな愛読誌の編集長になるとは、そのころ考えてもいなかったが、70年代を思い出すと、どこの学校にも一人はいたであろう、ただの映画好き少年だった自分が甦ってくる。だから時々70年代の映画をTVで見かけると、そのころの洋画にワクワクしていた気分を思い出して、思わず見入ってしまうのかもしれない。第1弾も素晴らしいラインナップだが、この後も、ザ・シネマには70年代特集第2弾、第3弾をぜひお願いしたいところだ。



70年初頭の女性の印象的なヘアスタイルと言えば、センターパートの黒髪ストレートロングヘアだ。ナチュラル志向だった60's末のヒッピーからの影響が70年代前半まで続いていたのだ。日本の女性アイドルにも多かったこの髪形だが、外国人スターで一人あげるとすれば1970年の『ある愛の詩』主演のアリ・マッグローだろう。飾らず、清純な、もっと言えば清貧な雰囲気さえ漂うこの髪型が、貧乏女子大生の涙涙の悲恋物語によく似合った。

70年代半ば、ベトナム戦争もようやく終結し、暗い時代はひとまず終わったものの、アメリカは慢性的不況にあり、治安も悪化していた。そんな世相を反映してか、派手で享楽的、でも安い、しかしシックな(『チープ・シック』というファッション指南書が流行った)服装術がトレンドとなる。
その典型例が1977年の『サタデー・ナイト・フィーバー』でのジョン・トラボルタの格好だ。あの純白の3ピースのスーツは、トラボルタのためにわざわざ誂えたオーダーメイド、ではなく、コスチューム・デザイナーの女性とトラボルタが買ってきたもの。実はそこらの洋服屋で売っていた既製服なのだ。監督からの経費節減命令で衣裳部にシワ寄せがいった結果が、あのスーツだったわけだが、見事に“チープ・シック”な時代の空気感とマッチして、映画服飾史に残る名衣裳となり、それだけにとどまらず、真似する若者が70年代後半には世界中で大量発生した。

そして翌年。またもトラボルタはトレンド・セッターとなる。もとはブロードウェイ・ミュージカルだった『グリース』。その1978年映画版に主演した。この映画が、すでに流行しつつあった50年代リバイバル・ブームの決定打になる(50年代の高校が舞台の"ハイスクール・ミュージカル"なのだ)。
フィフティーズ人気は、73年のスピルバーグ監督作『アメリカン・グラフィティ』に始まるが、『グリース』が第2のピークをもたらし、その結果、アメリカが最も輝いていた古き良き時代、オールディーズな50’sにあこがれる現実逃避的なノスタルジアが、70年代末のトレンドとなった(最近の日本での昭和30年代ブームによく似ている)。そして、続くあたらしい時代のファッション、50年代ファッションに大きく影響を受けた80年代前半のファッションの方向性を、決定づけることにもなったのである。
(文/編成部 飯森)


“銀幕のスタア”という存在は昔からいたが、70年代、“アイドル”的な外国映画スターが登場する。これは、外国人スターを迎える日本側の文化状況の大きな変化による。余談ながら、まずこの点に触れなければ話を先に進められない。
日本の“アイドル”の起源には諸説あるが、『スタ誕』、『君スタ』といったオーディション番組の流行や、「となりの真理ちゃん」に代表されるように、70年代は庶民性や親近感が商品価値を持ち、好んで消費された初めてと言っていい時代だった。
玄人っぽくない、あるいは、本当についこの間までずぶの素人だったティーンエイジャーたち。彼らは、必ずしも絶世の美男美女である必要もないし、超絶歌唱力や天才的演技力を備えている必要もない。そんな“普通の”若者たちのけなげな頑張りを、愛でる。心から応援する。この、日本独特のエンターテイメントの形こそが“アイドル”だ、という考察が存在し、それは70年代に始まる、とされる。

その流れが、外国人映画スターにも波及したのが70年代だ。その典型が73年『エクソシスト』のリンダ・ブレア、今回放送される『小さな恋のメロディ』のマーク・レスター、トレイシー・ハイドたちや、『ラストコンサート』のパメラ・ヴィロレッジである。特にトレイシー・ハイドは『小さな恋のメロディ』以前はほとんど素人で、しかも以降もあまり女優としては活動せず本国イギリスでは素人同然であり続けたが、日本ではたった1本の主演映画だけで局地的な人気を長く誇った。
あまりにも普通っぽい、玄人っぽくない美少女の無垢さ。手の届きそうな、すぐ隣りにいそうな距離感。それこそが“アイドル”の核心であるとしたら(それはAKB時代の今日も変わっていないが)、トレイシー・ハイドこそはまさしく“アイドル”だった。
『がんばれ!ベアーズ』のテイタム・オニール。もちろん彼女は史上最年少アカデミー助演女優賞ウィナーであり、天賦の演技力に恵まれた不世出の天才子役ではあったが、その庶民的で普通っぽいルックス、日本人が空想するガール・ネクスト・ドア(アメリカ版となりの××ちゃん)感は、これまた“アイドル”に不可欠の天稟であり、彼女もまた代表的な70年代外国人“アイドル”女優だった。
以上、狭義の“アイドル”の代表的存在としてトレイシー・ハイドとテイタム・オニールに特に言及したが、広義のアイドル、すなわちアイドルを“人気スター”の同義語だと定義するのであれば、さらにここに『ある愛の詩』のアリ・マッグローや『サタデー・ナイト・フィーバー』のジョン・トラヴォルタまでもが含まれることになるだろう。
しかし、筆者にとっての外国人“アイドル”は、やはり、来日時にお仕着せの振り袖やら浴衣やらを無理やり着させられて、その和コス姿でカメラに笑顔を振りまく、どこまでもけなげで、普通っぽくて親近感のわく、映画雑誌のグラフ特集やピンナップによく登場していたティーンエイジャーの少女たちなのである。
(文/編成部 飯森)

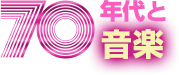
今回の特集には71年の『小さな恋のメロディ』と77年の『サタデー・ナイト・フィーバー』が含まれるが、もし70年代を代表する映画音楽を尋ねたら、ビージーズによるこの2作のテーマ曲はおそらく上位にランクインしてくるに違いない。
前者のテーマ曲「メロディ・フェア」は、ノスタルジックでメロウな“メロディ”と、可憐な少女を見守るような優しいリリックが、この映画とトレイシー・ハイドのために書かれたようなナンバー。
実は60年代末のアルバムに収録されていた既存の曲なのだが、本作の主題歌となってとりわけ日本人に深く愛され、シングルカットされ、日本では以後も数々のアーティストによってカバーされた。日本人にとって、まさに70年代映画音楽筆頭格の一曲と言える。
一方、後者のテーマ曲「ステイン・アライヴ」は、ビージーズが大きく路線変更した後に発表された、「メロディ・フェア」と同じグループの楽曲とは思えないほどのファンキーなディスコチューン。世界的に大ヒットし、各国ヒットチャート1位に長く居座り続け、グラミー賞最優秀アルバム賞にも輝いた。日本人だけでなく全世界の人が共有する70年代の思い出の一曲である。

忘れじの70年代映画音楽はこの他にも枚挙にいとまが無い。今回の特集に含まれる作品の中では何といっても、70年度アカデミー作曲賞に輝く、映画音楽の大家フランシス・レイによる『ある愛の詩』だろう。この難病悲恋ものの"ラブ・ストーリー"は、物悲しくも美しすぎるテーマ曲と「愛とは決して後悔しないこと」の名ゼリフによって、映画史に残る傑作となった。巨匠フランシス・レイの楽曲は、他にも『男と女』、『白い恋人たち』、『雨の訪問者』のワルツなどが日本人に好まれ、イージーリスニングの定番となっていった。

日本人に愛されたという点では『ラストコンサート』も外せない。こちらも難病悲恋もの。音楽映画ということもあって、一曲だけでなく印象に残る曲が幾つも一本の映画に詰まっていた。軽妙で滑稽味もあるメインテーマは、物語の結末を知って聴くとどこか物悲しい響きも。「ステラの夢」の美しく儚く、中盤で情熱的に弾き上げていくピアノソロの旋律は、まさにヒロイン・ステラを象徴する名曲だ。ピアノソロから静かに始まる「ステラに捧げるコンチェルト」は、クライマックスに相応しい盛り上がりで観客に涙をもよおさせた。
こう振り返ってみると、「ステイン・アライヴ」のような世界的ヒット曲も思い出深いが、アジアの一隅の日本でとりわけ愛聴された曲の、なんと多かったことか!「メロディ・フェア」も『ある愛の詩』のテーマも、そして『ラストコンサート』の幾つもの名曲たちも、日本人の心の琴線に触れ、長く親しまれていった。この一事をとっても、70年代は映画ファンにとって豊かな時代であったと言えるだろう。
(文/編成部 飯森)