検索結果
-
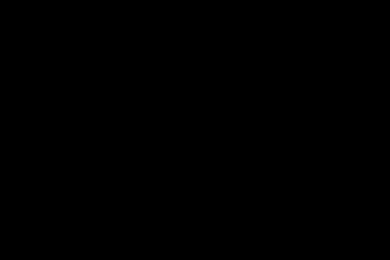
PROGRAM/放送作品
栄光のアカデミー賞(1973)
世界中が注目する映画の祭典、アカデミー賞。その輝かしい歴史と魅力に迫る!
2月15日から放送の【アカデミー賞大特集】にあわせて、過去30年にわたる受賞作品紹介からインタビュー、賞レースの裏側まで、アカデミー賞の魅力を余すことなくお伝えする、映画ファン必見の特別ミニ番組。
-

COLUMN/コラム2016.01.15
僕が結婚を決めたワケ
シカゴ。ベンチャー企業を営むロニー(ヴィンス・ヴォーン)は「会社が軌道に乗るまでは生活の安定が保証出来ないから」と、長年のガールフレンドのベス(ジェニファー・コネリー)に結婚を切り出せないでいた。しかし共同経営者で親友のニック(ケヴィン・ジェームズ)とその妻ジェニーヴァ(ウィノナ・ライダー)から「早くプロポーズをしないと彼女を失うぞ」と忠告され、ようやくゴールインする決意を固めたのだった。 ところがプロポーズの下見に訪れた植物園で、ロニーはジェニーヴァと年下のイケメン・マッチョ(チャニング・テイタム)の浮気現場を目撃してしまう。おりしも会社は存続の命運がかかったプレゼン準備の真っ最中。小心者のニックに真実を告げたら、仕事に影響が出てしまうことは間違いなしだ。友情と仕事にがんじがらめになったロニーは、ニックに何も言い出せなくなってしまうのだった……。 そんなプロットを持つ『僕が結婚を決めたワケ』の監督が、あの巨匠ロン・ハワードであることを知ったらビックリする映画ファンは多いんじゃないだろうか。しかもハワード、本作をトム・ハンクス主演のダン・ブラウン原作映画第二弾『天使と悪魔』(09年)と男気F1ドラマ『ラッシュ/プライドと友情』(13年)の間に撮っている。わけわかんない! でもよく考えてみればハワードの俳優時代の代表作は『アメリカン・グラフィティ』(73年)やテレビドラマ『ハッピーデイズ』(74〜84年)だったわけだし、監督業に進出してからも、主演を兼ねた『バニシングIN TURBO』(77年)、マイケル・キートンの出世作『ラブ IN ニューヨーク』(82年、キートンがパンツ一丁でニューヨークの街角を歩くシーンは『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』(14年)でオマージュを捧げられた)、そしてトム・ハンクスとの初タッグとなった『スプラッシュ』 (84年)といった初期作品はコメディばかりだった。 一見シリアス一辺倒になっていたように見える近年だって、ジェイソン・ベイトマンやマイケル・セラのブレイク作にもなったカルト・コメディ・シリーズ『ブル~ス一家は大暴走!』(03年〜)をプロデュース、慇懃無礼なトーンのナレーションまで担当して番組の生み出す笑いに貢献している。『僕が結婚を決めたワケ』はハワードにとって異色作ではなく原点回帰作なのだ。 そんなハワードにとっては重要な本作の主演俳優に彼が選んだのがヴィンス・ヴォーンだった。いや、コラボレイターといった方が相応しいかもしれない。というのもこの作品、製作総指揮にはヴォーンも関わっており、彼の過去のプロデュース兼主演作とも作風が似通っているからだ。 ここで、日本ではあまり語られることがないヴィンス・ヴォーンのキャリアを振り返ってみよう。ヴォーンは、70年ミネソタ生まれのシカゴ育ち。俳優デビュー作はアメフト青春映画『ルディ/涙のウイニング・ラン』(93年)だった。この作品の撮影現場で、彼はやはりこれがデビュー作だったジョン・ファヴローと出会って意気投合する。二人は、オーディションに挑戦しては失敗し、酒を飲みながら愚痴を言い合う生活をロサンゼルスで送るようになった。やがてファヴローはヴォーンとの日々を脚本化してスタジオに売り込みをかけ、映画化に成功する。それがファヴロー自ら主演も務めたコメディ『スウィンガーズ』(96年)だった。 この作品で、ファヴローの親友役を実生活そのままに演じたヴォーンは大ブレイク。精悍なルックスが買われて、『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(97年)やリメイク版『サイコ』(98年)に出演。ジェニファー・ロペスと共演したSFXスリラー『ザ・セル 』(00年)は全米ナンバーワンに輝くなど、スター街道を駆け上がっていった。 当時の彼の呼び名は何と<ネクスト・マーロン・ブランド>! だが多くの俳優にとっては勲章のように感じられる呼び名は、ヴォーンにとっては嬉しくも何ともないものだった。むしろ<友情に厚いお気楽男<役でブレイクしたのに、ルックスばかりが騒がれて場違いな場所に来てしまったと思っていたに違いない。そんなところに救いの神が現れた。ベン・スティラーである。スティラー演じる主人公の兄役を演じた『ズーランダー』(01年)をきっかけに、彼はスティラー率いる俳優集団、所謂「フラットパック」との共演を繰り返し、コメディ映画に専念するようになっていった。 ルーク・ウィルソンやウィル・フェレルと共演した『アダルト♂スクール』(02年)、スティラーと共演した『ドッジボール』(04年)、そしてオーウェン・ウィルソンと組んだ『ウェディング・クラッシャーズ』(05年)といった大ヒット作でのヴィンス・ヴォーンのキャラクターは常に一貫している。それは<一見イイ加減だけど、恋愛よりも友情を選ぶ熱い男>だ。この頃急激に太ってしまい、女性ファンの多くを失ってしまったヴォーンだが、それ以上に同性からの圧倒的な支持を獲得。ヴォーンは一躍コメディ・スターの仲間入りをしたのだった。 そんなヴォーンが、プロデュースを兼務する形で発表した一連の主演作は、より同性のファンに向けて作られている。ジェニファー・アニストン演じる恋人と破局に至っていくまでを淡々と描いた『ハニーVS.ダーリン 2年目の駆け引き』(06年)、ヴォーンとリース・ウィザースプーン扮する夫婦がそれぞれの離婚した両親の家をクリスマスの日に巡り歩きながら人間関係に永遠など存在しないことを悟っていく『フォー・クリスマス』(08年)、大物監督になった旧友ジョン・ファヴローと共同で脚本も手がけた夫婦和合セミナーがテーマの『カップルズ・リトリート』(09年)、そして精子バンクに登録していたせいで独身でありながら何百人もの子どもの父親になっていたことを主人公が知る『人生、サイコー!』(13年)。どの作品も、男女関係を男の視点から本音で語ったビターなコメディばかりだ。 「自分勝手」「女性のことを分かっていない」そんな批判を受けてもヴォーンの視点は一切ブレない。作品の舞台の多くが今なお彼が暮らす地元シカゴ(ハリウッド・スターでロサンゼルスでもニューヨークでもない街に住んでいるのはとても珍しい)であることは、こうした作品のヴィジョンがヴォーン本人から生まれたものであることを象徴している。そんな側面からも『僕が結婚を決めたワケ』がロン・ハワードの監督作であると同時にヴィンス・ヴォーンの作品だということが、映画を観ると分かってもらえると思う。 最後に本作でヴォーンの<相手役>に扮したケヴィン・ジェームズについても触れておきたい。65年ニューヨーク生まれの彼はスタンダップ・コメディアンとしての活動を経て、シットコム『The King of Queens』(98〜07年)でブレイク。親友のアダム・サンドラーとは『チャックとラリー おかしな偽装結婚!?』(07年)や『アダルトボーイズ青春白書』(10年)、『ピクセル』(15年)などで再三共演しており、『モール★コップ』(09年)に始まる主演映画は全てサンドラー製作である。 ベン・スティラーとアダム・サンドラー自体は古くからの友人なのだが、それぞれがあまりにビッグだからか、二つの派閥が絡むことはあまり無い。そういった意味でも本作は画期的な作品である。これをきっかけに今後、色々な組み合せの共演作が実現することを期待したいものだ。
-

PROGRAM/放送作品
ハンニバル
華麗なる殺人鬼、ハンニバル・レクター博士が、FBI特別捜査官クラリスと再会!
アカデミー賞を受賞した前作『羊たちの沈黙』から10年を経て公開され、衝撃のラストが全世界を震撼させた続編。クラリス役はジョディ・フォスターにかわってジュリアン・ムーアが演じる。
-

COLUMN/コラム2016.02.15
ふたりのパラダイス
ニューヨーク。会社員のジョージ(ポール・ラッド)は、自分探し中の妻リンダ(ジェニファー・アニストン)を養うために仕事に励んでいた。ところがある日、会社がFBIによる業務停止処分を受けたことであえなくクビになってしまう。 やむなくアトランタに住む兄を頼って都落ちする二人だったが途中、偶然立ち寄ったヒッピー・コミューンで金銭に縛られない生き方を知り、これまで感じたことがない喜びを経験する。「ここがパラダイスだ!」コミューンへの永住を決意したジョージとリンダだったが、ニューヨーカーだった二人には理解不能なコミューンの風習や掟がその前に立ち塞がる。遂には二人の間にも隙間風が吹くようになってしまい …。 それまでの常識が崩れ落ちる瞬間に、人は笑う。だからコメディ映画にとって、2008年の世界的金融危機(いわゆるリーマン・ショック)は格好の題材だった。何故なら今まで「頭が良い人たちがマジメに働いている」と信じられていたアメリカの金融業界が、素人を騙すことしか考えていない詐欺まがいの集団だったことが明るみになってしまったのだから。 その証拠と言うわけではないけれど、あの事件から現在までわずか8年ほどしか経ってないにも関わらず、金融危機を題材にしたコメディ映画の多さと言ったらない。例えばベン・スティラーとエディ・マーフィの共演が話題を呼んだ『ペントハウス』(11年)。一見すると単なる泥棒コメディなのだけど、実際はスティラー扮する高級タワーマンションの管理人が、従業員仲間の年金を詐欺まがいの投資で台無しにしてしまった悪徳投資家へのリベンジを描いたものだった。 やはり一見お気楽な刑事コメディに見えるウィル・フェレルとマーク・ウォールバーグの共演作『アザー・ガイズ 俺たち踊るハイパー刑事!』(10年)も地道に働く庶民を食い物にする金融機関の横暴がテーマだった。エンド・タイトルでは金融危機を引き起こしながら、法律で裁かれた金融関係者が殆ど居ないことが具体的なデータで挙げられている。 この隠れた意欲作の監督兼脚本家を務めたアダム・マッケイが、クリスチャン・ベールやスティーヴ・カレル、ブラッド・ピットといった豪華キャストを迎えて撮ったのが、今年のオスカー賞レースで数多くのノミネートを獲得した『マネー・ショート 華麗なる大逆転』(15年)だった。 サブプライム市場の崩壊を事前に予測した金融トレーダーたちの活躍を描いた実録映画ではあるものの、巨額の利益を上げながら主人公たちの表情がいずれも冴えなかったのが印象的だった。無理もない。金融市場が崩壊したことで確かに銀行の首脳陣は退陣を余儀なくされたけど、その際に彼らが億単位の退職金を得ていたのに対して、庶民は不況の影響で仕事を失い、巨額の負債に苦しむことになったのだから。 ブラック・コメディとしても鑑賞可能なデヴィッド・フィンチャー監督作品『ゴーン・ガール』(14年)の主人公であるニックとエイミーも、金融危機をきっかけにマスコミ界の仕事を失い、夫の故郷のミズーリ州に都落ちせざるを得なくなった夫婦だ。引っ越し先で妻のエイミーが引き起こす事件は、元の生活に戻ろうとするあまりの行為だったことを考えると、たしかにヒドい人ではあるものの(詳しくは映画を見れば分かる)彼女だってある意味、金融危機の被害者だったと言えないこともないのである。 そして『ふたりのパラダイス』の主人公であるジョージとリンダもまた金融危機の被害者といえる。しかも都落ちを決意するまでの経緯は『ゴーン・ガール』のニックとエイミーそっくり。但しその行き先をヒッピー・コミューンにしたことで、もっとブライトな笑いに満ちた仕上がりになっている。 資本主義から逃れて自由な生き方を模索するヒッピーたちが、都会から離れて農村や山奥に集団で住むことによって自給自足を試みた共同体がヒッピー・コミューンである。 「ヒッピー・コミューン?『イージーライダー』には出てきたけど、そもそも今も実在するの?」そう思ってしまう日本人は多いかもしれない。たしかに全盛期である60〜70年代に比べると随分と数は減ってしまったけど、ヒッピー・コミューンは今もあちこちで存続中だ。ウィノナ・ライダーやジャック・ブラックのようにコミューン育ちのハリウッド・スターがいるくらいだし、その思想はシリコン・ヴァレーのIT起業家やブルックリンのヒップスターにも受け継がれている。 本作では、幻覚剤や無農薬農業、菜食主義、フリーセックス、そして新生児の胎盤食い(ヒッピーは動物が出産後に胎盤を食べることを真似て、煮たり焼いたりして食べているらしい。もっともとてもマズいらしいけど)といった<コミューンの儀式あるある>がことごとくギャグになっていて、ヒッピー・カルチャーを知っていたら最高に笑えること間違いなしだ。 こうしたヒッピー・カルチャーに翻弄される主人公のジョージとリンダを演じているのは、ポール・ラッドとジェニファー・アニストン。ふたりの共演は、『私の愛情の対象』(98年)で既に実現しており、アニストンの人気を決定づけたシットコム『フレンズ』の末期(02〜04年)にはラッドも準レギュラーで出演していたりと、その交流歴は長い。但し前者ではゲイの男とストレートの女性の親友同士、後者では「アニストンの親友の恋人がラッド」という間接的な関係だったので、今回が初めての男女関係を演じることになる。 何でも、ラッドの親友で本作の監督兼脚本家であるデヴィッド・ウェインから本作のアイディアを初めて聞いた際に、ラッドは「遂にジェニファーと本格共演する時が来た」と直感し、彼女を誘ったのだそう。多忙なジェニファーもそれに応えて、念願の共演が実現したというわけだ。私生活でも友人同士というだけあって、さすがに息はぴったりで、途中二人の間に隙間風が吹く際には、ハッピーエンドが分かってはいてもハラハラしてしまう。 そんな二人を、『『M*A*S*H』』(72〜83年)やウディ・アレン作品で知られるベテランのアラン・アルダ(奇しくも彼は『ペントハウス』で悪得投資家を演じている)や『ライラにお手あげ』(07年)の怪演が未だに忘れられないマリン・アッカーマン、『シックス・フィート・アンダー』(01〜05年)のローレン・アンブローズら個性派たちが好サポート。中でもコミューンのリーダー格のセスを演じるジャスティン・セローは、いかがわしさ満点で強烈な印象を残してくれる。 日本の映画ファンには『マルホランド・ドライブ』(01年)の映画監督役や『チャーリーズ・エンジェル フルスロットル』(03年)の悪役くらいでしか知られていないセローだけど、近年は『LOST』のクリエイター、デイモン・リンデロフが手掛けるミステリー・ドラマ『LEFTOVERS / 残された世界』に主演したことで人気爆発。また『トロピック・サンダー/史上最低の作戦』(08年)や『アイアンマン2』(10年)、『ロック・オブ・エイジズ』 (12年)の脚本も書いている才人である。 そんな多才な才能に惹かれたのか、アニストンとセローは本作での共演をきっかけに交際をスタート。昨年遂にゴールインを果たしている。結果的にポール・ラッドは親友のジェニファーに家庭という名のパラダイスをもたらしたのだった。 こうした事実を踏まえながら、リンダとセスの2ショット・シーンを観てみるのも本作の隠れた楽しみだろう。 Film © 2012 Universal Studios. All Rights Reserved.
-

PROGRAM/放送作品
ハンニバル・ライジング
[R-15]美しき殺人鬼、誕生!トマス・ハリス原作のハンニバル・シリーズ映画化最新作!
『羊たちの沈黙』『ハンニバル』『レッド・ドラゴン』と続く、殺人鬼ハンニバル・レクター博士の映画化シリーズ、第4弾!美形俳優ギャスパー・ウリエルが復讐に燃える青年期の博士を妖艶に演じた話題作!
-

COLUMN/コラム2017.10.20
『レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語』に出てくる「パスタ・プッタネスカ」こと「風俗嬢パスタ」のレシピに挑む!!!
写真/studio louise 今回は『レモニー・スニケットの世にも不幸せな物語』の中で印象的に登場する、「パスタ・プッタネスカ」の作り方をご紹介しましょう。 映画チャンネルなのでまずは映画紹介から。 ボードレール家の子供たちは火事で両親を失った。少女発明家の長女ヴァイオレットと、読書好きの弟クラウス、そして末っ子の赤ちゃんサニーは、オラフ伯爵という遠い親戚に引き取られる。だが遺産目当てのオラフは子供たちを殺して遺産を我が物にしようと画策。子供たちはオラフの元から逃げ、別の遠い親戚に預けられることに。しかし、三文役者のオラフは変装し、周囲の大人たちの目を誤摩化して子供たちに付きまとう。 一見して、超ティム・バートンっぽいダーク・ゴス・メルヘンチックな映像と世界観の映画なのですが、その見立てはハズレてはおりません。そもそも監督に当初ティム・バートンが打診されており、またそのためか、撮影監督に『スリーピー・ホロウ』でアカデミー撮影賞ノミネートの(てか当代最高のカメラマンの)エマニュエル・ルベツキ、美術には完全にバートン組の一員であるリック・ハインリクスといった面々が名を連ねていますからね。 あと、ジム・キャリー扮演の悪党の三文役者オラフ伯爵が変装して遺産狙いで子供たちを追い回すというお話なので、ジム・キャリーの『マスク』ばりの変キャラ七変化や過剰演技が楽しめるのですが、もう一点、これは人それぞれ趣味もあるとは思いますけど、エミリー・ブラウニング史上この時がいちばん可愛いですわ! エミリー・ブラウニング嬢、ロリ系女優としてその後もご活躍。日本風スク水ずん胴(いや、良い意味でね)姿を披露した『ゲスト』、日本風愛と正義のセーラー服美少女戦士役でアクションしまくった『エンジェル ウォーズ』、脱いだ『スリーピング ビューティー/禁断の悦び』、美声を聞かせたレトロキュートなミュージカル『ゴッド・ヘルプ・ザ・ガール』(写真)と、文化系男子好みな作品選定で全幅の信頼を置かれてますが、本作でのゴスロリ黒ドレス姿の可憐さたるや! このエミリー・ブラウニング嬢たち3姉弟が、悪党オラフ伯爵に引き取られてきた初日に即、ディナーを30分で作るよう命じられる。いきなりの家政婦扱い。姉「パスタにしましょう」弟「パスタ・プッタネスカなら、少ない材料で出来るからね」 ということで、ザルの代わりに網戸を、鍋の代わりに痰壷を使い、パスタ・プッタネスカを手早く作るのです。 Netflixオリジナルの連続ドラマ版には、姉弟が図書室に行ってレシピを調べるシーンがあります。[図書室にて]姉「これなら作れそう。パスタ・プッタネスカ!」弟「イタリア語でどんな意味だろう?」姉「(料理本を読み上げ)ニンニクとタマネギを炒めて、オリーヴとケイパー、アンチョビ、刻んだパセリとトマトを入れて煮る」[キッチンにて]ナレーション「パスタを茹でるまでの間、ヴァイオレットはニンニクを炒め、アンチョビを洗って切った。クラウスはトマトとオリーヴの準備。(中略)そして末っ子がパセリを歯で食いちぎる作業を終えると、初めて伯爵の家に来た時の気持ちは消えた。惨めな気持ちは薄れていたのだ」姉「このソース、パパも誉めてくれたはず!」 ええと、これからご紹介するワタクシのレシピでは、タマネギは使いません。甘味が出ちゃうのがイヤなのと、ワタクシが参考にした幾つかのレシピでは使ってませんでしたから。あと、「アンチョビを洗う」という行為は意味がわかりません!英語でもそう言ってるんだけど、ダメ!絶対!! この2点は原作に書かれてないので、文字通りのNetflixオリジナルのアレンジらしい。ダメ!絶対!! あと、弟君に「イタリア語でどんな意味だろう?」と言わせておいて答を劇中で教えないのが、実は、軽くイタズラ心に溢れていて面白い。これも原作に書かれていないNetflixオリジナル台詞みたいなんですが、実は「プッタネスカ」って、子供に意味を教える訳にはいかない、とんでもない意味なのです! 「プッタネスカ」とは「風俗嬢の」という意味で、「パスタ・プッタネスカ」でしたら「風俗嬢パスタ」ということ。これ、イタリアで風俗嬢が客を取る合間にチャチャっと作って手早く食事を済ませていたから、それくらい簡単に作れるお手軽レシピ、ということが語源との説があります。ま、お子様には秘密ということで。 では、前置きはこれくらいにして早速いってみましょう! 【材料(4人分)】 ・唐辛子×2本・ドライオレガノ×2つまみ・ニンニク×1片・チェリートマト×1パック(有っても無くても)・生イタリアン・パセリ×売ってる1袋・トマトペースト(有っても無くても)・パスタ(ここではリングイネ。スパゲッティーでももちろん可。ただ麺が良い)・トマト缶×1缶・ケイパー・アンチョビいっぱい(5尾以上は!味の決め手なので!)・黒オリーヴ(種有りの方が断然味が良いのでオススメ) 【作り方】 ① フライパンにオリーヴオイルを注ぎ、唐辛子とニンニクのみじん切りとアンチョビいっぱいを入れ、超極弱火で熱を入れていく。トマトの食感がお好きならここで生チェリートマトを半分に切ったものも加熱する(別に無くてもいい)。 ② 5分も加熱するとアンチョビが熱で崩れる。この状態まで加熱したら、 ③ この時点でパスタ用の湯を大鍋で沸かし始めること。それと同時にフライパンの方は中火にヒートアップし、イタリアンパセリを除く全ての材料を一斉に投下!すなわち、トマト缶1缶、トマトペースト適量(無くても可)、ケイパーとブラックオリーヴお好みの量、乾燥オレガノを加え、材料外だが塩(適量)も加えて味を調える。 ④ 湯が沸いたらパスタを茹でる。湯が沸くまで15分ぐらいか?そしてパスタの茹で時間は普通7分?アルデンテ着地狙いで6分?超適当だが、トマトソースの方の煮込み時間もそれで十分。この時間を活用してイタリアン・パセリを適当に刻んでおこう。 ⑤ パスタ茹で上がり=ソース煮詰まり完了。パスタをソースに絡め、皿に盛り付け、最後に生イタリアン・パセリをたっぷりと散らす。 【実食】 うん!いつもながら、地味に美味いな!とにかく簡単、ってことが、この料理最大のメリットで、簡単すぎて失敗しようがないのですが、コツはアンチョビをケチらないことですな。肉を使ってないので、味のゴージャス感はアンチョビだけにかかってます。これケチると味気ない貧乏ったらしい味になってしまうので。 にしても、妻が実家出産でしばらく独り暮らししてた頃は、仕事終えて家に帰ったらいつもパパっと作って平日2回ぐらいはこれ食いながら安ワインで映画を見てましたね。やっぱ、映画ですから!自分で言うのもなんですが、映画見るなんて、そこそこオシャレで知的で洗練された趣味だとは思いませんか皆さん!エクスペンダブルズとか!! であるならば、コンビニエントでインスタントな夕食よりかは、手抜きとはいえ多少はこだわった、自分でチャチャっと作る簡単ディナー程度は、映画見る晩には格好つけたいじゃないですか、皆さん!■ COPYRIGHT © 2017 BY DREAMWORKS LLC AND PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
-

PROGRAM/放送作品
パニック・フライト
飛行機という巨大な密室で繰り広げられる知能戦…、はらはらドキドキのサスペンス・アクション
『エルム街の悪夢』、『スクリーム』シリーズで知られるホラー映画職人監督ウェス・クレイブンが、ホラー映画で見せる緊迫感をそのままサスペンス・アクションに持ち込んだ、新境地開拓作。
-

COLUMN/コラム2017.10.10
【再掲載】3つの『ブレードランナー』、そのどれもが『ブレードランナー』の正しい姿だ!
例えば『ゾンビ』のように、公開エリアによって権利保持者が違ったため、各々独自の編集が施されたケースもあれば、『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズや『アバター』のように、劇場公開版とは別の価値を持つものとして、DVDやBlu-rayなど制約のないメディアで長時間版を発表する場合もある。 『ブレードランナー』もそれらのように、いくつもの別バージョンが存在する作品として有名だ。しかし、先に挙げた作品とは「発生の理由」がまったく異なる。いったいどのような経緯によって、同作にはこうしたバージョン違いが生まれたのだろうか? なぜバージョン違いが生まれたのか? それは最初に劇場公開されたものが「監督の意図に忠実な作品ではなかった」というのが最大の理由だ。 映画の完成を定める「最終編集権」は、作品を手がけた「監督」にあると思われがちだ。しかし、その多くは作品の「製作者」が握っており、監督が望む形で完成へと到らないケースがある。『ブレードランナー』もまさしくそのひとつで、1982年に劇場公開された「通常版」は、製作者の権利行使によって完成されたものなのだ。 当然、それに納得いかなかったのが、監督のリドリー・スコットである。醇美にして荘厳な映像スタイルを自作で展開させ「ビジュアリスト」の名を欲しいままにする希代の名匠。そんな完璧主義の鬼が、自らの意図と異なるものに寛容であるはずがない。そう、もともと『ブレードランナー』は、リドリーの意図に忠実に編集されていたのである。しかし製作側が完成前にテスト試写をおこない、参加者にアンケートをとったところ、以下のような驚くべき意見が寄せられてしまったのだ。 「映画に出てくる単語や用語が難しい。“レプリカント”って何? そもそも“ブレードランナー”って何なの?」 「ラストが暗すぎる。デッカード(ハリソン・フォード)とレイチェル(ショーン・ヤング)は、あの後どうなったの?」 こうした意見に製作側が戦々恐々となったのは言うまでもない。そして収益に響いては困るとばかりに、編集に修正を加えるのである。「用語が難しい」という問題には、劇中にわかりやすいナレーションを入れることで対応し、そして「ラストが暗い」には、「レイチェルには限られた寿命がなく(レプリカントは4年しか生きられない)、ふたりは生き延びて仲良く暮らしました」とでも言いたげなハッピーエンド・シーンを追加した。 しかし、今となっては考えられないことかもしれないが、こうした製作側の配慮もむなしく、『ブレードランナー』はヒットには到らなかったのである。 何が問題だったのか? それは懸念された「内容の難解さや暗さ」ではなく、ダークなセンスこそ光る本作を「SFアクション劇」で売ろうとした製作側の大きな宣伝ミスだったのだ。そして皮肉にも、その退廃的な未来図像や哲学的なストーリーが目の利いた映画ファンから絶賛され、『ブレードランナー』は年を追うごとに注目を集め、マスターピースとしてその名を高めていくのである。 ■「ディレクターズ・カット/最終版」(1992年)の誕生 商業性を優先した製作側に、作品を曲解されてしまったとリドリー・スコット監督は考えていた。作品の評価が高まるにつれ、彼は今そこにある『ブレードランナー』が、自分の意図どおりのものでないことにジレンマをつのらせたのである。そして「いつか私の『ブレードランナー』を作る」と、来るべき機会をじっと待っていたのだ。 そして、ついにその祈願が果たされるときがやってくる。1991年、ワーナー・ブラザースが同作のファンの需要に応え、「通常版」の前のバージョンの公開を局地的に展開していた。そう、リドリーの意向に沿った編集版だ。 それに対してリドリーは、 「あの編集バージョンはあくまで粗編集で、未完成のものだ。公開を承認することはできない。これはビジネスの問題じゃなくて芸術の問題だ」 と、公開にストップをかけたのだ。そしてワーナーに対し、ある代案を呈示したのである。 「監督である私の意図にしたがい、新たに編集したものならば公開してもいい」。 この代案が受け入れられ、編集権はリドリーに譲渡される形となった。そしてリドリーは自分どおりの、新たな編集による『ブレードランナー』を発表することになったのだ。それが「ディレクターズ・カット/最終版」である。 ■「通常版」と「ディレクターズ・カット」、ここを見比べよう! 監督の意図に忠実な「ディレクターズ・カット/最終版」は、「通常版」に入れられたナレーションをすべて取り払い、そして最後に追加されたハッピーエンド・シーンも削除したバージョンだ。そこには監督の「混沌とした未来像をありのままに受け止めてほしい」という演出プランが息づいている。 こうした点にこだわりながら、改めて両バージョンを見比べてほしい。ナレーションのない「ディレクターズ・カット/最終版」は、耳からくる情報収集で聴覚を奪われないぶん、視覚を集中して働かせられる。そのため、映像が放つインパクトをより強く受け取ることができるのだ。公開当時、革命的で前代未聞といわれたデッドテックな未来像。その視覚的ショックを、監督の思う通りに実感できるという次第だ。 さらにリドリーは「ディレクターズ・カット/最終版」に新たなショットを付け加えることで、観客がこれまで抱いてきた『ブレードランナー』の固定観念を覆すことに成功している。それが「森を駆けるユニコーン(一角獣)」のイメージ・シーンである。 デッカードが見る「夢」として挿入されるユニコーンの映像。それは彼の同僚ガフ(エドワード・ジェームズ・オルモス)が捜索現場に残した「折り紙のユニコーン」と重なり合う。デッカードの脳内イメージを第三者であるガフが知っているということは、「デッカード自身もレプリカントなのでは?」という疑念を観る者に抱かせるのだ。そしてその疑念こそが「ディレクターズ・カット/最終版」の、もうひとつの変更点=“ハッピーエンドの否定”へとリンクしていく。 「ならば『通常版』は、監督の意図と違うからダメなのか?」 と訊かれれば、それはノーだ。「通常版」固有のナレーションは、1940?50年代に量産された「フィルム・ノワール(犯罪映画)」や「ハードボイルド小説」のスタイルを彷彿とさせる。『マルタの鷹』や『三つ数えろ』『ロング・グッドバイ』など、主人公が自身の行動や考え、感情をストーリーの流れに沿って口述する文体は、フィルム・ノワール、特にハードボイルド小説の「探偵ジャンル」に顕著なものだ。そうした古来の語り口を介することで、『ブレードランナー』もまた「孤独な主人公が犯罪者を追う」古典的な物語であることを認識させてくれるのである。 そういう観点からすれば「通常版」は“未来版フィルム・ノワール”として独自の価値を持つものであり、監督が思うほど「ディレクターズ・カット/最終版」に劣るものでは決してないのである。 ■さらに作品を極めたい?そして「ファイナル・カット版」(2007年)へ リドリーは紆余曲折を経て、自分の意向に沿った『ブレードランナー』を世に出すことに成功した。だが、それだけでは満足しないのがアーティストの性(さが)だろう。「さらに極めたものを作りたい」という思いは、完璧主義者としての彼の奥底に深く根を張っていたのだ。 そうした自身の思いと、多くのファンの作品に対する支持はワーナー・ブラザースを動かした。同社は『ブレードランナー』公開から25周年を迎えるにあたり、改めて同作の権利契約を結び、“究極”ともいえる「ファイナル・カット版」の製作にゴーサインを出したのである。 「ファイナル・カット版」は、基本的には前述の「ディレクターズ・カット/最終版」をアップデートしたものだ。なので「通常版」→「ディレクターズ・カット/最終版」に見られたような大きな違いはなく、下記のようにディテールの修正が主だった変更点である。 【1】撮影・編集ミスによる矛盾の修正 撮影ミスや編集ミスで、カットごとに違うものが映し出されるシーン(不統一な看板の文字など)や、または矛盾を生じるセリフの修正などが徹底しておこなわれている。特に代表的なのは、ブライアント(M・エメット・ウォルシュ)がレプリカントに言及するセリフで「(6体の逃亡したレプリカントのうち)1匹は死んだ」としゃべっていたものを、「2匹が死んだ」と変えている場面だ。これはデッカードが追う残り4体のレプリカント(ロイ、ゾーラ、リオン、プリス)の数に合致させるための変更である。 あるいは修正のために、新たに映像素材を撮影したシーンもある。デッカードに撃たれたゾーラが倒れるシーンで、スタントの代役が如実に分かるミスショットがあるが、ゾーラ役のジョアンナ・キャシディを招いて撮ったアップショットを代役にリプレイスメント(交換)することで解決へと導いている。また人口蛇をめぐってデッカードがアブドルと話すシーンでの、声と口の動きが一致していない問題点には、ハリソン・フォードの実子ベンジャミン・フォード(お父さんそっくり!)の口もとを合成し、同様に解決されている。 【2】特殊効果シーンの一部変更ならびに修正 オプチカル(光学)による合成ショットのブレや、シーンによって左右反転するデッカードの頬傷メイク、あるいはスピナーが浮上するさいに見える、吊り上げるためのワイヤーなど、ミスや製作当時の技術的な限界を露呈した点がデジタル処理で修正されている。またバックプレート(背景画像)が大きく入れ替えられている部分もあり、たとえばロイの死の直後にハトが飛び去るショットは、前カットとの連続性を持たせるために晴天から雨天へとレタッチされ、下部分に写る建造物も新たにデジタル・ペイントされて、違和感をなくしている。 【3】未公開シーンの挿入 デッカードがゾーラを訪ねるシークエンスで、繁華街に登場するホッケーマスクのダンサーなど、未公開だったショットが追加されている。またユニコーンのシーンも1ショット追加され、それにともないデッカードのアップにユニコーンのショットがインサートされる編集処理となり、ユニコーンのシーンはディゾルブ(オーバーラップ)でなくなった。 すべてのバージョンが『ブレードランナー』である ! そう、1982年の『ブレードランナー』初公開から四半世紀の間に、映画の世界には大きな変革が及んだ。「デジタル技術」の導入により、そのメイキング・プロセスや作品の仕上がりに高いクオリティが与えられたのだ。監督とスタッフは「ファイナル・カット版」作成に際し、オリジナルの本編シーン35mmネガ、そして視覚効果シーンの65mmと70mmオリジナルネガをスキャンしてデジタルデータに変換し、すべての編集や修正をコンピュータベースでおこなっている。 その結果、同バージョンは「ディレクターズ・カット/最終版」と比較(あるいは「通常版」と比較)しても、とにかく映像の美しさという点で勝っている。デジタルによる高解像度のスキャンによって、これまでの別バージョンに較べて画面の隅々までが明瞭に見えるようになったし、照明効果の暗かった場面の光度や輝度をデジタル処理で上げることで、暗部に隠れた被写体の可視化に「ファイナル・カット版」は成功している。 また映像面だけでなく、サウンドにおいても微細に加工が施されている。セリフ、効果音、スコアそれぞれのトラックからノイズをデジタルで消去し、それらをリミックスして響きのいい音を提供している。またナレーションを排したために、ところどころで音の隙間が出来てしまった場面においても。スピナー飛行時の通信ノイズや街の雑踏など新たなサウンドエフェクトで補っているのだ。 こうした丹念な修正作業と、リドリー・スコット監督の執念によって、「ファイナル・カット版」は『ブレードランナー』の“完成型”といえるものに仕上がった。とはいえ、デジタルという態勢下で加工された「ファイナル・カット版」に対し、あくまでフィルムベースで存在する「通常版」「ディレクターズ・カット/完全版」の“映画らしい質感”を称揚する者も少なくない。なにより私(筆者)自身、作家性を重んじる立場から「ファイナル・カット版」に感動しつつも、「最初に劇場公開されたものこそオリジナル」という主義でもあるので、すべてのバージョンを観るたびに心が揺れる。だからどの『ブレードランナー』を支持するかは、観る者の嗜好によって一定ではないだろう。 しかし、誰がいかなるバージョンに触れたとしても、やはり『ブレードランナー』という作品そのものが持つ「魅力」と「偉大さ」を、改めてすべての人が感じるに違いない。■ 【3月放送日】 『ブレードランナー』…5日、25日 『ディレクターズカット/ブレードランナー 最終版』…11日、29日 『ブレードランナー ファイナル・カット』…20日、26日 『(吹)ブレードランナー ファイナル・カット』…20日、26日 『デンジャラス・デイズ/メイキング・オブ・ブレードランナー』…5日、20日 TM & © The Blade Runner Partnership. All rights reserved.
-

PROGRAM/放送作品
ビッグ・バウンス
担いだつもりが担がれて…?南国ハワイで繰り広げられる、だまし合いのだまし合い
『ゲット・ショーティ』『ジャッキー・ブラウン』『アウト・オブ・サイト』などの原作で知られる、憎めないアウトサイダーを描く小説家エルモア・レナードの初期小説を、ハリウッド随一の個性派キャストで映画化。
-

COLUMN/コラム2017.10.05
個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年10月】飯森盛良
実は昔っからロマコメがキュンキュンに一番好きという42歳中年ヘテロ妻子ありオヤジです。そういう男子もいるのだ。趣味で見る映画では野郎キャストはどうでもいい。ただヒロインを消費したいだけなんだ。アグリー?あと、バッドエンドなんてお仕事以外では見たかないねえ、嫌な気分は最近のニュースだけで沢山さ。ハッピーエンドだけ見ていたい。アグリー?アグリーな人にだけ全力でオススメしたいのが、近年稀に見るベストだと感じた本作。僕の座右の銘は「いつも心にトレンディを」。イカしたリア充都会暮らし、軽妙洒脱な会話、当然のごとくハッピーエンド。この感じだけで人生を満たしたいんだ僕は!そして一番はヒロインのイモージェン・プーツの愛らしさ。恋に落ちて僕は君をこう呼ぶことにした、「芋ぷぅ」と。■ © 2013 AWOD Productions, LLC. All Rights Reserved