検索結果
-
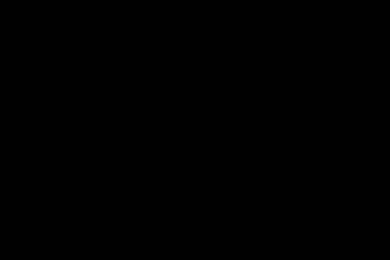
PROGRAM/放送作品
栄光のアカデミー賞(1974)
世界中が注目する映画の祭典、アカデミー賞。その輝かしい歴史と魅力に迫る!
2月15日から放送の【アカデミー賞大特集】にあわせて、過去30年にわたる受賞作品紹介からインタビュー、賞レースの裏側まで、アカデミー賞の魅力を余すことなくお伝えする、映画ファン必見の特別ミニ番組。
-

COLUMN/コラム2017.10.05
個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年10月】うず潮
不慮な事故で死んでしまった彼女がゾンビになっても彼を愛し続ける!元カノ(ゾンビ)と今カノの間で揺れる青年の顛末を描くゾンビ・コメディ!監督は『グレムリン』シリーズなどのヒット作を手がけたジョー・ダンテ。御年70歳を迎えても精力的に作品を造り続ける彼は、『冒険野郎マクガイバー』の新TVシリーズ『MACGYVER/マクガイバー』でも監督しています(スゴイ!)。そんな彼が66歳の時に撮ったのがこの『ゾンビ・ガール』。熟練の技によるおバカ加減が絶妙で、『シッチェス映画祭ファンタスティック・セレクション2015』にて全国劇場公開された話題をさらいました! 三角関係で揺れるホラー映画マニア青年マックス役を、『ターミネーター4』『スター・トレック』新シリーズに出演した新鋭アントン・イェルチンが軽妙に演じ、その彼女でゾンビになっても彼を愛し続けるイタイ役を、『トワイライト・サーガ』シリーズに出演したアシュリー・グリーンがウザさMAXで好演。さらに2012年の「世界で最も美しい顔100人」の第3位に輝いたアレクサンドラ・ダダリオがキュートに今カノを演じています。彼女は『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シリーズ(ザ・シネマで10月放送)にも出演していて、そのお顔はお美しいのひと言。元カノ(ゾンビ)と今カノの美女ふたりに言い寄られる彼の行動にツッコミを入れながら見るとより楽しい1本です!■ ©2014 BTX NEVADA, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.
-
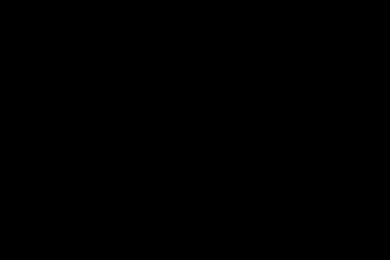
PROGRAM/放送作品
栄光のアカデミー賞(1975)
世界中が注目する映画の祭典、アカデミー賞。その輝かしい歴史と魅力に迫る!
2月15日から放送の【アカデミー賞大特集】にあわせて、過去30年にわたる受賞作品紹介からインタビュー、賞レースの裏側まで、アカデミー賞の魅力を余すことなくお伝えする、映画ファン必見の特別ミニ番組。
-

COLUMN/コラム2017.08.29
個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年9月】キャロル
マーシャル・アーティスト(武道俳優)といえば、ブルース・リー、チャック・ノリス、ジャン・クロード=ヴァン・ダムらのような空手やテコンドーの使い手が主流のハリウッド。その中でもひとり合気道をメインにしたミックス・マーシャル・アーツの信念を貫き、独自のスタイルを確立させたスティーヴン・セガールは、65才を過ぎた今も年数本に出演するペースで現役真っ盛りに活躍しています。不思議なことに、彼のキャリア最高傑作とも称される1992年の『沈黙の戦艦(原題:UNDER SIEGE)』が大ヒットして以降、日本に配給されるセガール作品にはことごとく『沈黙の○○』という邦題が付けられています。チョイ役の作品でも『沈黙~』の冠が堂々と付けられ、DVDのジャケ写ではまるで主役級の扱いなんてことも。そして何を隠そう、本作『沈黙のSHINGEKI/進撃』がまさにそれ。正直に申し上げて、セガールの登場シーンは殆どありません!ハッハー!実にザンネーン!なのですが、それでもキャストが地味に豪華(!)なところが救いのポイント。主演は『CSI:科学捜査班』でおなじみのジョージ・イーズ。新シリーズ『MACGYVER/マクガイバー』で主人公の相棒役に抜擢され、今後ブレイクの予感も!ヒロインには、『新ビバリーヒルズ青春白書』で一躍時のひととなったアナリン・マコード。スーパーボディの彼女が夜のプールでスッポンポン!お色気シーンは美しすぎて男女問わず必見です。そして極めつけは2016年公開『ドント・ブリーズ』で盲目の老人役が記憶に新しいスティーヴン・ラング。強面を活かした役が多い彼ですが、本作でも謎に包まれた男の独特の“怖さ”を、ベテラン俳優ならではの巧みな演技で魅せています。 セガール全開ムービーを期待するとガッカリなところがあるかもしれませんが(笑)、ブレイク必至のライジング・スターたちの好演を観るのもまた一興。9月のザ・シネマで是非お楽しみ下さい。■ (C) MMXIV AMJ Productions, LLC All Rights Reserved.
-
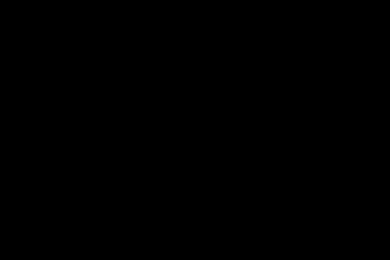
PROGRAM/放送作品
栄光のアカデミー賞(1976)
世界中が注目する映画の祭典、アカデミー賞。その輝かしい歴史と魅力に迫る!
2月15日から放送の【アカデミー賞大特集】にあわせて、過去30年にわたる受賞作品紹介からインタビュー、賞レースの裏側まで、アカデミー賞の魅力を余すことなくお伝えする、映画ファン必見の特別ミニ番組。
-

COLUMN/コラム2017.08.29
個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年9月】お殿
建設中の博物館で足を滑らせた失業中の広告マンのロベルトが、足組のようなものに落下し剥き出しの鉄の棒に頭が刺さってしまいます。棒を抜いたら出血多量で死にかねず、救助を呼んだものの動けません。まさに「ピンで刺された虫のよう」な男の姿に、マスコミは大騒ぎ、報道合戦が白熱します。就職活動では無視されまくったのに今は国中に注目されている!ロベルトはこのオイシイ状況を利用し金儲けをしようと考えます。家族のため、広告マンとしてのプライドのため、痛みに耐え脂汗流しながら交渉するロベルト。この作品、スペインのブラックコメディなのですが、中々シニカルなものになってます。ロベルトが失業を苦に自殺未遂したと勘違いし同情した多くの若者が、キリストよろしく磔にされたロベルトを聖者のように扱ったり、広告業界の面々がえげつない便乗商法を繰り広げたり。異常な事態に発展していく様は、ある意味見ていて笑えます。ロベルトは無事に助かるのか、そして大金を手に入れることができるのかというところですが…オチまでシニカル。監督は、『どつかれてアンダルシア(仮)』や『気狂いピエロの決闘』で知られる、スペイン、バスク地方出身のアレックス・デ・ラ・イグレシア。本作を彼は「自らの魂をお金にしなければいけない時、人はどのように尊厳を保つか」についての映画だと語っています。若者の失業率が50パーセントを超えると言われるまでの経済危機に陥っているスペインで、「お金」と「尊厳」というテーマが彼独自のスタイル:コメディとして描かれています。ブラックな笑いも存分に味わうことのできる本作ですが、ロベルトを思う家族の姿には思いがけず心がギュッーと締め付けられます。特に印象的なのは奥さんルイサの聖女っぷり。40後半でもスタイル抜群で美しさ健在のサルマ・ハエックが、夫に寄り添う献身的なルイサを好演しています。また、エスパーニャ・ディレクトのリポーター役のイグレシア作品常連女優カロリーナ・バングは2014年に監督と結婚。ザ・シネマで放送中の、ゴヤ賞8部門を受賞した『スガラムルディの魔女』にも出演しています。映画の原題は人生のきらめき、という意味の「La chispa de la vida」。実際にスペインのコカコーラのスローガンとして使用されました。ブラックな笑いの中に、人生で大切なものは何かを考えさせてくれるこの作品、ぜひご覧ください。■ ©Alfresco Enterprises y Trivision
-
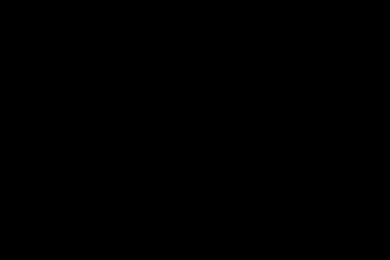
PROGRAM/放送作品
栄光のアカデミー賞(1977)
世界中が注目する映画の祭典、アカデミー賞。その輝かしい歴史と魅力に迫る!
2月15日から放送の【アカデミー賞大特集】にあわせて、過去30年にわたる受賞作品紹介からインタビュー、賞レースの裏側まで、アカデミー賞の魅力を余すことなくお伝えする、映画ファン必見の特別ミニ番組。
-

COLUMN/コラム2017.08.29
個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年9月】飯森盛良
『エイリアン:コヴェナント』一足お先に見たが、「人間はどこから来たのか?人は何のため生まれてくるのか?」について語りたいシリーズであることがますます鮮明に。またリドスコ映画の同窓会の趣も。タイレル社長とロイバッティの関係、人体の腑分けに熱中するレクター博士の貴族趣味などが映画中に散りばめられ、さらに文学や音楽からの引用といい、「どんだけ深えんだ!」という豊潤な作品になった。しかーし!完全に『プロメテウス』の続編。『エイリアン』シリーズは見てなくても『プロメテウス』だけは見ておかないと話についていけない。ま、公開前にウチでは『エイリアン』シリーズも『プロメテウス』も全部やるんだけどな!■ © 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
-

PROGRAM/放送作品
フェリーニ 大いなる嘘つき
インタビュー、メイキング映像、スタッフの証言…偉大なる創造者フェリーニの実像が明らかに!
F・フェリーニが亡くなる直前にD・ペティグリュー自ら行ったインタビューをベースに、巨匠の人となりや創作の秘密の一端を明かしていくドキュメンタリー。フェリーニ作品の未公開映像やスタッフの証言も満載。
-

COLUMN/コラム2017.07.29
『ブレンダンとケルズの秘密』7/29公開。まあこれはアカデミー賞ノミネートされるわな!なワケとは!?
本日、アニメ映画『ブレンダンとケルズの秘密』が公開されました。いゃ〜待望でしたねえ!昨夏は『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』が単館系として全国順次公開され、公開規模に比して多くの日本人が魅了されて話題になりました。その監督のデビュー作が今作です。公開順が日本では逆転してしまいましたが。 『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』は“ポスト・ジブリ”との呼び声高いアイルランドのアニメーション・スタジオ「カートゥーン・サルーン」の第2作で、2014年度アカデミー長編アニメ映画賞にノミネートされたほど評価が高った。結局その年は『ベイマックス』が獲りましたけど、ジブリの『かぐや姫の物語』とも競ったのでした。その戦績からクオリティは推して知るべしということで。 監督はアイルランド人のトム・ムーア。これが監督2作目で、デビュー作である『ブレンダンとケルズの秘密』という作品も存在するらしい。しかもそっちもアカデミー長編アニメ映画賞にノミネートされている(2009年度)。獲ったのは『カールじいさん』でしたが、他に『コラライン』とか『ファンタスティック Mr.FOX』と競ったというのだから、デビュー戦からして華々しい。 ちなみに昨夏、ワタクシは監督にインタビューさせてもらいましたが、その模様と『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』についてはコチラの過去記事から。今回のこの投稿とも超リンクしてくる内容です。あわせてお読みいただけたら大変うれしい。 昨夏、この『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』に魅了され、デビュー作『ブレンダンとケルズの秘密』というのも見てみたい!と思った日本人は、少なからずいたでしょう。今夏、その願いが叶います!関西の映画祭で上映されたことはありましたが、ついに、商業上映で全国順次ロードショーが実現しました。 昨夏の『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』と同じくアイルランド感満点の映画となっております。映画を通じて遥かなる異国の文化や歴史に親しみを持てるってのは、実に素晴らしいことですなあ!映画を見る理由の一つです。きっと外国人も、ジブリの『もののけ姫』や『千と千尋』を通じて、我が国に興味と親近感を持ってくれたのでしょう。だから“ポスト・ジブリ”なのです。 ■ ■ ■ 今作『ブレンダンとケルズの秘密』のあらすじを、解説もちょいちょい差し挟みながら以下ご紹介していきましょう。時は9世紀。ケルト民族の島アイルランドはすでにキリスト教化されており修道院が各所に建っている。そこをヴァイキングが襲う。黄金製で絢爛豪華な教会の聖具を狙って。ヴァイキングはこの映画では顔も人格もない宇宙からのインベーダー的な扱いになっていますが、でもケルト人だってアイルランドの先住民族という訳ではなくて、この1000年くらい昔にヨーロッパ本土からやってきた移民・難民もしくは侵略者だったんですけどね。 今ではアイルランドといえば様々な映画で描かれている通り“カトリックの国”という印象ですが、9世紀のこの時代はローマ・カトリックとは一線を画する独自キリスト教派「ケルト系キリスト教」が盛んな島でした。4〜5世紀、ヨーロッパ本土は民族大移動(皆ご覧375ゲルマン人の移動だよ、375年)と西ローマ帝国崩壊(ローマは死なむ476と言いつつ死んじゃった、476年)の影響で大混乱におちいっていたのですが、最果ての島アイルランドはその混乱とは無縁だったため、キリスト教が無傷で温存された上に独自の発達を遂げたのです。 「学者と聖者の島」と尊称され、各国から留学僧を多く受け入れ、逆に各国に宣教師を派遣もしていた、西ヨーロッパ随一の文教センター。それがこの時代のアイルランドでした。遣隋使・遣唐使時代の都・長安みたいなものでしょうか。だからこの映画の中では、黒人まで含む、様々な人種・民族の留学僧がアイルランドの修道院に集っているのです。アイルランド史ではこの時代を「聖者の時代」と呼んでいます。ケルト民族の文化と融合した美しいキリスト教の文物が数多く作られ、それらは今ではアイルランドを象徴する文化財となっていますが、それをヴァイキングが狙ってきて、この映画のキーアイテム「ケルズの書」もそのうちの一つ(しかも現国宝)なのです。 「ケルズの書」とは、極彩色の緻密細密な渦巻き模様や唐草文様に彩られた福音書。渦巻き模様や唐草文様はケルト民族の伝統文様です。ケルト民族の故地・ヨーロッパ本土スイスあたりにあった紀元前のラ・テーヌ文化にまでさかのぼります。千数百年前にスイスにいたご先祖様と同じ模様を使って、その子孫たちが、アイルランドで独自に発展させ世界が絶賛した「ケルト系キリスト教」の聖典を彩った。それが「ケルズの書」なのです。それからさらに1000年後、ケルト民族の数十世代後の子孫たる現代アイルランド人が今も国宝として大切にしているのも納得です。 さて、ウンチクはやめてそろそろあらすじを始めねば。その頃ケルズ修道院というところにブレンダンというわんぱく少年修道士がおりました。この修道院では、「芸術を生み出すこと(特に写本作り)、文化を後世に伝え残すことが重要」という考えと「安全保障が最重要。壁を建設して異民族・外敵(ヴァイキング)の侵入を防ぐことが喫緊の課題」という考えが対立しています。大昔から「我が国をとりまく安全保障環境がヤバいことになってる」と騒いではやたらと壁を建設したがる輩ってのはいるものです。そのタイプが修道院長。ブレンダン君の叔父さんです。 ブレンダン君はアイルランドのケルト系キリスト教を慕って渡来してきた外国人留学僧たちに囲まれ、装飾写本作りに興味を持つのですが、叔父さんの安保院長からスゲ無く「そんな下らんことにかまけていられるご時世か!」的なリアクションを返される毎日。そんなある時、当代最高の写本絵師ブラザー・エイダン(実在の歴史上の人物)がヴァイキングから逃れここケルズ修道院まではるばるやって来る。このエイダン師に感化され、ますます写本熱が高まるブレンダン君。叔父さんの院長は苦々しく思う。 エイダン師は美しいイラストで埋め尽くされた描きかけの書を携えてきており、興味津々のブレンダン君に絵本作りを手伝ってくれと頼みます。まず森に入ってインクの材料となる木の実を拾ってきてくれと言い、その言いつけに従って、鉄壁の要塞と化しつつある修道院を抜け出し森にはじめて分け入ったブレンダン君は、その森の奥で道に迷ってしまいます。 そこで、不思議な自然児、森に精通していて「ここは私の森」と豪語する白髪の少女アシュリンと遭遇するのです。 アシュリンちゃんとは何者なのか?ケルト民族は妖精を信じていますので、妖精か妖怪変化のたぐいでしょうか?森はキリスト教ではなく妖精や異教の領域。そこでキリスト教の修道士ブレンダン君とケルトの妖精アシュリンちゃんが仲良しになるというところが、とてもアイルランド的なのです。ケルト+キリスト教=アイルランドなのです。「ケルト系キリスト教」も当然そういうことですし、今作劇中のキーアイテム「ケルズの書」も、ケルト伝統装飾で彩られたキリスト教福音書ですから。 このアシュリンちゃんも畏れる、忌むべき存在が森の奥底深くには潜んでいる。それがクロム・クルアッハ神。いにしえのケルト神話の神で、キリスト教以前のアイルランドには金銀製の巨像が祀られていたといいます。12柱の青銅製の従属神像を従えていたともいう。生贄を求め、初子かその家の子供たちの1/3を犠牲に捧げれば、戦いにも勝てるし大豊作も叶えてくれる、と信じられていました。まあ、はっきり言って邪神ですな。この邪神像を引きずり倒した漢が、アイルランドを象徴する聖人、三つ葉のクローバーでおなじみセント・パトリックなのですが、閑話休題。こういう、古代ケルトのまがまがしい存在も、妖精も、アイルランドの森には潜んでいる、という、まさにジブリ的な、『もののけ姫』的なアニメなのであります。 さて、とあるクエスト達成のため、この邪神クロム・クルアッハと対峙せねばならなくなるブレンダン君×アシュリンちゃんコンビ。さらに、ヴァイキングの来寇が目前に迫っていた…高い壁をはりめぐらせたケルズ修道院の命運は?そして、現代にまで伝わりアイルランドの国宝とされるに至る「ケルズの書」はいかにして誕生するのか? この続きは、映画本編でお確かめください。 ■ ■ ■ 最後に。一時期はキリスト教世界の中心地でさえあったアイルランド。その国際的地位が、実際にヴァイキングの襲来と破壊によって大きく衰退したことは歴史的な事実です。ヴァイキングは8世紀末からヨーロッパ中の沿岸部を荒らし回りました。しかし実はその前に「ケルト系キリスト教」の影響力も、民族大移動と西ローマ滅亡の大混乱から200年を経て立ち直りつつあったヨーロッパ本土のローマ・カトリックとの教義論争に敗れて(664年ホイットビー宗教会議)地位が弱まっていたのです。そのためアイルランドもまた、普通のカトリックの一角となってしまい(それでもだいぶユニークですが)、そしてさらにその後、キリスト教化したイギリス、しかもさらに後にはプロテスタント国となったイギリスの強い影響にさらされながら、こんにちに至るのです。 壁を築くというのは、侵略の恐怖にさらされた当時の人々にとっては切実な願いだったでしょうし、当然の行動でしょう。でも、無駄だった。ヴァイキングの侵寇も大英帝国の専横も、結局、防ぐことはできませんでした。だから無駄だ、とは思いません。国防が無駄である訳がない。やるだけやる意味はある。それで救われた命も幾つかはあったかもしれない。でも逆に、文化・芸術だって決して無駄ではない。結局、文化だけが残りました。ケルト芸術と「ケルト系キリスト教」の精華たる「ケルズの書」は、こんにちにまで伝わって、民族の誇り、アイデンティティの核として、国宝となったのです。 このアニメ映画、ケルトの伝統模様、渦巻き模様や唐草文様が画面中に散りばめられています。紀元前のラ・テーヌ文化から伝わる模様を使って9世紀に描かれた「ケルズの書」をめぐるファンタジー冒険アニメを、現代アイルランドのアニメ作家・スタジオが、やはり同じ文様を使って描く。文化と芸術が、二千数百年の時を経て、民族のあいだで連綿と伝えられてきたという確たる証拠。それがこの『ブレンダンとケルズの秘密』なのです。 まあ、これはアカデミー賞ノミネートされるよね!(蛇足:アシュリンちゃん、『ソング・オブ・ザ・シー 海のうた』にも隠れキャラとして出ています。見れる人は探してみよう) 7月29日(土)にYEBISU GARDEN CINEMAほか全国順次ロードショー2009年/75分/カラー/ドルビー・デジタル/ヴィスタサイズ/フランス・ベルギー・アイルランド合作 ©Les Amateurs, Vivi Film, Cartoon Saloon