SF小説の古典として名高い、ジャック・フィニィ(1911~95)の「盗まれた街」。1955年に発表されて以来、洋の東西を問わず、多方面にインパクトを及ぼした。日本でも、手塚治虫の「ブラックジャック」にインスパイアされた一編があるなど、影響を受けたクリエイターは少なくない。
ハリウッドでの映画化は、4回に及ぶ。本作『SF/ボディ・スナッチャー』(1978)は、その2回目の作品である。
まずは原作小説のストーリーを、紹介しよう。主人公は、アメリカ西海岸沿いの田舎町サンタ・マイラで開業する、医師のマイルズ。ある時彼の診察室に、ハイスクール時代に何度かデートした美しい女性ベッキーが訪れる。
彼女の用件は、いとこのウィルマを診て欲しいということだった。ウィルマは、自分の育ての親である伯父が、偽者だと思い込んでいるという。
マイルズはベッキーの依頼に応え、ウィルマの元を訪れる。その際に彼女の伯父にも会ったが、何ら変わった様子は感じられない。しかしウィルマに言わせると、小さなしぐさや癖、身体の傷までそのままで、思い出話をしても、ちゃんと答えてくれるのだが、「何かが決定的に違う」というのである。ウィルマには伯父が、感情らしい感情を、失ってしまっているように思えるらしい。
そしてその時以降、マイルズの診察室には、ウィルマと同じようなことを訴える患者が次々と訪れる。夫が自分の妻を、「妻でない」と言い張る。子が親を、或いは友人が友人を、偽者だと主張するのである。
マイルズは精神科医のマニーの力を借りるのだが、一向に埒が明かない。その一方で、お互いバツイチになってからの再会だった、ベッキーとの距離が縮まっていく。
ベッキーとのデートを楽しんでいる最中、マイルズは友人の小説家ジャックから、至急家に来て欲しいという連絡を受ける。2人でジャック邸を訪れると、彼の家のガレージへと案内される。
そこにあるビリヤード台の上には、シートにくるまれた人間の死体が置いてあった。ジャックはマイルズに、その死体をよく観察してくれと頼む。
その死体は、成人の顔にしては未熟な印象であり、その肉体は傷一つなく、未使用と言える状態だった。死体らしい冷たさもなく、その指先には、指紋がなかった。まるで、一度も生きたことがないかのように。
マイルズとベッキー、ジャックとその妻シオドラは、この物体と、最近この街に住む人々の身に次々と起こっている、身近な人々を別人と感じる症状に、何らかの関わりがあると思い至る。そしてマイルズは、ベッキーの自宅の地下室にも、同じものを発見する。
街の人々は、この不思議な物体に次々と乗っ取られている!
しかし相談していた精神科医のマニーを呼ぶと、物体はいつの間にか姿を消していた。マニーはマイルズたちが、幻覚を見たに過ぎないと指摘。マイルズたちも、一旦は納得せざるを得なかった。
しかし、奴らの“侵略”は確実に進んでいた。マイルズたちは次第に追い詰められ、街からの脱出を、決意するのだったが…。
「盗まれた街」で、サンタ・マイラの人々の身体を乗っ取っていくのは、死滅の危機に直面した惑星から、宇宙間の莫大な距離を、数千年の歳月を費やして漂流してきた宇宙種子である。巨大なサヤのようなその種子は、ターゲットとなる人間の近くに置かれると、その者が眠っている間に、個々人が持つ正確な原子構造の図式を読み取って複製し、完全なる同一人物が生まれる仕組みとなっている。それと同時に、複製された側の人間は、灰色の塵となって消えてしまう。
“睡眠”は、人間が生きていく上で避けられないもの。ところが眠ってしまうと、一巻の終わりというわけだ。このメカニズムが、実に恐ろしい。
原作では、主人公たちの抵抗によって、宇宙種子による地球侵略は、頓挫する。いわばハッピーエンドを迎えるのだが…。
原作が発表された翌年に公開されたのが、『ボディ・スナッチャー/恐怖の街』(56/日本未公開)。アクション映画の名手ドン・シーゲル監督による、「盗まれた街」の映画化第1作の登場人物や筋立ては、ほぼ原作に忠実である。物語の終幕も、希望が残る。
大きく改変されたのは、主要登場人物の一部に待ち受ける運命。クライマックスには、過酷としか言いようがない展開が訪れる。
それを考えると、原作に準拠したような終幕は、正直違和感が残る。実はシーゲルは、ケヴィン・マッカシーが演じる主人公のマイルズ医師が、ハイウェイに立って1台の車を止めて、サヤに対する警告を発するところで、エンドマークを出したかったという。彼は観客に向かって指を差し、叫ぶ。「次は、あなたの番だ!」
こうしたアンチ・ハッピーエンドが避けられたのは、製作側の意向だった。シーゲルはもしそれに従わなければ、脚本家のダニエル・メインウォーリングと共に、「交替させられてしまっただろう」と、後に述懐している。
この映画化第1作は、“赤狩り”の時代を背景にした寓話であると、後世まで語られる作品となった。米ソ冷戦が激化し、“共産主義”の脅威が広く語られる中で、アメリカ国民の中には、「同僚や隣人が、スパイでもおかしくない」という疑心暗鬼が広がっていた。身近な者が共産主義者であっても、見た目は普通の人間と変わらない。どうやって見分ければ良いのか?誰を信用すれば良いのか?…というわけだ。
こうした映画化作品の評価と共に、原作小説に対しても、その“意味”を巡る解釈は、様々に為されてきた。しかし原作者フィニィは、それを一笑に付す。
「…これは楽しんでもらうためのただのお話。それ以上の意味はない…」
「…映画にかかわった人々がなんらかのメッセージを持っているという議論は、いつもくすぐったい思いで拝聴していました。そうだとすれば、それは私が意図した以上のものだし、映画は原作に忠実なのだから、そもそもメッセージとやらがどうやって入り込んだのか想像もつきません…」
フィニィはこう語るが、しかしながら、長く読み継がれるような優れた物語は、現実の変化に応じて、意味付けや解釈が変わってしまうのが、至極当たり前である。「盗まれた街」に関しては、発表から65年の間の、4度の映画化作品を見ると、各時代が抱える問題や病弊が、明確に浮かび上がる。
ドン・シーゲル版から23年後の、2度目の映画化作品、『SF/ボディ・スナッチャー』は、『スター・ウォーズ』(77)『未知との遭遇』(77)『エイリアン』(79)などで、世界的なSF映画ブームが沸き立っている最中に、製作・公開された。監督を務めたのは、後に『ライトスタッフ』(83)や『存在の耐えられない軽さ』(88)を撮る、フィリップ・カウフマン。
本作には、ドン・シーゲルやケヴィン・マッカーシーがカメオ出演。前作へのリスペクトぶりを、至るところに溢れさせながらも、70年代後半という、時代の装飾を纏わせている。
宇宙の彼方で絶滅する惑星、そしてそこから逃れて、地球に向けて侵略を開始する微生物が描かれるオープニングで、この作品が何を描くかを、高らかに宣言した後に登場する舞台は、田舎町のサンタ・マイラではなく、大都市のサンフランシスコ。そしてドナルド・サザーランドが演じる主人公ベネルは、医師ではなく、州の公衆衛生官となっている。
ベネルはある時、職場の同僚であるエリザベス(演;ブルック・アダムス)から、夫の様子がおかしくなり、「彼が彼でなくなった気がする」と奇妙な相談を持ち掛けられる。これをきっかけに、ベネルは周囲の異変に気付いていく…。
サヤが人体を乗っ取る原理は、前作と変わらない。しかし、特殊メイクなどSFX技術の著しい進歩と、しかもCG登場以前というタイミングがあって、サヤが人体を複製していく描写が、何ともグロテスク。実にリアルで、グチャドロに表現される。
舞台を大都市に変えた狙いも、明白だ。本作のプロデューサーであるロバート・H・ソロ曰く、ここに暮らす人々は「お互いに無関心であり、回りの人の小さな変化などに、誰もが気がつかない」。それ故に、“複製”になり代われる怖さは、倍増するというわけだ。
主人公の職業変更も、その流れの中で行われた。レストランなどの店舗や施設の衛生状況をチェックするのが仕事の公衆衛生官ならば、無関心な大都市の中でも、いち早く異常事態に気付くことが、不自然ではない。
映画史的に鑑みればこの頃は、SF映画ブームであると同時に、60年代後半から70年代中盤に掛けて、アメリカ映画を席捲した“ニューシネマ”が終焉を迎えた時期である。『SF/ボディ・スナッチャー』は、“ニューシネマ”が肯定的に捉え続けた、反体制文化や個人主義に対して、疑念を提示しているとも言える。そうした方向性が行き過ぎると、社会やコミュニティが崩壊に向かうという考え方である。
それにしてもメインキャストに、ドナルド・サザーランド、『ザ・フライ』(86)のジェフ・ゴールドブラム、そしてMr.スポックことレナード・ニモイと、よくもまあ個性的な“顔”ばかり揃えたものである。宇宙種子に乗っ取られて、当然とも思えてしまう。
それは冗談として、そんな面相のサザーランドだからこそ、ブルック・アダムス演じる美しきヒロインとのロマンスが、より切なさを帯びる。職場の気の置けない友人同士だった筈が、侵略者からの逃避行の中で、お互いを愛していることに気付いてしまう。
それだけに主人公が、前作同様に、何よりも大切なものを失ってしまうクライマックスに、私は涙を禁じ得なかった。先にも挙げた通り、SFXの発達によって、よりグロテスク、且つ、より痛ましく、そして、よりもの悲しいシーンになっているのである。
『SF/ボディ・スナッチャー』に続く、「盗まれた街」3回目の映画化は、15年後のアベル・フェラーラ監督作品、『ボディ・スナッチャーズ』(93/日本未公開)。前作と同じく、ロバート・H・ソロが製作を手掛けている。
主演は、ガブリエル・アンウォー。当時20代前半の彼女が、ティーンエージャーを演じた。
この作品の舞台は、アメリカ国内の米軍基地。主人公は、土地の汚染を調べる仕事をする父親の異動で、継母や幼い弟と基地内に移り住むことになるが…。
田舎町でも大都市でもなく、軍の基地が宇宙種子に乗っ取られていくというのが、新たな設定。栽培されて増殖したサヤが、トラックなどで他の町や都市に運び出されていく描写は、前2作でもあったが、こちらは軍用トラックで、大々的に展開されるわけである。
文民統制が取れなくなって、集団ヒステリーに陥った軍部が暴走する恐ろしさが描かれている…と解釈することも出来るだろう。しかしそんなことよりも、ティーンの少女を主人公にしたことによって、「思春期の不安定な心理が生んだ妄想劇といえばそう見えなくもない」(後記の「映画秘宝」より井口昇氏の文を引用)のが、ポイントとも言える。
いずれにせよ、「盗まれた街」という原作の、汎用性が窺える改変である。
そして4回目にして、今のところ最新の映画化作品は、『ヒトラー〜最期の12日間〜』(2004)などの成功により、ハリウッドに招かれたドイツ人監督オリヴァー・ヒルシュビーゲルがメガフォンを取った、『インベージョン』(07)である。
スペースシャトルの墜落によって、未知の宇宙ウィルスが地球上に降下し、やがて蔓延していく。その脅威に戦いを挑んでいくヒロインは、ニコール・キッドマンが演じる、バツイチで一人息子と暮らす、シングルマザーの精神科医。
今回は、ウィルスに感染した者が眠りに就くと、起きた時には、“別人”になっているという仕組み。お馴染みのサヤが出てこないのには、些か拍子抜けするが、2001年にアメリカを襲った“同時多発テロ”や、HIVやレジオネラ、SARS、鳥インフルエンザ等々、未知のウィルスが次々と現れては、人類の脅威と喧伝されるようになった時代を受けての、改変であった。
そしてその改変が、実は『インベージョン』製作から13年経った、2020年のまさに今こそ、ピタリとハマってしまう。ここまで記せば、ピンと来た人が多いだろう。
現在、全世界に蔓延し、人類の脅威となっている“新型コロナ禍”である。
『インベージョン』に於いて未知の宇宙ウィルスは、文字通りの“飛沫感染”によって、拡がっていく。また物語の中で、登場人物たちの都市間の移動も多く、それがウィルスが蔓延していく情勢と合致する。
感染しても、すぐに発症するわけではない。また中には抗体を持つ者が居て、発症しないが故に、侵略者たちには脅威となり、逆に人類にとっては、ワクチンをもたらす福音となる。
『インベージョン』はそうした意味で、13年早かった作品とも言える。そして改めて、原作者ジャック・フィニィのオリジナルの発想の素晴らしさにも、思い至るのである。■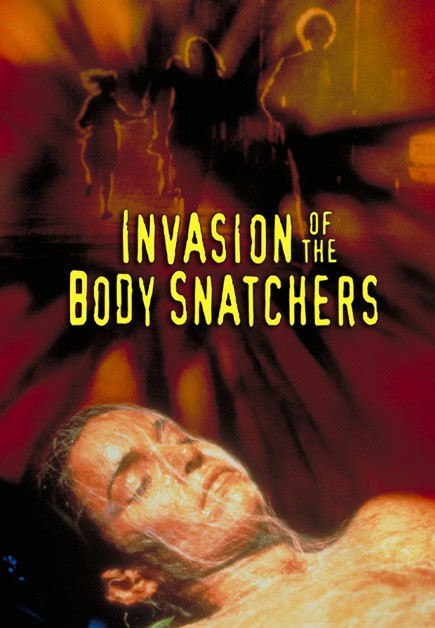
「SF/ボディ・スナッチャー」INVASION OF THE BODY SNATCHERS © 1978 METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC.. All Rights Reserved


