本作『ローズマリーの赤ちゃん』(1968)の原作小説は、アイラ・レヴィン(1929~2007)が、67年に発表。ベストセラーになった。
レヴィンは、物語に時事的な社会問題を織り込んでサスペンスを醸し出す、巧みなストーリーテラーとして評価が高かった作家である。72年に出版された「ステップフォードの妻たち」は、“ウーマン・リブ”の時代への男性の恐怖心をベースにしたもの。76年の「ブラジルから来た少年」では、ナチス・ドイツ残党の実在の医師メンゲレが、当時最新の“クローン”技術で、ヒトラーの復活を企てる。
そしてそれらに先立つ「ローズマリーの赤ちゃん」は、50年代末から60年代初めに起こった世界的な大事件から、着想を得ている。
ニューヨークに住む、ローズマリーとガイの若夫婦。ガイは俳優で、舞台やテレビCMなどに出演するも、今イチぱっとしない。
夫婦は歴史のあるアパート、ブラムフォードへと引っ越す。2人の中高年の友人ハッチは、過去に数々の事件が起こった場所だと懸念するが、夫婦は耳を貸さなかった。
入居して間もなくローズマリーは、隣室のカスタベット夫妻宅の居候だという、若い娘テリーと親しくなる。しかしその数日後、テリーは窓から身を投げ、自殺を遂げる。
その件がきっかけで、ローズマリーとガイは、テリーの面倒を見ていた隣室の老夫婦、ローマンとミニーと顔見知りになる。夕食に招かれるなどする内に、ガイは演劇に詳しいローマンと親しくなり、カスタベット家を頻繁に訪ねるようになる。
そして間もなく、ガイのライバルの俳優が突如失明。ガイに役が回るという、思いがけないチャンスが巡ってきた。
時を同じくしてガイは、子作りにも積極的になる。ローズマリーの排卵日、彼女はミニーから差し入れられたデザートを食べた後、目まいに襲われ、ベッドに臥せってしまう。
その夜ローズマリーは、夢を見る。ガイやカスタベットらが見守る中で、人間離れした者に犯されるという内容の悪夢であった。
翌朝起きると、彼女の身体のあちこちに、引っかき傷が出来ていた。ガイは、子作りのチャンスを逃したくなかったので、意識のないローズマリーを抱いたと説明をする。
そんな不快な経緯がありながらも、待望の妊娠をしたローズマリーは、幸せに包まれた。まるで家族のように喜ぶカスタベット夫妻は、高名な産科医を紹介。その上で、自家栽培で作った薬草を使ったドリンクを、毎日届けてくれるようになる。
ローズマリーは酷い痛みに襲われて、痩せ細っていく。心配したハッチが、彼女の身の回りのことを調べて行き当たった、大切なことを伝えようとする。しかしその直前に彼は倒れ、意識不明となってしまう。
周囲に対して、疑心暗鬼になっていくローズマリー。やがて彼女は、カスタベット夫妻とガイが、サタニズム=悪魔を信仰する者で、生まれてくる我が子をその生贄にしようとしているのではないかと、恐れ慄くようになる。
ローズマリーが抱いた恐怖は、果して現実のものなのか?それとも彼女の妄想なのか?
女性が妊娠した際に、普通に抱く不安がある。無事に我が子は、生まれてくるのか?そして、健やかに育ってくれるのか?
1950年代末から60年代初めに、鎮静・催眠薬として発売されていたサリドマイドが、その不安を増大させた。この薬を妊娠初期に服用すると、胎児の手や足、耳や内臓などに、深刻な奇形をもたらしたのである。世界で1万人近く、日本だけでも、千人の胎児が被害にあったと推定される。
レヴィンは、このサリドマイド禍が引き起こしたパニックに、カルト宗教としてのサタニズムを絡めて、「ローズマリーの赤ちゃん」の作品世界を構築したのである。
その映画化権を取得したのは、ギミックの帝王と謳われた、ウィリアム・キャッスル。キャッスルは、映画にショック死保険を掛けたり、上映中に本物の骸骨を出現させたり、客席に微電流を流したりと、様々な仕掛けを行ったことで知られる。
いわばB級ホラーの職人監督であったキャッスルは、「ローズマリー…」も自ら監督するつもりであったが、製作元のパラマウントのプロデューサー、ロバート・エヴァンスから、ストップが掛かる。エヴァンスが白羽の矢を立てたのは、ヨーロッパ駐在時代に観て、非常に感心したイギリス映画『反撥』(65)の監督、ロマン・ポランスキーだった。
ユダヤ系ポーランド人のポランスキーは、1933年パリ生まれ。3歳の時に家族でポーランドへ移住すると、ナチス・ドイツのワルシャワ侵攻に遭い、ユダヤ人ゲットーでの生活を、余儀なくされる。
やがて家族は皆、強制収容所へと送られる。ポランスキーだけは父の手で逃がされ、そこから終戦までは、幾つかの預け先を転々とすることになった。
戦後に父親は、命拾いして戻って来た。しかし母親は、アウシュビッツで虐殺されていた。
ポランスキーはその後、ポーランドの映画学校で、監督を志すようになり、処女長編『水の中のナイフ』(62)を撮る。この作品は本国では酷評されたものの、ヴェネチアをはじめとする海外の映画祭で高く評価された。
母国を出て、外国で英語での映画製作に取り組むようになったポランスキーは、イギリスで、『反撥』『袋小路』(66)『吸血鬼』(67)の3本を立て続けに撮り、それぞれに成功を収めた。
ポーランド映画界での先輩アンジェイ・ワイダは、次のように語っている。
―ポランスキーは、いわゆるコスモポリタンであって、どこの国でも映画をつくることができさえすればいい、と考えている人ですー
そんなポランスキーに、ハリウッドからオファーが届いた。「ローズマリーの赤ちゃん」映画化の話である。
ポランスキーがハリウッドに着くとすぐ、原作の校正刷りが届けられた。しかし彼は、旅の疲れがあって、読むのは翌日にしようと、ベッドに潜り込んだ。ところが、ついページをめくってしまったところ、惹き込まれて、明け方までかけて、一気に読んでしまったという。
ポランスキーは、翌朝撮影所に出掛けると、「OKだ。大変に面白い。だが条件がひとつある。それは物語をこのままにして、全く改訂しないということだ…」と、伝える。製作側もその方針に異存はなく、ポランスキーのハリウッド進出が、正式に決まった。
エヴァンスが『反撥』に感心して、ポランスキーに監督をオファーしたことは、先に記した通りだ。『反撥』は、セックスへの恐怖心が昂じて、閉鎖空間で現実と妄想の区別がつかなくなって狂っていく、若い女性が主人公の作品である。
そんな作品を撮ったポランスキーこそ、「ローズマリー…」の映画化に正に打ってつけの人材と、エヴァンスは見込んだ。そしてポランスキーもまた、この題材に強く惹かれたというわけである。
ポランスキーは自分で注文をつけた通り、ほぼ「原作に忠実」な映画化を行った。そんな中ローズマリーが犯されるシーンで、LSDを服用したかのような、サイケな映像を用いて、現実とも妄想ともつかないように演出している辺り、当時の彼の才気が爆発している。
原作からの改変として、ポランスキーが挙げるのは、次の一点のみ。
「…私はラストを少し改変した。というのは、本の結末は少しばかり失望させるものだったからだ。あそこはちょっと長引きすぎると思う」。
これに関しては機会があったら、是非原作と映画版の違いを、自らの目で確かめて欲しい。
何はともかく、レヴィンの原作とポランスキー監督のマッチングは、大成功! ローズマリー役のミア・ファローのニューロティックな感じもピタリとハマった。映画は大ヒットを記録し、ポランスキーはアカデミー賞の脚色賞にもノミネートされる。
通常ならばこうした経緯を、「幸運な出会い」と表現するべきなのであろう。しかしこの作品に関しては、それ以上に他の形容をされる場合が多い。「呪われた映画」であると…。
後に原作者のレヴィンは、自分は“サタン”を信じないと発言。またポランスキーは、無神論者であることを明言している。それなのにこの作品とその成功は、作り手がつゆとも思わなかった、“悪魔”を呼び込んでしまったのである。
『ローズマリー…』の大成功により、ハリウッドの住人として認められたポランスキーは、映画公開の翌年=69年2月、ロサンゼルスに居を構える。それから半年経った8月9日朝、ポランスキー家のメイドが、5人の遺体を発見する。
殺害されていたのは、ポランスキーが『吸血鬼』で出会って結婚し、当時妊娠8カ月だった女優のシャロン・テートと、ポランスキー夫妻の関係者ら。ポランスキー本人は、次回作のシナリオ執筆のためロンドンに滞在しており、留守にしていた。
数か月後、凶行に及んだのは、チャールズ・マンソンが率いるカルト集団であることが判明。この犯行は無差別殺人の一環であり、ポランスキーの邸宅が狙われたのは、単なる偶然であった。
いずれにせよ、『ローズマリー…』が成功せず、ポランスキーがロスに居を移すことがなかったら…。若妻がカルト集団に惨殺されることも、なかったわけである。
因みに映画でローズマリーらが住むアパート、ブラムフォードの外観に使われたのは、ニューヨークのセントラルパーク前に在る、ダコタハウス。1980年12月8日、ここに住むジョン・レノンが、玄関前で撃たれて落命した、あのダコタハウスである。
これは、映画とは何ら関係のない事件である。しかしミア・ファローが、ビートルズのメンバーと共に、インドで瞑想の修行に臨んだ過去の印象などもあってか、『ローズマリー…』を「呪われた」と語る場合、不謹慎な言い方になるが、レノンの殺害が、その彩りになってしまっているのは、紛れもない事実と言える。
さてシャロンを失って、憔悴しきったポランスキーであったが、やがてその悪夢を振り払うかのように、次々と新作に取り掛かるようになる。しかしワイダが言うところの、“コスモポリタン”ぶりに拍車が掛かったようで、その舞台はイギリス、イタリア、フランスなどに渡る。
結局ポランスキーが、『ローズマリー…』の他にハリウッドで手掛けた作品は、『チャイナタウン』(74)のみ。そしてその主演だったジャック・ニコルソンの邸宅で、ポランスキーは、13歳の少女モデルの強姦という、“事件”を起こしてしまう。
ポランスキーは、己の原体験を、スクリーンに映し出すことを、特徴とする映画作家である。例えばイギリスで撮った『袋小路』に登場する主人公夫婦は、ポランスキーがシャロンの前に結婚していた、バルバラ・ラスとの関係をモデルにしたとされる。またアカデミー賞監督賞に輝いた『戦場のピアニスト』(02)は、実在のユダヤ系ポーランド人ピアニストの体験記を原作としながら、主人公のナチス・ドイツからの逃亡劇には、ポランスキー自らの体験を、多々盛り込んでいる。
しかしながら、ポランスキーが77年に起こした、少女の強姦事件は、まるでその真逆である。シャンパンと麻薬的な効果のある鎮静剤を飲ませて、性交に及んだと言われているが、これはその9年前に撮った『ローズマリー…』に於ける、悪魔主義者たちの手口をトレースしているかのようだ。
ポランスキーは拘留後、一旦釈放された際に、再びの収監から逃れて、アメリカ国外へと脱出した。以降アメリカへの入国は不可能となり、アカデミー賞が贈られた際も、セレモニーへの出席は、叶わなかった。
アメリカ脱出後、ポランスキーはパリを拠点とし、そこで新たなる家庭も持った。2009年に映画祭で訪れたスイスで身柄拘束されたことはあるも、翌年には釈放されて、フランスに戻っている。
とはいえ、その出自に加えて、アメリカで巻き込まれた悲劇と、自ら起こした事件によって、ポランスキーは、“コスモポリタン”というよりは、“デラシネ=根無し草”としての映画人生を、歩み続けているようにも映る。■
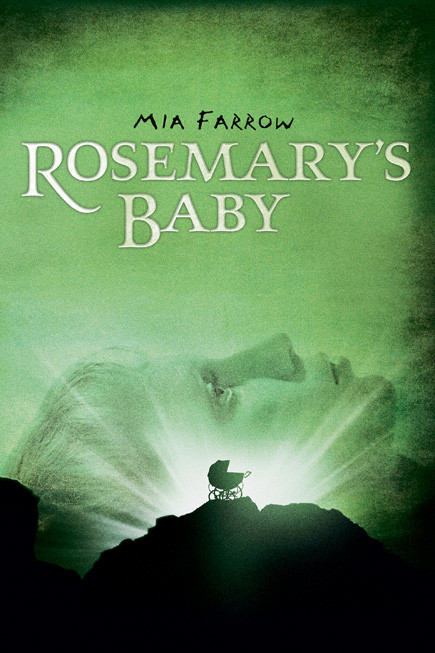 『ローズマリーの赤ちゃん』TM, ® & © 2021 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.
『ローズマリーの赤ちゃん』TM, ® & © 2021 by Paramount Pictures. All Rights Reserved.


