COLUMN & NEWS
コラム・ニュース一覧
-

COLUMN/コラム2018.11.02
悪魔が作らせたのか?97年の予言的映画『ディアボロス/悪魔の扉』が的中させた、21世紀のモラルハザード②
(前回の①はコチラ) この映画『ディアボロス/悪魔の扉』の原題であり原作小説の題名でもある「悪魔の弁護人(Devil's Advocate)」とは、本来は慣用表現である。ラテン語の「アドヴォカートゥス・ディアボリ」がそのまま英語に入ってきたもので、元はカトリックの宗教用語だ。 会議などにおいて、ただの一つの異論も出ずに議論がスムーズにまとまるということは、決して好ましくない。反対意見を言い出しづらかっただけということはないか?そうでないにせよ、思わぬ矛盾や欠点がその満場一致の結論に潜んでいる危険性は絶対に無いと言い切れるのか? そのリスクのヘッジを期待して、あえて反論だけを専門に述べる担当を設ける。本人が本音でどう考えているかはこの際関係ない。とにかく主流意見に論理的に反証していくことが組織における彼の担務なのだ。そのポストがアドヴォカートゥス・ディアボリ、「悪魔の弁護人」もしくは「悪魔の代弁者」である。カトリック教会における「これを奇跡だと認定する」「この人を聖人・福者に列する」といったお墨付きを与える会議にその反論係は置かれた。 こんにち、専門の係でなくとも、会議等でそうした役割を果たしている人のことを、英語でDevil's Advocateという。そして、同じ機能を社会的に担っているのが、近代の司法制度における弁護士なのだ(ついでながら、議会政治における野党も同様。“議論のための議論”、“反対のための反対”にも意義はある)。 「犯人め!」「一番重い刑罰を課せ!」「死刑だ!!」などと大勢が形成されつつある中でも、法律を盾に被告人利益の最大化に努める専門家が必要であることは明らかだ。「盗っ人にも三分の理」という言葉もある。やむにやまれぬ酌量すべき情状もあったかもしれないし、正当防衛や緊急避難的な動機があったかもしれない。それどころか、まったくの濡れ衣や冤罪かもしれないのだ。そうした主張を素人である被告人に代わって法的に代言してくれるプロは、近代法治社会においては不可欠に決まっている。それが無い裁判は「魔女裁判」と呼ぶのだ。 一方でこの賢明なシステムには、ワイドショーの“コメンテイター”なる連中が床屋政談調でよく放言する「殺された被害者より被告の人権ばかりが守られているのは如何なものか」という嫌いがあることもまた、否定のしようもない。原作小説『悪魔の弁護人』のモチーフは、まさにこの近代的ジレンマだ。 主人公はミルトン代表から、妻を殺めた夫を無罪に持ち込む弁護を任される。原作でのミルトン法律事務所はこの手の訴訟を専門に引き受けていて、殺人者を次々に無罪放免にして世間に野放しにしている。まさに、悪魔の手先という文字通りの意味での「悪魔の弁護人」なのである(邦題『ディアボロス/悪魔の扉』はこのWミーニングを活かせていない)。さらにそこから原作の主人公は一歩進んで、悪を世に解き放つこと自体がミルトンの究極目的ではないのか?ミルトンこそ実は本物のサタンそのものではないのか!?という妄想もしくは疑念にとらわれていくことになる。 原作小説は、1990年に出版された。これもまた、予言の書ではなかったのかと思えてくる。 例えばその翌年に、LAでロドニー・キング事件が起こる。仮釈放中の黒人青年ロドニー・キングが車で逃走、パトカーとのカーチェイスになったが観念して車から降りたところ、白人警官たちに組み伏せられ、警棒で滅多打ちにされ、リンチ(私刑のこと。刑法による刑事罰ではなく、個人が私的に好き勝手な罰を加える行為)によって半殺しにされた。彼は無抵抗で武器も帯びていなかったにもかかわらず。その一部始終は近隣住民によってハンディーカムで撮影されていた。全米も、全世界も、私も、その粗いビデオ映像をTVで目撃した。 当然ながら暴力警官たちは告発され、翌年、裁判が始まる。くだんのビデオも証拠として提出されたが、警官側の“悪魔の弁護人”がとった法廷戦術は、裁判をLA郊外の、住民の98%が白人というエリアで開廷させることだった。その人口比率を反映して選任された12人中10人が白人の陪審員は、1992年4月29日、容疑者である白人警官全員を正当防衛で無罪とする評決を下したのである。 直後「人種差別だ!」と怒り狂った一部の黒人住民が暴徒化し、LAは三日三晩の無法状態に突入する。これが92年の「ロス暴動」だ。無関係の白人が引き出されて黒人暴徒に撲殺されるなど合計50人以上の死者が出、放火でいたるところ火災も発生。商店への襲撃と略奪が横行し、住民は銃で武装し自衛と籠城を始め、ついには軍隊が投入される事態となる。州内治安維持を任務とする州兵だけでなく連邦の実戦部隊までもが投入された。BDU迷彩服にPASGT防弾ベスト&ヘルメットにM16A2アサルトライフルという、前年の湾岸戦争と寸分たがわぬ格好の兵士たちがLAの街角に出動し、誰がどう見ても“市街戦”と見えるこの光景はTV中継された。私も当時、食い入るようにニュースを見、見ながらも目を疑った覚えがある。これが、『ビバリーヒルズ・コップ』や『リーサル・ウエポン』で子供の頃から憧れてきたあの街で今、実際に起きているのか!? 第三世界の紛争地帯とかではなく? 次は95年、OJシンプソン裁判だ。黒人でアメフトの元スター選手、引退後に芸能人に転身してからも成功を収めていたOJ(映画俳優としては74年『タワーリング・インフェルノ』、78年『カプリコン・1』等に出演)が、その前の年、白人で美人の元妻とその若い恋人を惨殺した嫌疑を持たれる。逮捕される予定日に、OJは自殺をほのめかし取り乱してハイウェイを逃走。パトカー軍団による一大追跡劇が演じられたりもした。 そして翌年、世紀の裁判が始まる。あらゆる物証、DNAまでもが、犯人がOJであることを物語っていた。DNA鑑定で、犯行現場に遺された血痕とそこにいなかったはずのOJ(手にどこかで怪我を負っていた)から採血したサンプル血液は、570億分の1の確率で一致した。地球上に人間は70億しかいない。 成功者OJは大金を積み、一流どころの有名弁護士を雇い入れていく。当時は“ドリームチーム”などと持てはやされたものだが、本稿では“悪魔の弁護団”と呼ぶとしよう。彼らは、①犯人が犯行時にはめた遺留品の革手袋がOJのものにしてはキツかったこと、を突き、OJが証拠現物の手袋をはめようとしてもキツくてはめにくい、という小芝居まで本人に演じさせて(キツくても最終的にはめられるのだが…)、そのパフォーマンスを鮮烈に陪審員の網膜に焼き付けさせ、他のDNA以下の科学的証拠群の印象をすべて吹き飛ばしてしまうことに成功した。次いで、②現場検証にあたり手袋など重要証拠を発見した白人刑事が差別主義者であった事実、を証明してみせ、この訴訟が人種問題であるかのような争点ズラしをすることにも成功したのである。OJは“悪魔の弁護団”の活躍で無罪評決を勝ちとった。 …何かが、間違っている気がしないか?「疑わしきは被告人の利益に」の大原則は解る。近代法治社会が拠って立つ原理原則だ。これがなければ中世の魔女裁判になってしまう。だがしかし、絶対に、何かが腐敗していないか? 原作小説『悪魔の弁護人』は、このジレンマがモチーフとなっているに違いない。道徳を失くした司法制度、ソフィストとしての弁護士を、厳しく断罪する。 原作におけるミルトン法律事務所は、殺人者など“黒”を“白”と言いくるめる訴訟を専らとしており、そして人殺しを無罪放免にして次々と世間に解き放っている。文字通りに悪魔の手先という意味での「悪魔の弁護人」だと前に記した。その究極の目的は“邪悪を為すこと”だと主人公は疑い始める。 だが一方の映画のミルトン法律事務所の方は、性格が異なる。映画版のそれにとって、主人公は事務所初となる刑事弁護士で、むしろ異色の経歴だ。彼以外は証券取引法や海事法、国際公法、知的財産権法など様々な法律分野の専門弁護士たちで、彼らエリートが結集した“ドリームチーム”がミルトン法律事務所であり、大口クライアントを企業訴訟で勝訴に導いては巨額の弁護報酬を得ている、拝金主義の権化のような組織として描かれている。はっきり言って、カネが目的なのだ。邪悪を為すことではない。 だからこの映画は、道徳を失くした司法、という原作のモチーフも確かに主要なものとして残っているが、それ以上に、強欲を批判すること、虚栄を断罪することの方に力点が置かれている。モチーフが違う、テーマが違うのだ。そして強欲の大罪こそが、21世紀型の悪、完全に行き詰まった2010年代の資本主義が直面することになった最大の巨悪であるということを、我々は現実の差し迫った問題として知っている。1997年のこの映画は、21世紀型モラルハザードを予言してしまっているのである。それどころか、作り手の思惑さえ超えて、2018年の我々が見ると戦慄を禁じえない、いくつもの予知夢的記号に満ちてすらいるのだ。一体どうやって97年の作り手たちがその要素を入れようなどと考えつけたのか?悪魔に導かれたとしか説明がつかない。 深い考えが作り手にあったわけではないだろう。だが序盤に出てくるパーティーのシーンで、我々はまず一度、ギクリとさせられる。思わず体がビクッと反応する、とある予想もしない言葉が飛び出してくるからだ。それはミルトン法律事務所の盛大なパーティー。会場は、主人公が転居してきたマンションの上層階。NYの夜景を一望できる摩天楼のエセ天上界だ。まさに、虚栄の極み。政財界の大物や著名人も顔を見せて、密談と言うにはあまりに大っぴらに蓄財の法的相談が交わされている。そこで、出席した女性陣がこんなことを言って、2018年の我々をギクリとさせるのだ。 (つづき③(完)序盤のパーティーのシーンで突如飛び出す2018年の我々には衝撃的な言葉とは!?) © Warner Bros. Productions Limited, Monarchy Enterprises B.V., Regency Entertainment (USA), Inc. 保存保存
-

COLUMN/コラム2018.10.30
悪魔が作らせたのか?97年の予言的映画『ディアボロス/悪魔の扉』が的中させた、21世紀のモラルハザード①
当チャンネルでの放映予定は当面ないが、ジョニー・デップの『フロム・ヘル』をご記憶だろうか?“切り裂きジャック”の真犯人探しモノで、19世紀末ヴィクトリア朝ロンドンの深い闇と、酸鼻きわめる猟奇描写と、あっと驚く“切り裂きジャック”の正体が見どころの、出来の良いスリラーだった。 クライマックスでついに正体を現したその人物は、傲然とこう言い放つ。「後世の人々は語るだろう、20世紀を生んだのは私だと」 まさしくそうだ。 あれは「猟奇殺人」であり、「快楽殺人」でもあったかもしれず(映画では別の犯行動機があるという話になっていたが)、そして何よりも、犯人がマスメディア(当時は新聞)に犯行声明文を送り付け、そのメディアが発信するどぎついタブロイド的・ワイドショー的情報を大量消費した資本主義社会の都市住民が、恐怖しながらも興奮した「劇場型犯罪」だった。 マスメディアを通じてそうした類いの犯罪に触れた20世紀の大衆は、それを、生理的に恐怖し嫌悪しつつ、道徳的には怒り悲しみつつも、同時にまた、それを旺盛に消費もした。猟奇事件や未解決事件を扱うドキュメンタリーやノンフィクションに恐いもの見たさの好奇心から触れて、深淵を覗き込んでしまった覚えは、誰にだってあるはずだ。20世紀、それは大衆に消費されるコンテンツの一つになった。 『フロム・ヘル』は、19世紀末のロンドンにおいて“先行配信”された20世紀型モラルハザード※のコンテンツが、悪魔の扉を開いた、という物語なのだ。 ※「モラルハザード」という言葉の本来の意味は違う。誤用が広まっている。ここでは誤用と承知で使うが正確な国語的語義は各自でおググりあれ。 そして、本稿で取り上げる1997年の映画『ディアボロス/悪魔の扉』。こちらは、90年代末のNYに存在する社会の歪みが、21世紀型モラルハザードを先取りしており、それが悪魔の扉を開くだろう、と予言した物語で、そして、実際その通りになってしまったのである。そのことを、本稿では恨み節調に書いていきたい。 まず、あらすじから始めよう。冒頭の舞台はフロリダの田舎町だ。主人公(キアヌ・リーヴス扮演)は負け知らずの若手弁護士。いま抱えているのは、被告の男性教諭が原告の女子中学生に強制猥褻をしたという裁判だ。依頼人の教師が“黒”である真相が、我々観客とキアヌの二者にだけ明かされる。女生徒が検察の質問に答えて被害の詳細を勇敢に証言している最中、依頼人は、じっとりと汗ばんだ左手で犯行時と同じ動作を、なでるような、もむような、挿入するような指の動きを、無意識のうちに再現しており、あまつさえ、反対の右手を膨らんできた己の股間にまでこっそり持っていく始末なのだ、デスクの下で。そこは誰の目からも死角。唯一、隣に座っている弁護士キアヌ・リーヴスからのみ、そこは死角ではない。その卑猥な指の動きに気づいてしまった彼は、自分の依頼人が“黒”だと悟る。たちまち生理的嫌悪が湧き上がる。が、弁護士が被告の弁護を放り出すわけにもいかない。周到に練り上げてきた法廷戦術にのっとり、彼は、女生徒が教諭の陰口を叩いていた事実、教諭を嫌い、教諭も彼女をしばしば叱っていた事実、さらには、女生徒が同級生たちと少々エッチな秘密の遊びをしていた事実を、原告の少女本人に向かい声を荒げて突きつけ、動揺させ、泣かせ、被害者であるこの女子中学生が、問題児であり、色ガキであり、先生を逆恨みしているかのように陪審員の印象を操作することに成功する。今回も彼の勝ちだった。無罪評決だ。 この裁判を傍聴していた男から、祝勝会で声をかけられる。彼はNYの法律事務所の人間で、ぜひヘッドハントしたいと言う。条件は破格だ。詳しい話を聞きにNYまで行ってみると、職場環境も社宅も申し分ない。人生の成功者の暮らしだ。事務所はワールドトレードセンターのほど近く(倒壊4年前のツインタワーが映し出される)。オフィスビルの最上階で、モダンインテリアで統一された最先端のデザイナーズオフィスだ。住環境の方は、『ローズマリーの赤ちゃん』のダコタハウスや『ゴーストバスターズ』の高層マンションを思い出させる、19世紀末築のクラシカル&クラッシーな歴史的建築物。法律事務所の代表がその不動産を丸ごと一棟所有していてスタッフを各階に住まわせているのだ。無論本人はペントハウスに君臨し、上層階から下層階へと事務所でのヒエラルキー順にフロアが割り当てられているのである。 この初老の代表がジョン・ミルトン(すごい名前だ!アル・パチーノ扮演)。家父長的なカリスマ性を発散し、確固たる成功哲学を持ち、時にそれを雄弁に語り、夜ごとパーティーを催し、若い美女たちをはべらせ、部下にもそのオコボレを与え、事務所スタッフを完全に支配しているのである。主人公は、このミルトンにまず感謝し、次いで心酔し、その下で働けることを光栄に思う。 …が、しかし。 この『ディアボロス/悪魔の扉』には原作が存在する。1990年に書かれた小説『悪魔の弁護人』がそれで、映画化時に邦訳も出たことがある。主人公がフロリダではなく元々NY郊外に暮らしていたり、ペドフィリア教員がキモでぶハゲおやじではなくレズ女教師だったりと、多少の違いはあるが、ここまではおおむね映画版も原作も同じ展開をたどる。途中から違いが広がっていき、最後には全く別の結末にそれぞれたどり着くのだが、最大の相違は何かと言えば、まず端的に、主人公の妻のキャラクター造形であり、より根本的には、そもそものモチーフとなっているもの、テーマが違うのである。 映画版で奥さんを演じるのはシャーリーズ・セロンだ。中学教諭の強制猥褻裁判でも夫を応援し、勝訴が決まれば誰より喜ぶ。野心も強く、NYでのセレブ新生活に大興奮する。気っ風の良い田舎の元ヤン若妻みたいな辣腕カーディーラーの女性だった。しかし、そんな彼女がNYで次第に精神に変調をきたし、泣きじゃくりながら被害妄想と神経衰弱の症状に陥っていく。 一方、原作小説の方では真逆のキャラクターとして描かれている。NY郊外の弁護士家庭という中の上クラスの生活に満足している専業主婦で、その地域社会に愛着も抱いており、上を目指して別の生活に飛び込もうという気はさらさら無い。夫が強制猥褻容疑の被告の弁護を担当し原告の女子中学生を人格攻撃したことも恥じている。そんな彼女が、マンハッタンに移って豪華な暮らしを始めると、カネと消費の亡者に豹変するのだ。 要は、どちらも中盤で奥さんのキャラクターがガラリと一変してしまうのである。そのトリガーとなるのが「悪魔」という本作のキーワードだ。 映画版では、奥さんシャーリーズ・セロンが、この、人も羨む勝ち組ライフのふとした瞬間に、何か禍々しい、悪魔的な存在をチラチラ垣間見るようになり、フロリダではあれほど明朗快活だった彼女が、オカルト的な影に怯えて田舎に戻りたいと泣いて懇願しだす。主人公キアヌには悪魔の影など見えないのだが、妻の方は妄想なのか何なのか、不吉な気配を繰り返し感じるようになる。 「妄想なのか何なのか」と書いたが、これはつまり、いわゆる「ニューロティック・スリラー」的展開だ。この映画は、慣れない贅沢暮らしでノイローゼになり追い詰められていく心を病んだ庶民女性の物語なのか?それとも、本当に悪魔は実在するのに、それを旦那を含む誰からも信じてもらえない孤立した女性の物語なのか?どちらなのか!? それでクライマックスまで興味を持続させるのがニューロティック・スリラーというジャンルである。 一方、原作の方もニューロティックなのだが、悪魔が実在するのか妄想なのか、どちらなのかで読者を翻弄するのは、こちらでは主人公である旦那の方だ。ミルトン代表から殺人者の弁護を任され、良心の呵責に苦しむのみならず、ミルトンこそ実は本物の悪魔ではないのか!?と疑いだす。疑うほどに、逆に妻の方は、夫のことを精神異常あつかいしつつ、自身は浪費に明け暮れていく。悪魔に取り込まれつつあるのか? ヒロインである奥さんが、このように原作と映画化版とで正反対に描かれるのだが、より重要なのは、そもそもモチーフが違う、テーマが違う、ということの方だ。次回はそこに触れていきたい。 (つづき② 原題「悪魔の弁護人(Devil's Advocate)」は慣用句。その意味を知っているか?) © Warner Bros. Productions Limited, Monarchy Enterprises B.V., Regency Entertainment (USA), Inc. 保存保存 保存保存
-
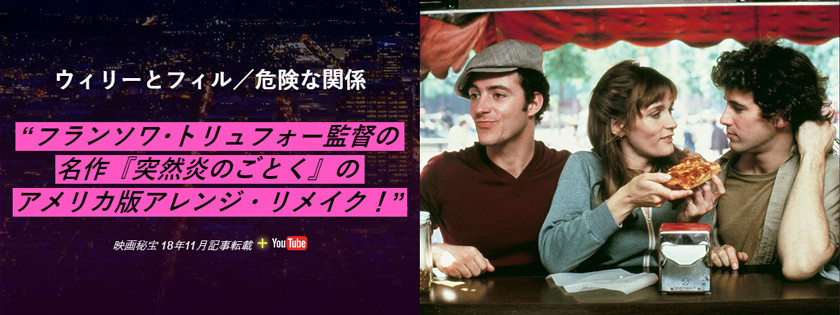
COLUMN/コラム2018.10.23
フランソワ・トリュフォー監督の名作『突然炎のごとく』のアメリカ版アレンジ・リメイク!
今回紹介するのは『ウィリーとフィル/危険な関係』(80年)。これは日本では劇場公開されず、TVで1度放送されただけで、その後VHSもDVDも出ていません。ものすごく珍しい映画のひとつです。この映画は1970年から1980年の10年間を描いた物語で、マーゴット・キダーがヒロインを演じています。この女優さんはこのあいだ亡くなってしまいました。その追悼放送の意味も込めています。 マーゴット・キダーの周りにいる2人の男が、ウィリーとフィル。この3人の関係を描いているのですが、彼女をめぐって男2人が争ったりせず、男たちは彼女がどちらを愛していても幸せなんです。しかも男同士、ものすごく仲がよくて、愛し合っている。そんな三角関係なんですね。この映画の最初、名画座でのある映画の上映シーンから始まるんですけど、それはフランス映画で、フランソワ・トリュフォー監督が1962年に作った“JULES AND JIM” という映画。日本では非常に変で『突然炎のごとく』というタイトルなんですが(笑)、そのジュールとジムを、ウィリーとフィルが観ているところからこの映画は始まります。 この『突然炎のごとく』という映画がいかに世界中の映画に影響を与えたかを知らないと、なぜ『ウィリーとフィル』という映画が作られたのかわからないと思います。『突然炎のごとく』は、これまでの結婚制度であるとか男尊女卑とかを破壊するような、革命的な映画として衝撃を与えて、62年にこれが公開された後、60年代のカウンターカルチャーという、世界的な文化革命が起こるんですね。その起爆剤となった映画なんです。 そしてこの『ウィリーとフィル』は、ニューヨークに住んでいるイタリア系とユダヤ系の男同士。ウィリーのほうは高校の先生でユダヤ系、非常にまじめな男です。フィルは写真家でイタリア系の女ったらし。この一見まったく合わないような2人が『突然炎のごとく』を観に行って、意気投合します。イタリア系のフィルを演じているのはレイ・シャーキーという俳優さんで、この人は若くして亡くなったので代表作がそんなにないんですが、ユダヤ系のウィリーを演じているマイケル・オントキーンという人は、『ツイン・ピークス』(90 ~ 91年)の保安官のハリー・トルーマンを演じた人として、日本では非常に有名ですね。この2人が一妻多夫の映画である『突然炎のごとく』を観たあとに、ある女性と出会います。それが、マーゴット・キダーです。彼女を2人とも愛して、10年間ずっと、くっついたり離れたりしながら暮らしている。ちなみに『突然炎のごとく』はこの映画だけじゃなくて、まずアメリカでものすごいブームを呼んだときに、影響を受けたのが『俺たちに明日はない』(67年)なんですね。さらに『明日に向って撃て!』(69年)もそうでした。 この『ウィリーとフィル』は、監督であるポール・マザースキーの自伝的なものでもあります。この人は実際に主人公たちと同様にNYから出てきた人で、TVの仕事をして、その後ハリウッドに行き映画監督になったので、フィルのたどる道は、マザースキー監督自身がたどった道でもあるんですね。こういった感じで事実がすごく反映されているんですけど、中でもマーゴット・キダー扮するヒロインの非常に自由な、結婚をしても結婚というものに縛られず、2人の男を同時に愛するシングルマザーとなるんですが、この彼女のキャラクターには、キダー自身のすごく自由な性格も投影されていますね。この映画は、一見何の映画なのかわからない、時代性を映しすぎているからという問題があるんですけど、知れば知るほど非常に深い映画です。■ (談/町山智浩) MORE★INFO. 当初はウディ・アレンとアル・パチーノの主演で企画されていた。撮影はウィリー役にジョン・ハードを配して始まったが、最初の週でクビになった。ナタリー・ウッドが自身の役でカメオ出演している。フランス映画好きのマザースキー監督、本作の後にも『素晴らしき放浪者』(32年)をリメイクした『ビバリーヒルズ・バム』(85年)を撮っている。
-

COLUMN/コラム2018.10.19
男たちのシネマ愛『モリー』2018年11月放送
映画ライターなかざわひでゆき×ザ・シネマ飯森盛良の対談シリーズ「男たちのシネマ愛」が今、初の音声ファイルとなって帰ってきた!今回熱く語るのは、名物特集「激レア映画、買い付けてきました」として調達してきた2018年11月の3作品。3本目は、ハートウォーミングな兄妹のドラマを、90年代末の美しすぎるLAを舞台に綴る感動作『モリー』。90'sリバイバルの今、このキラっキラ感にヤラれろ!うおっまぶしっ!!
-

COLUMN/コラム2018.10.18
~昔々イタリアで~レオーネが夢見たもの 『ウエスタン』
セルジオ・レオーネ監督の『ウエスタン』の冒頭。荒野に佇む小さな駅に、悪党面のガンマンたちが現れる。演じるは、ハリウッド製B級西部劇の悪役として鳴らしたジャック・イーラムに、ジョン・フォード組常連の黒人俳優ウディ・ストロードら3人。老駅員に凄んでみせ、他の乗客を追い払うと、3人はそれぞれ己の位置を決めて、待ち伏せの態勢を取る。やがて列車が到着するも、降りる者はなく、拳銃を構えていた3人の緊張が、ふっと緩む。 ところがその時、どこからともなくハーモニカの音色が聞こえてくる。列車が走り出した線路の向こう側に、チャールズ・ブロンソンが演じる1人の男が立っている。やがて3人vs1人の間で、各々の拳銃が火を噴く瞬間が訪れる。…生き残ったのは、ハーモニカの男だけだった…。 レオーネ作品ならではの、エンニオ・モリコーネの旋律も聞こえてこないまま、14分30秒の長きに渡る、このオープニングに関しては、初公開時から厳しい意見が寄せられた。ここで端的な批判の例として挙げるのは、映画評論家の二階堂卓也氏の指摘。労作にして史料的価値も高い、二階堂氏の名著「マカロニアクション大全 剣と拳銃の鎮魂曲」(洋泉社 1999年初版刊行)の中で、次のように断じている。 「思わせぶり過多な演出と執拗なクロース・アップの手法にはいささか辟易させられた。この二つは冒頭から早くもエンエン……といった調子で表現される」「三人の無法者が駅からホームへ出るまでが実に長い」「…意味ありげで、実は何もない俳優たちの所作は頻繁に撮し出され、これには閉口せざるをえないのだ」 なるほど、“マカロニ・ウエスタン=イタリア製西部劇”を、1960年代中盤からリアルタイムで追ってきた筆者ならではの、正しき識見に思える。レオーネ監督が、『荒野の用心棒』(1964)『夕陽のガンマン』(1965)『続・夕陽のガンマン/地獄の決斗』(1966)の、いわゆる“ドル箱三部作”で確立して磨きを掛けた得意技を、「これでもか!」と押し付けてくる様に、ウンザリといったところか。「過ぎたるは猶及ばざるが如し」というわけだ。 しかし私の場合、事情が違う。リアルタイムでスクリーン鑑賞したレオーネ作品は、彼の遺作となった『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』(1984)のみ。他の作品は、彼がこの世を去った、1989年以降に初めて触れている。 原題が“Once Upon A Time In The West=昔々、西部で”という本作は、まず“マカロニ・ウエスタン”の世界を確立した、“ドル箱三部作”の総決算的な位置付けにある。それと同時に、『夕陽のギャングたち』(1971)『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』へと続く、ハリウッド資本が大々的に導入された、“ワンス・アポン・ア・タイム三部作”の第1作に当たる。 『ウエスタン』は、60年の生涯で10本に満たない監督作しか残せなかったレオーネが、それでも“巨匠”と言われるに値する風格を見せつけた作品と、私には映る。「過ぎたる」部分にこそ、レオーネの“円熟”そして“野心”が見えてくるのである。 些か“作家主義”が過ぎるという誹りを、免れないかも知れない。しかしレオーネが死してから、そのフィルモグラフィーを追うようになった者としては、決して間違った見方ではないだろう。 “マカロニ…”で名を成したレオーネが、終生憧れたアメリカへの想いを吐露したと言われる、“ワンス・アポン・ア・タイム三部作”。その第1作『ウエスタン』に籠められた“アメリカへの想い”は、実はレオーネ1人だけのものではない。 本作原案に、レオーネと共にクレジットされている、ベルナルド・ベルトルッチとダリオ・アルジェント。後にイタリア映画を代表する存在になる2人だが、当時は20代。ベルトルッチは、駆け出しの映画監督。アルジェントはまだ、映画ジャーナリストだった。 この2人が数か月の間、レオーネ邸に呼ばれては、『ウエスタン』のストーリーのガイドラインを組み立てていった。そんな2人はレオーネと同じく、ジョン・フォード監督作品を代表とする、ハリウッド製西部劇をこよなく愛していた。 レオーネは本作で目指していたものを、後に次のように語っている。 「アメリカの西部劇の伝統的な筋立て、道具立て、背景、そして個々の作品への言及―こういったものを使って、私なりのやり方で国民の創生の物語を作ってやろう、というのが基本アイデアだった。伝統に挑戦したかったんだ。ありふれたストーリーに昔ながらの登場人物たちを配しながら、偉大でロマンティックな大西部を消滅させようとするアメリカ史上最初の経済的大発展の中で、最後の瞬間を生きようとしていた時代のアメリカを再構築したかったんだよ」 『ウエスタン』は、オープニングの待ち伏せシーンが、『真昼の決闘』(1952)へのオマージュであるのをはじめ、様々な“西部劇映画”からの引用に満ちている。『アイアン・ホース』(1924)『シェーン』(1953)『追跡』(1947)『捜索者』(1956)『赤い矢』(1957)『大砂塵』(1954)『ウィンチェスター銃'73』(1950)『ワーロック』(1959)等々。こうした引用の中には、ベルトルッチがレオーネに気付かれぬ内に、イタズラ小僧のようにこっそりと潜り込ませたものもある。作品完成後に指摘されたレオーネは、激怒したという。 その上で『ウエスタン』には、3人にとってイタリア映画界の偉大な先達である、ルキノ・ヴィスコンティ監督の『山猫』(1963)の影響を、強く見出せる。『山猫』は、時代の波に取り残されたイタリア南部の貴族階級が、北部から吹く革新の風によって、没落を決定づけられる物語。一方『ウエスタン』では、馬に乗り西部を開拓したガンマンたちが、鉄道によって財を成さんとする者たちに、居場所を追われていく。 『ウエスタン』キャストのトップにクレジットされるのは、クラウディア・カルディナーレ。『山猫』では、新しい時代の成金勢力者の娘役だった彼女に、本作では、都市部から西部に移り住み、最終的には根を張って生きていくことが提示される、高級娼婦出身のヒロインを演じさせている。これは当然、意識的なキャスティングであろう。 チュニジア出身のイタリア人女優カルディナーレがヒロインの物語で、西部の滅びゆく男たちを演じるのは、チャールズ・ブロンソン、ジェイソン・ロバーズ、そしてヘンリー・フォンダ。彼らはまさに、レオーネのアメリカへの憧れを体現したような俳優たち。特にブロンソンとフォンダのキャスティングは、レオーネにとっては数年来の念願だった。 ハーモニカを吹きつつ復讐を企てながら、ヒロインを支えるように立ち回る流れ者役のブロンソン。『荒野の七人』(1960)で彼を見初めたレオーネが、かつて『荒野の用心棒』(1964)の主役をオファーした経緯がある。しかし、元はイタリア語で書かれた脚本を、妙な英語で訳したものを渡されたブロンソンは、一読すると、にべもなく断った。 余談になるが、ここでブロンソンが『荒野の…』を受けていたら、クリント・イーストウッドに主役が行き着くことはなかった。そうなると、後の“ダーティハリー”にして、アカデミー賞監督であるイーストウッドの今日も、なかったかも知れない。 さて、そんな『荒野の…』主役に関しては、ブロンソンにオファーする前、レオーネが誰よりも出演を熱望した第1候補がいた。それが、名優ヘンリー・フォンダだった。 しかし『荒野の…』時には、まったく無名のイタリア人監督だったレオーネ。彼の想いはフォンダ本人まで届くことなく、そのエージェントから門前払いの憂き目に遭ってしまった。 そして“ドル箱三部作”でレオーネが名声を得た上で、改めての『ウエスタン』出演のオファー。フォンダはレオーネと面談し、未見だった“ドル箱三部作”を観た上で、首を縦に振った。その裏には、フォンダの友人で、『続・夕陽のガンマン…』の主要キャストだった、イーライ・ウォラックの尽力もあったという。 フォンダが『ウエスタン』で演じたのは、鉄道成金の手先になって、幼き子どもでも躊躇なく撃ち殺す、冷酷非情なガンマン。そしてヒロインのカルディナーレも、彼に犯されてしまう。『若き日のリンカーン』(1939)『荒野の決闘』(1946)などで清廉なイメージの強かったフォンダに、敢えて“悪役”をあてたのである。 フォンダは役作りのため、ヒゲをたくわえ、ブラウンのコンタクトレンズを入れて、ロケ地へと現れた。レオーネは直ちに、ヒゲを剃ってコンタクトも外すように、フォンダに命じた。レオーネの憧れた、ブルーの瞳のままのフォンダに“悪役”を演じさせることこそ、大西部が消滅していく様の象徴だったのかも知れない。 こうして理想のキャストを得た上で、ジョン・フォードの『駅馬車』(1939)などに登場する、アメリカ・モニュメントバレーでのロケも実現したレオーネ。2時間45分という長尺で、『ウエスタン』を完成させた。 興行の結果で言えば、フランスでの大ヒット以外は、ヨーロッパ各国で、“ドル箱三部作”の興行収入を下回る結果に。更にはアメリカでは、その長さを嫌ったスタジオ側によって、20分のカットが行われて作品のリズムが狂わされた上に、観客がフォンダの悪役に抵抗を覚えたせいもあってか、惨憺たる成績に終わった。 こうした流れは、“ワンス・アポン・ア・タイム三部作”を通じてのものとなり(遺作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』では、もっと悲惨な短縮&再編集が行われた)、レオーネが撮った“アメリカ映画”が、初公開時に観客席を埋めることは、ついぞ起こらなかった。 しかし『ウエスタン』も『ワンス・アポン…』も、現在ではレオーネの望んだ形が“正規版”。再評価が大きく進んでいる。 レオーネが、生前には遂に掴めなかったアメリカの夢。しかし彼が死して30年近く経った今、その作品の輝きは“映画史”の中で、年を経るごとに増しているかのようだ。◾︎ TM & Copyright © 2018 by Paramount Pictures Corporation. All rights reserved
-

COLUMN/コラム2018.10.16
男たちのシネマ愛『スモール・タウン・イン・テキサス』
映画ライターなかざわひでゆき×ザ・シネマ飯森盛良の対談シリーズ「男たちのシネマ愛」が今、初の音声ファイルとなって帰ってきた!今回熱く語るのは、名物特集「激レア映画、買い付けてきました」として調達してきた2018年11月の3作品の2本目、ニューシネマ風味の効いた香ばしい70'sアクション、本邦初公開『スモール・タウン・イン・テキサス』!にしても何この展開!!?? 見れるのはザ・シネマのみ!!!
-

COLUMN/コラム2018.10.15
フェリーニ初のカラー映画は、自身の夫婦生活を投影したセクシュアルでサイケデリックなダーク・ファンタジー『魂のジュリエッタ』
イタリア映画の巨匠フェデリコ・フェリーニ。彼の映画に出てくる主人公たちは、しばしば異空間のような世界をひたすら彷徨(さまよ)う。高度経済成長に浮かれる現代ローマを舞台にした『甘い生活』(’60)然り、退廃的で享楽的な古代ローマの混沌としたデカダンを再現した『サテリコン』(’69)然り、そして旧世代のプレイボーイがウーマンリブ的な女性だらけの世界に足を踏み入れる『女の都』(’80)然り。これらの作品では、狂言回しとしての主人公をある種の象徴的な世界へと放り込み、放浪の過程で多種多様な人物と交わらせることによって、映画が作られた時代の空気や精神を鮮やかに浮き彫りにしていく。あえて明確なストーリー性を薄め、映像にも寓話的なシンボリズムを多用するのが特徴だ。この手法をさらに個人の内面へと推し進め、主人公のパラノイア的な心象世界にフェリーニ自身の映画監督としての苦悩や迷いを投影したのが『81/2』(’63)であり、その姉妹編に当たるのが本作『魂のジュリエッタ』(’65)である。 主人公はブルジョワ階級の人妻ジュリエッタ(ジュリエッタ・マッシーナ)。結婚15周年のお祝いを準備していた彼女だが、大勢の友達を引き連れて帰ってきた夫ジョルジョ(マリオ・ピスー)は、すっかりそのことを忘れていたようだ。釈然としないままパーティの夜は更け、やがて余興の降霊会が始まる。幽霊オラフに「あなたは不幸な人間だ」と言われて気を失うジュリエッタ。それ以来、彼女の脳裏で何者かが囁くようになり、忘れかけていた過去の記憶が次々とフラッシュバックし、あらゆるところで悪夢の断片を見るようになる。 そんなある晩、寝言で知らない女性の名前を2度もつぶやく夫。不安に駆られたジュリエッタは、親友ヴァレンティナ(ヴァレンティナ・コルテーゼ)に誘われ両性具有の預言者ビシュマ(ヴァレスカ・ゲルト)の助言を仰ぐ。男を悦ばせる術を学べと言われて抵抗感を覚えるジュリエッタ。しかし、家に戻るとスペインからやって来た夫の友人ホセ(ホセ・ルイス・デ・ヴェラロンガ)を紹介され、夫にはない繊細で知的な魅力を持つ彼に惹かれる。さらに、自由奔放な隣人スージー(サンドラ・ミーロ)と親しくなった彼女は、知らずに招かれた乱交パーティで出会った若い美青年にベッドへ誘われるものの、すんでのところでハッと我に返って逃げ出す。 なお一層のこと心をかき乱され、現実と妄想の境界線がどんどん曖昧になっていくジュリエッタ。興信所の調査で夫の浮気も決定的になった。アメリカ人の精神分析医から「本当は夫と別れることを望んでいるのじゃないか、自由になることを恐れているだけじゃないか」と指摘され戸惑う彼女は、夫の不倫相手と直接会おうと意を決するのだったが…。 『カビリアの夜』(’57)以来、久々に愛妻ジュリエッタ・マッシーナを自作に起用したフェリーニ。『81/2』の主人公である映画監督グイドがフェリーニの分身であったように、本作のジュリエッタはジュリエッタ・マッシーナ本人の分身とも考えられるだろう。事実、『魂のジュリエッタ』には、フェリーニ夫妻の私生活を投影したであろうと思われる部分が少なからずある。おしどり夫婦と呼ばれて50年近くの結婚生活を添い遂げた2人だが、その一方で日常生活は家庭内別居にも等しく、同じ家の中でもお互いの居住空間は別々だったという。しかも、夫フェリーニの女性関係は半ば公然の事実。本作に出演している女優サンドラ・ミーロとも不倫の噂があった。必ずしも順風満帆な結婚ではなかったのだ。 一説によると、あまりにも現実の夫婦生活に近い要素がストーリーに盛り込まれていることから、当初は脚本を読んだジュリエッタが強く憤慨していたとも伝えられている。このままだと2人は離婚してしまうのではないか?と周囲の友人が心配したほど、一時は険悪な仲になってしまったそうだ。『81/2』では映画監督として創作に行き詰まった自身の苦悩と葛藤を描いたフェリーニだが、本作では妻ジュリエッタを介して自身の複雑な結婚生活の実態を、ある種のフェミニズム的な幻想譚へと昇華させた。そういう意味でも、本作は『81/2』に続くフェリーニの私小説的な映画として見るべきなのだろう。 目を引くのは全編に散りばめられた鮮烈な色彩と、シュールでシンボリックな幻想的ビジュアルの数々だ。本作はフェリーニにとって初めてのカラー映画。色とりどりの衣装からセット、照明に至るまで、まるで色を得た歓びが弾けるかのように、ありとあらゆる色彩が所せましとスクリーンを埋め尽くす。ヒロインの秘めたる性的願望と罪悪感を具現化したような悪夢的なイメージショット、前衛的かつ実験的な演出や画面構図もワクワクするくらい刺激的だ。今見ても全く古さを感じさせない。さながらセクシュアルでサイケデリックなダーク・ファンタジー。そのクセになるトリップ感は、以降の『サテリコン』や『カサノバ』(’76)、『女の都』にも相通ずるものがあると言えよう。 製作費は当時のイタリア映画としては破格の300万ドル。それゆえ、プロデューサーのアンジェロ・リッツォーリは、主演がジュリエッタ・マッシーナでは興行的に弱いのではないか?と心配し、代わりにキャサリン・ヘプバーンを推薦してきたがフェリーニは頑として折れなかったという。その代わりということなのかもしれないが、両性具有の預言者ビシュマ役にハリウッド・スターを起用しようと考えたフェリーニは、渡米した際に往年の大女優メエ・ウェストにオファーを持ちかけたが断られた。結果的に選ばれたのは、パンク・カルチャーの源流になったとも言われるドイツ出身の前衛舞踊家ヴァレスカ・ゲルトだ。 本作はジュリエッタ・マッシーナ以下の華やかな女優陣も見どころだ。ジュリエッタの隣人スージー、祖父と駆け落ちしたサーカスの踊り子ファニー、そして幻覚に出てくる幽霊アイリスの3役を演じるサンドラ・ミーロは、ロベルト・ロッセリーニ監督の『ロベレ将軍』(’59)などで一世を風靡した小悪魔的な女優で、結婚を機に芸能界を引退していたが、フェリーニのラブコールに応えて『81/2』の映画監督グイドの愛人カルラ役でカムバックした経緯があった。本作では決してセクシーとは言えない主演女優ジュリエッタに代わって、妖艶な魅力を存分に振りまいている。85歳になった今もバリバリの現役だ。 ジュリエッタの親友ヴァレンティナには、ハリウッドでも活躍したイタリアの知性派女優で、フランソワ・トリュフォーの『アメリカの夜』(’73)でアカデミー助演女優賞に輝いたヴァレンティナ・コルテーゼ。ジュリエッタの妹でテレビ女優のシルヴァには、『鉄道員』(’56)の清純な娘役から国際的な人気セクシー女優へ成長したシルヴァ・コシナ、もう一人の妹アデーレには同じく『鉄道員』の母親役で有名なルイーザ・デッラ・ノーチェが扮している。また、若いメイドのエリザベッタ役を演じているミレーナ・ヴコティッチは、『ブルジョワジーの秘かな愉しみ』(’72)に『自由の幻想』(’74)、『欲望のあいまいな対象』(’76)など晩年のルイス・ブニュエル作品に欠かせない常連で、アンドレイ・タルコフスキーの『ノスタルジア』(’83)や大島渚の『マックス・モン・アムール』(’86)にも出ていた知る人ぞ知る名脇役女優だ。 そして、ジュリエッタの潜在的なコンプレックスの元凶である威圧的な母親として強烈なインパクトを残すのが、ファシスト時代のイタリア映画界を代表するスター女優カテリーナ・ボラット。彼女もまたサンドラ・ミーロと同様に、引退していたところをフェリーニに熱望され『81/2』で女優復帰し、フェリーニの弟子でもあったピエル・パオロ・パゾリーニの『ソドムの市』(’75)では少年少女に背徳的な物語を語って聞かせる老貴婦人を演じていた。 なお、ジュリエッタがメイドたちと一緒に見ているテレビの美容番組で、顔面美容法のお手本を披露しているモデルは、実際に当時のヨーロッパで活躍していたアメリカ人トップモデルで、マリオ・バーヴァ監督の『モデル連続殺人!』(’64)で演じた顔面を焼かれて殺される犠牲者役が印象深いメアリー・アーデン。同じ番組の最後を締める女性司会者役には、ヴィットリオ・デ・シーカの『あゝ結婚』(’64)やダミアーノ・ダミアーニの『警視の告白』(’71)などで知られる美人女優で、’60年代お洒落系ガーリー映画の名作『キャンディ』(’68)ではリンゴ・スターの童貞を奪ったキャンディに復讐しようとする凶悪バイカー姉妹のリーダーを演じていたマリルー・トロがカメオ出演している。 また、友人や知人を自作に出演させることの多いフェリーニ。本作でも彼が普段から助言を得ていた自称ローマ警察の公認霊媒師ジーニアスことエウジェニオ・マストロピエトロが降霊会の霊媒師役で登場し、イタリアの文豪サルヴァトーレ・クァジモド夫人で元プリマドンナのマリア・クマーニ・クァジモドが預言者ビシュマの講演会で観衆の一人(ピンクの花飾りのついた帽子を被った白いドレスの御婦人)として顔を見せている。 ゴールデン・グローブ賞をはじめ、ニューヨーク批評家協会賞やナショナル・ボード・オブ・レビュー賞の外国語映画賞を獲得し、本国イタリアでもシルバー・リボン賞(イタリア版ゴールデン・グローブ)の助演女優賞(サンドロ・ミーロ)と美術賞(ピエロ・ゲラルディ)に輝いた『魂のジュリエッタ』。恐らく一般の観客にとっては斬新すぎたのだろう。当時は興行的に失敗してしまい、オムニバス映画『世にも怪奇な物語』(’68)を挟んだ次回作『サテリコン』まで4年のブランクが空く結果となってしまったが、サイケデリック・ムーブメントとポップ・アートの時代を敏感に捉えたフェリーニの先鋭的な映像センスは今なお刺激的だし、なによりもその自由奔放で豊かなイマジネーションには感動と興奮を禁じ得ない。◾︎ ©1965 RIZZOLI
-

COLUMN/コラム2018.10.12
『ヘルハウス』“オカルト映画ブーム”から45年後の楽しみ方。
呪われた幽霊屋敷の怪異を描く『ヘルハウス』は、1974年9月に日本で劇場公開されている。そしてこの公開のタイミング故に、“オカルト映画ブーム”の文脈で語られることが多い作品となった。 幽霊譚やモンスター、魔女・悪魔など、科学では割り切れない不可思議な超常現象をモチーフやテーマにした作品は、映画の草創期から、繰り返し製作されてきた。ではこのジャンルが、“オカルト映画”と呼ばれるようになったのは、いつ頃からだったのか? その嚆矢として度々取り上げられる作品に、ロマン・ポランスキー監督の『ローズマリーの赤ちゃん』(1968)がある。しかし巷で“オカルト映画”という言葉が浸透したのは、やはりウィリアム・フリードキン監督の『エクソシスト』(1973)以降であろう。少女に取り憑いた悪霊パズズとカソリックの神父の対決を描いて、世界的な大ヒットとなったこの作品は、“オカルト映画ブーム”のまさに立役者となった。 後続の作品の中には、『オーメン』(1976)や『シャイニング』(1980)『ポルターガイスト』(1982)等々の優れものもあった。しかし一方で、“エクソシストもの”とでも言うべき、オリジナリティに欠けるエピゴーネンも、数多登場することとなる。 さて話は戻って、ここで本題の『ヘルハウス』である。『エクソシスト』の日本公開が、1974年の7月。そして冒頭で記した通り、その大ヒットの余波がある、2か月後の9月に、『ヘルハウス』は公開された。 当初は原題(The Legend of Hell House)をおどろおどろしく直訳した『地獄邸の伝説』という邦題が決まっていたが、急遽原題の一部をピックアップした英語タイトルへとチェンジ!本作の宣伝関係者が『エクソシスト』の大ヒットにあやかろうと、「同じカタカナ五文字の『ヘルハウス』で行け~!」となった結果であろうことは、まったくもって想像に難くない。 そんな経緯もあって、まるで“ブーム”に便乗して、製作・公開されたかのような印象さえある、『ヘルハウス』。しかし“エクソシストもの”のような作品群とは、明らかに一線を画す作品なのである。 『ヘルハウス』の原作・脚本を担当したのは、リチャード・マシスン(1926~2013)。小説家としては、1950年24歳の時にデビューし、現在までに3度映画化された「アイ・アム・レジェンド」(1954)や、「縮みゆく人間」(1957)「奇蹟の輝き」(1978)などSFホラーやファンタジーの名作をものしている。更にはウエスタンやノンフィクションまで、長年に渡ってジャンルを横断する活躍を見せた。 脚本家としても、TVシリーズの「トワイライト・ゾーン」(1959~64)、エドガー・アラン・ポー原作の映画化作品『アッシャー家の惨劇』(1960)『恐怖の振子』(1961)などをはじめ、数多くの映画、TVドラマを手掛けている。 自らの小説を脚色した作品を挙げても、スピルバーグの出世作『激突!』(1971)や、『ある日どこかで』(1980)など、名作・話題作のタイトルが、次々に挙がる。 マシスンは、モダンホラー小説の巨匠・スティーヴン・キングが「私がいまここにいるのはマシスンのおかげだ」と語るような、偉大な存在なのである。そして『ヘルハウス』の原作「地獄の家」(1971)は、彼の手掛けた数々の長編小説の中でも、「最高傑作」と評されることが多い作品なのだ。 この作品に先駆けてマシスンは、霊能力者や超能力者など“サイキック”の歴史を描く、長編小説やTVシリーズなどに挑むものの、頓挫して未完に終わっている。しかしその際に長期に渡るリサーチから、超能力や心霊現象などに関する膨大な知識を得た。そしてそれが、『ヘルハウス』へと注ぎ込まれている。 物語の舞台は、エメリック・ベラスコという富豪が建てた巨大な屋敷、通称“ベラスコハウス”。変態的サディストだったベラスコによって、ここを訪れた多くの者がマインドコントロールされ、乱交や近親相姦、獣姦など痴態を繰り広げた果てに、命を落とした。そしてベラスコ自身も、行方不明となる。 その後“ベラスコハウス”に関しては、2度に渡って科学者や霊能者から成る調査団が送り込まれるも、そのほとんどが命を落とすか正気を失うこととなった。そして本作は、2度目から30年の月日を経て行われることとなった、3度目の調査の顛末を描く。 そのメンバーは、物理学者とその妻、若き女性霊能力者、そして30年前の調査でただ一人生き残った、男性霊能力者の4人。 女性霊能力者は、ベラスコの息子と称する霊と交信し、その魂を屋敷の魔力から解き放とうと力を尽くす。一方で、霊の存在など信じない物理学者は、屋敷やそこに居る者たちに異変をもたらすのは、電磁力のようなエネルギーだと分析し、自らが開発した機械で消滅させようと試みる…。 映画版『ヘルハウス』は、原作にほぼ忠実な展開だが、大きな変更点がある。原作ではアメリカのメイン州に位置したベラスコハウスが、映画ではイギリスに移されている。 幽霊屋敷の怪異譚と言えば、アメリカよりもイギリスの方がやはりしっくりくる。そして監督のジョン・ハフは、1950年代からクラシックホラーを数々世に送り出してきた、イギリスのハマープロのテイストが滲み出るように、演出や画面のルックに趣向を凝らしたという。 ハマープロ仕立てのクラシックな幽霊屋敷に、科学者が西洋合理主義で挑むあたり、1973年、アメリカン・ニューシネマ全盛期ならではの“ホラー映画”とも言える。またこの作品の原作が、スティーブン・キングの『シャイニング』など、後の“モダンホラー”の先駆け的な存在となったことを考えると、映画『ヘルハウス』は、“モダンホラー”とイギリス流“クラシックホラー”のハイブリッドとも言える。 さてこの作品、2018年の今、もう一点大きな見どころがある。それは、良く言えば「渋い」、悪く言えば「地味」な、70年代キャスティング。 物理学者夫妻のクライヴ・レヴィルとゲイル・ハニカット、女性霊能者役のパメラ・フランクリン、そして男性霊能力者役のロディ・マクドウォール。中でもロディ・マクドウォールは、『ヘルハウス』での役どころが、彼のキャリアと重なるのが、大変興味深い。 ロディは、1928年生まれ。ジョン・フォード監督の名作『わが谷は緑なりき』(1941)での主演級の役どころなど、“天才子役”として数多くの映画に出演した。『名犬ラッシーの家路』(1943)で共演以来、エリザベス・テイラーの親友であったことも有名だ。 そんな彼も、子役を卒業する頃から低迷。やむなくハリウッドから離れ、その後ブロードウェイでキャリアを積み、30代になってから映画界へと戻った。それからは主に大作映画で脇を固めていたが、アラフォーの頃に大ヒットシリーズに主演級で出演する。『猿の惑星』シリーズ(1968~73)である。ご存知の方が多いと思うが、このシリーズでのロディは、特殊メイクでチンパンジーになり切っており、自分の顔は一切出ない。 そんなシリーズが終了するタイミングに、顔出しで主演したのが、この『ヘルハウス』なのである。そして本作でのロディの役どころは、30年前の調査での唯一の生き残りである、男性霊能力者フィッシャー。 フィッシャーは、30年前には十代中盤で、“天才少年霊能力者”と謳われる存在。しかし件の調査の際に、心身共に深く傷つき、その後世間から身を隠すように生きてきた。『ヘルハウス』は、そんな男が再チャレンジする話なのでもある。そして“ベラスコハウス”内でただ息を潜めて、「貝の殻に閉じ込もっていた」かのように見えたフィッシャーは、最後に大きな勝利を得る。 天才子役の時代から30年の歳月を経て、40代半ばにして本作に主演したロディ。キャスティングの際、作り手側にロディとフィッシャーを重ね合わせる意識がカケラもなかったとは、正直考えにくい。 本作から12年後、ロディは現代を舞台にした吸血鬼ホラーコメディ『フライトナイト』(1985)に出演する。大ヒットとなったこの作品でのロディの役どころは、気弱なヴァンパイアハンター、ピーター・ビンセント。当初はTV 番組の中だけの偽物のヴァンパイアハンターだったピーターだが、主人公の少年に救いを求められて、本物に成長する。 『ヘルハウス』でのフィッシャー役なしでは、考えにくいキャスティングである。そしてこのヴァンパイアハンターが当たり役となって、ロディは続編『フライトナイト2/バンパイヤの逆襲』(1988)にも再登場となった。 『ヘルハウス』の原作及び映画が、後の様々な作品に及ぼした影響なども考えながら観る。それもまた、本作の楽しみ方であろう。◾️
-
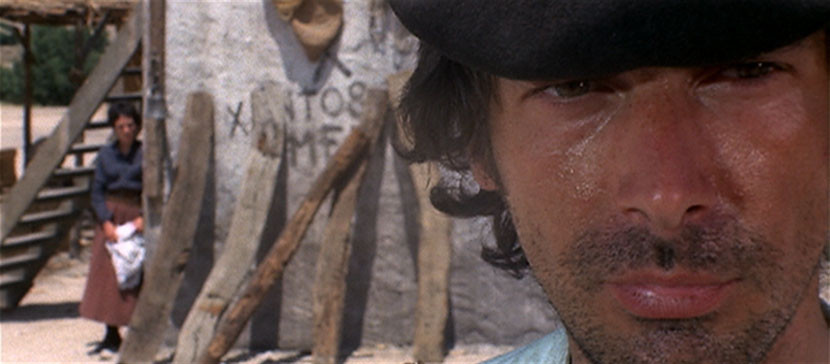
COLUMN/コラム2018.10.11
舞台裏ではスターと監督の軋轢が?有象無象のならず者がメキシコ革命で暴れまわる痛快マカロニウエスタン!『ガンマン大連合』
マカロニウエスタンの巨匠と言えばセルジオ・レオーネだが、もう一人忘れてはならない同名の大御所がいる。それがセルジオ・コルブッチだ。スタイルとリアリズムを追求して独自のバイオレンス美学を打ち立てた芸術家肌のレオーネに対し、シリアスからコメディまでなんでもござれ、荒唐無稽もデタラメも上等!な根っからの娯楽職人だったコルブッチ。多作ゆえに映画の出来不出来もバラつきはあったが、しかし時として『続・荒野の用心棒』(’66)や『殺しが静かにやって来る』(’68)のような、とんでもない傑作・怪作を生み出すこともあった。そんなコルブッチには、メキシコ革命を舞台にした「メキシコ三部作」と一部のマカロニファンから呼ばれる作品群がある。それが『豹/ジャガー』(’68)と『進撃0号作戦』(’73)、そして『ガンマン大連合』(’70)だ。 主人公はスウェーデンからメキシコへ武器を売りにやって来たキザな武器商人ヨドラフ(フランコ・ネロ)と、靴みがきから革命軍のモンゴ将軍(ホセ・ボダーロ)の副官に抜擢されたポンコツのならず者バスコ(トーマス・ミリアン)。国境近くの町サン・ベルナルディーノでは、庶民を苦しめる独裁者ディアス大統領の政府軍と、実は革命に乗じて金儲けがしたいだけだったモンゴ将軍の一味、そして非暴力を掲げて合法的に革命を遂行しようとする理想主義者サントス教授(フェルナンド・レイ)に心酔する若者グループが、3つの勢力に分かれて攻防を繰り広げていた。 モンゴ将軍に呼ばれてサン・ベルナルディーノに到着したヨドラフ。その理由は、町の銀行から押収したスウェーデン製の金庫だった。鍵の暗証番号を知る銀行員を殺してしまったため、スウェーデン人のヨドラフなら開け方が分かるだろうとモンゴ将軍は考えたのだ。成功したら中身の大金は2人でこっそり山分けするという算段。ところが、頑丈な金庫はヨドラフでも手に負えない代物だった。唯一、暗証番号を知っているのはアメリカに身柄を拘束されたサントス教授だけ。そこでモンゴ将軍は、万が一の裏切りを用心してバスコを監視役に付け、アメリカの軍事要塞に捕らわれているサントス教授をメキシコへ連れ戻す使命をヨドラフに託すこととなる。 …ということで、道すがら女革命戦士ローラ(イリス・ベルベン)率いるサントス派の若者たちの妨害工作に遭ったり、ヨドラフに恨みを持つアメリカ人ジョン(ジャック・パランス)の一味に命を狙われつつ、過酷なミッションを遂行しようとするヨドラフとバスコの隠密道中が描かれることとなるわけだ。 ド派手なガンアクションをメインに据えた痛快&豪快なマカロニエンターテインメント。荒々しいリズムに乗ってゴスペル風のコーラスが「殺っちまおう、殺っちまおう、同志たちよ!」と高らかに歌い上げる、エンニオ・モリコーネ作曲の勇壮なテーマ曲がオープニングからテンションを高める。革命の動乱に揺れるメキシコで、有象無象の怪しげな連中が繰り広げる三つ巴、いや四つ巴の仁義なき壮絶バトル。コルブッチのスピード感あふれる演出はまさに絶好調だ。終盤の壮大なバトルシーンでは、『続・荒野の用心棒』を彷彿とさせる強烈なマシンガン乱射で血沸き肉踊り、フランコ・ネロの見事なガンプレイも冴えわたる。コルブッチのフィルモグラフィーの中でも、抜きんでて勢いのある作品だと言えよう。 もともとマカロニウエスタンはロケ地であるスペインの土地や文化が似ている(元宗主国だから文化が似ているのは当たり前だけど)ことから、メキシコを舞台にした映画はとても多いのだが、その中でもメキシコ革命を題材にした作品と言えば、左翼革命世代の申し子ダミアーノ・ダミアーニ監督による社会派西部劇『群盗荒野を裂く』(’66)を思い浮かべるマカロニファンも多いだろう。しかし、コルブッチはダミアーニではない。確かに『豹/ジャガー』は左翼的メッセージがかなり強く出た作品だったが、あれはもともと『アルジェの戦い』(’66)で有名な左翼系社会派の巨匠ジッロ・ポンテコルヴォが監督するはずだった企画で、コルブッチは降板したポンテコルヴォのピンチヒッターだった。政治色が濃くなるのも当然だ。その点、コルブッチ自身が原案を手掛けて脚本にも参加した本作は、基本的に荒唐無稽なエンタメ作品に徹している。世界史に精通していたと言われる博識なコルブッチが、あえてメキシコ革命の史実を無視するような描写を散りばめているのも、その決意表明みたいなものかもしれない。 ただ、脚本の中に政治的な要素が全くないかと言えばそうでもない。金儲けのためなら政府軍にも革命軍にも武器を売る現実主義者ヨドラフ、革命の理想など特に持たず軍隊で威張り散らしたいだけのお調子者バスコ。この火事場泥棒みたいな2人が隠密道中を通じて、市民革命の強い理念に従って行動するサントス教授と若者たちに、少しずつ感化されていく過程が見どころだ。特に、マカロニウエスタンで野卑なメキシコ人を演じさせたら右に出る者のない名優トーマス・ミリアンが演じるバスコのキャラは興味深い。 棚ぼた式にモンゴ将軍の副官となり、虎の威を借る狐のごとくヒーロー気取りで振る舞う、もともと革命の精神とは全く縁のなかった貧しく無教養な男バスコ。「メキシコ人をバカにするな」「外国人と通じている女は罰してやる」「インテリは本と一緒に焼かれろ」。こういう偏った主張をする人間が、政治的混乱に乗じてマウントを取っていい気になるのは、古今東西どこにでもある光景だろう。しかし、そもそもがコンプレックスをこじらせただけのバカであって、根っからの悪人というわけではない。そんな単細胞な男が教養豊かなサントス教授から、本来の革命精神とは相容れない国粋主義の矛盾と欺瞞を説かれ、あれ?俺って実は悪人の側だったわけ?と気づき始め、純粋に自由と正義を信じて革命に殉じていく若者たちに感情移入していく。この視点はなかなか鋭い。 なお、マカロニブームを牽引した2大スターのフランコ・ネロとトーマス・ミリアンだが、映画で共演したのはこれが初めて。ミリアンにとっては意外にも初のコルブッチ作品だった。一方のネロはコルブッチ映画の常連組。監督が彼のアップばかり撮ることに嫉妬したミリアンは、電話でコルブッチに泣きながら抗議したと伝えられている。ただし、イタリア映画の英語版吹替翻訳で有名なアメリカ人ミッキー・ノックスによると、逆にコルブッチがミリアンにばかり気を遣うもんだから、不満に思ったネロがへそを曲げてしまったそうだ。ん~、どっちが本当か分からないが、しかしどっちも本当だという可能性もある。ミリアンがごねる→コルブッチが気を遣う→ネロがへそを曲げる、という流れならあり得るかもしれない。いずれにせよ、コルブッチとネロのコラボレーションはこれが最後となり、当初コルブッチが手掛ける予定だった『新・脱獄の用心棒』(’71)の出演もネロは渋ったという。結局、ドゥッチオ・テッサリが監督に決まったことで引き受けたのだが。いやはや、スターって面倒くさいですね(笑)。 なお、本場ハリウッドの西部劇でもお馴染みのジャック・パランスは、コルブッチの『豹/ジャガー』に続いてマカロニへの出演はこれが2本目。フェルナンド・レイも『さすらいのガンマン』(’66)以来のコルブッチ作品だ。また、ローラ役のイリス・ベルベンはドイツのテレビ女優。『続・荒野の用心棒』以降のコルブッチ作品に欠かせないスペインの悪役俳優エドゥアルド・ファヤルドが冒頭で政府軍の司令官を、ドイツの有名なソフトポルノ女優カリン・シューベルト(後にハードコアへも進出した)がヨドラフと昔なじみの売春婦ザイラを演じている。◾️
-
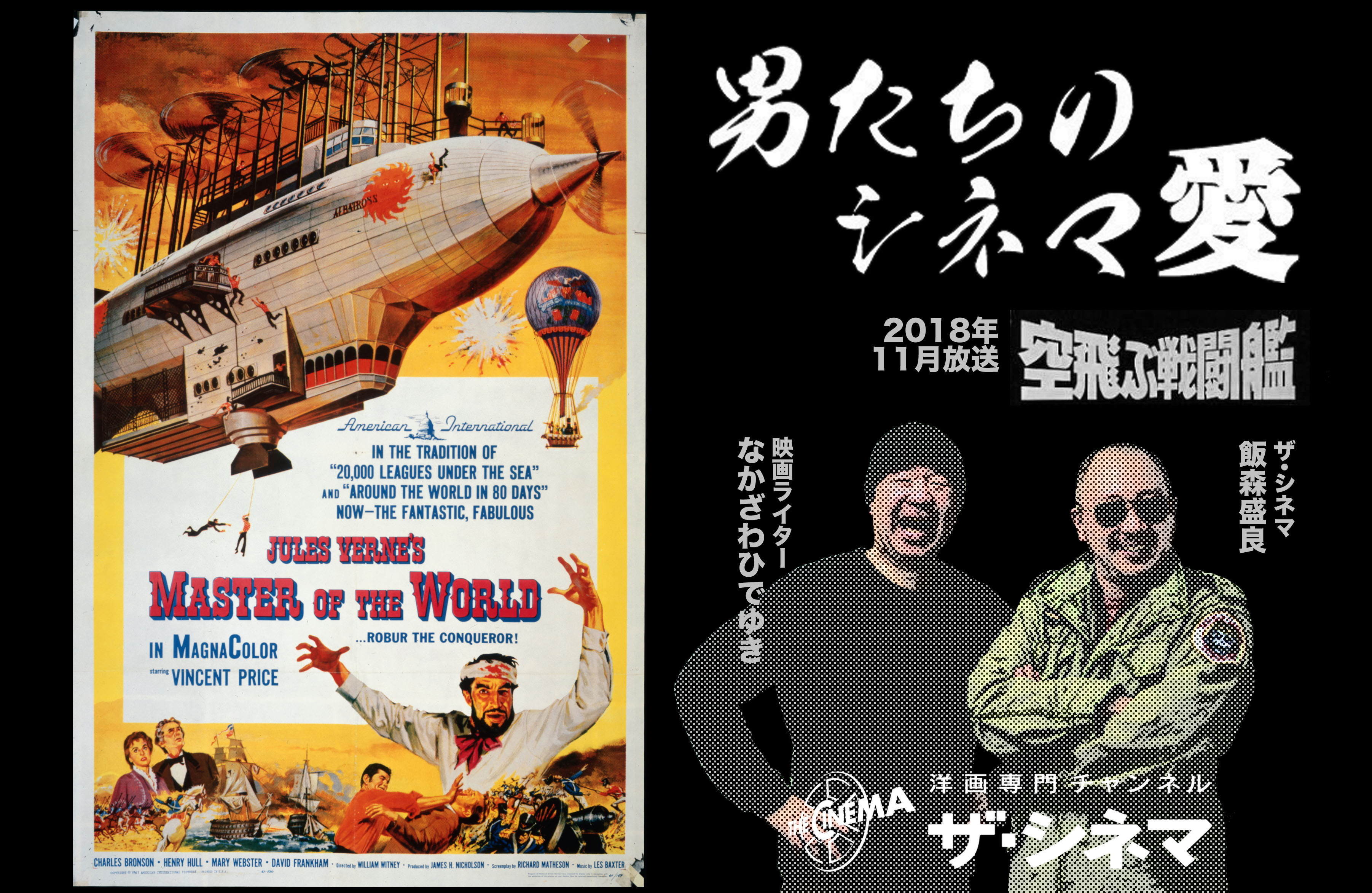
COLUMN/コラム2018.10.10
男たちのシネマ愛『空飛ぶ戦闘艦』
映画ライターなかざわひでゆき×ザ・シネマ飯森盛良の対談シリーズ「男たちのシネマ愛」が今、初の音声ファイルとなって帰ってきた!今回熱く語るのは、名物特集「激レア映画、買い付けてきました」として調達してきた2018年11月の3作品。まずはブロンソン主演スチーム・パンクAIP映画『空飛ぶ戦闘艦』だ!! 未DVD/BD化、VHSとビデオディスクにしかなっていない(はずの)激レア映画。いま見れるのはザ・シネマのみ!!! ※23分頃に「幕府側」と言っているのは「明治新政府側」の大まちがいです。お詫びして訂正いたします。by 飯森