検索結果
-
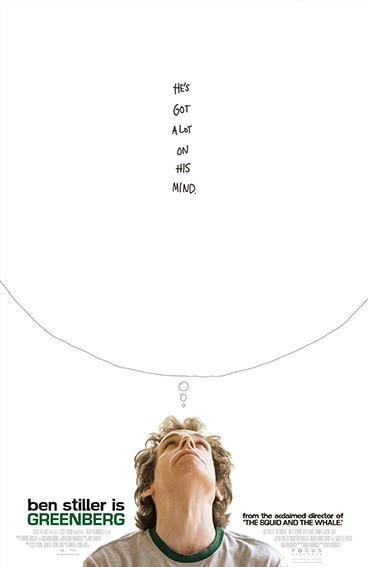
COLUMN/コラム2017.02.08
ベン・スティラー 人生は最悪だ!
ロサンゼルス。裕福なグリーンバーグ家では、雑事を代わりにやってくれるパーソナル・アシスタントを雇っていた。彼女の名はフローレンス。自分探しをしているうちに、大学にいた時間よりも大学を出てからの方が長くなってしまった女子だ。ある日、旅行中の犬の世話を頼まれた彼女は、家長フィリップの兄ロジャーと出会う。留守番を頼まれてニューヨークからやってきたという彼は、かつてはインディロック・バンドで活躍していたものの今は無職。精神病院から出てきたばかりで、気難しくてキレやすい中年男だった……。 『ベン・スティラー 人生は最悪だ!』は、ノア・バームバックにとってとびっきりの異色作である。というのも、彼は生まれ育ったのはブルックリン。最終学歴もヴァッサー大学という生粋のニューヨーカーだからだ。 監督デビュー作は、ヴァッサーを卒業した後も学生街のアパートに居座る若者たちをヴィヴィッドに描いたコメディ『彼女と僕のいた場所』(95年)。26歳という若さでデビュー出来たのは、クエンティン・タランティーノの成功によって、ちょうどハリウッドが若い才能の青田刈りを行なっていた時期だからだ。 とはいえ、バームバックには才能があった。ジョシュ・ハミルトン、エリック・ストルツ、パーカー・ポージー、エリオット・グールドらが出演したこの作品は評論家筋に絶賛を博したのだから。ヴァッサー大学は一時期、新入生の歓迎会でこの作品を必ず上映していたという。 同作の成功後、バームバックは『Mr. Jealousy』(97年)と『Highball』(97年)を立て続けに発表する。しかしデビュー作ほどの評価は得られず、後者に至ってはプロデューサーとの対立によってクレジットも外された形でDVDスルーの憂き目に遭ってしまった。 この事件によってバームバックのキャリアは一旦終わったかに思われたが、彼はウェス・アンダーソン監督作『ライフ・アクアティック』(04年)の共同脚本家として再び脚光を浴び、アンダーソンのプロデュースのもと撮った『イカとクジラ』(05年)で映画監督としても復活したのだった。 80年代のニューヨークを舞台にした同作の主人公は、離婚した両親の家を行ったり来たりする生活を送る高校生ウォルト。バームバックの両親もこの頃に離婚しており、この映画は半自伝作だった。ウォルト役のジェシー・アイゼンバーグの好演も相まって、『イカとクジラ』はスマッシュ・ヒットを記録。バームバックはアメリカ映画界の最前線に返り咲いた。 続く『マーゴット・ウェディング』(07年)も半自伝作だ。妹の結婚式に出席するために実家を訪れる主人公マーゴットの神経質なキャラは、『イカとクジラ』の母親と全く一緒である。但し同作は、ウェルメイドな『イカとクジラ』とは異なり、明確なクライマックスが無く、主人公がラストに何の成長もしないという、アメリカ映画のルールを無視した実験的な作りがなされていた。 そこでのバームバックの冒険を支えていたのが、当時の妻で、主人公の妹役で出演もしていた女優のジェニファー・ジェイソン・リーだった。『初体験/リッジモント・ハイ』(82年、バームバックとの出会いには同作で共演したエリック・ストルツが関与していた可能性がある)以来、個性派女優として活躍を続ける彼女は、自ら監督と脚本もこなした『アニバーサリーの夜に』(01年)を発表したこともある才人である。『アニバーサリーの夜に』は、セットを一切使用せず、実際の家で起きた一夜の出来事をデジタルカメラでおさめた実験作だった。 また同作には、『初体験/リッジモント・ハイ』以来のリーの親友フィービー・ケイツが、夫のケヴィン・クラインと子ども二人を引き連れて久々に映画出演をしたことでも話題になったが、その子どものひとりこそ、後に『イカとクジラ』でジェシー・アイゼンバーグの弟役を演じたオーウェン・クラインなのだ。リーは『人生は最悪だ!』でもストーリー作りに関与しており、撮影は彼女の地元ロサンゼルスで行われている。彼女はそれほどまでに当時のバームバックに影響を与えていた。 同時にバームバックは、インディ映画界で勃興していた新しい流れからも影響を受けていた。それが<マンブル・コア>である。アンドリュー・ブジャルスキ、アーロン・カッツ、ジェイとマークのデュプラス兄弟といったこのムーヴメントを担う若い作家たちは、互いの作品に出演しあい、ヤマもオチもない日常をビデオカメラで切り取った超低予算映画をひっそりと、しかし大量に送り出していた。 ジョシュ・ハミルトンを通じてマンブル・コアの中心人物ジョー・スワンバーグと知り合ったバームバックは09年にスワンバーグ監督作『Alexander the Last』をプロデュースしており、『人生は最悪だ!』ではフローレンス役にマンブル・コア映画の代表的な女優だったグレタ・ガーウィグを抜擢している。『グリーンバーグ』は<中堅監督が敢えて挑んだ若い映画>だったのだ。 そんな作りでありながら、本作がコメディ映画としても成立しているのは邦題通り、ロジャーをミジメなシチュエーションだと最高におかしいベン・スティラーが演じているからだろう。スターである彼が低予算映画に出演したのは、生粋のニューヨーカーの彼がバームバックのセンスに共感したからだろう。事実、これ以降のスティラーは声優を務めたアニメ『マダガスカル3』(12年)の脚本家にバームバックを推薦し、エディ・マーフィとの共演作『ペントハウス』(11年)でも自分の役のセリフのリライトをバームバックに依頼するなど彼に全幅の信頼を置いている。『イカとクジラ』の終盤ウォルトが訪れるのは、スティラーの人気シリーズ『ナイト・ミュージアム』で一躍有名になったニューヨークの自然史博物館。スティラーもここには少年時代に何度となく訪れたという。 スティラーが演じるロジャーのモデルはだから当然バームバック本人だ。劇中で彼が自動車免許を持っていないことが執拗にギャグにされているのは、バームバックもロサンゼルスに引っ越して当初は免許がなくて苦労したから。20代の時にメジャーデビュー寸前まで行きながら無職という設定も、もし『イカとクジラ』を撮れなかったらこうなっていただろうという平行宇宙の自分なのだろう。 そんな冴えないロジャーにフローレンスはなぜか惹かれてしまう。ロジャーも彼女に心を奪われながら、「年齢が違いすぎる。僕の恋人になるのは十代の子どもを持つ疲れた中年女だ」と前に踏み出すことを拒もうとする。 映画はふたりに何かが起きる寸前に終わってしまうけど、僕らはその後に起きたことを知っている。ロジャー=バームバックとフローレンス=グレタは恋に落ちてしまったのだ。バームバックはグレタを連れてニューヨークへと戻り、喜びと疾走感に溢れたグレタ主演作『フランシス・ハ』(12年)を発表する。その翌年にバームバックはリーと離婚している。 その後もバームバックはニューヨークを拠点に、グレタやスティラーと組んで快作を発表し続けているけど、倦怠感と孤独の中から何かが生まれる瞬間をとらえた『人生は最悪だ!』は彼のフィルモグラフィに残る異色作としていつまでも残り続けることだろう。なお本作、終盤のパーティ・シーンにブレイク前のブリー・ラーソン、ジュノー・テンプル、デイヴ・フランコ、ゾーシャ・マメットらが出演しているので、目をこらして探してほしい。 © 2009 Focus Features LLC. All Rights Reserved.
-

NEWS/ニュース2017.01.27
世界中が待ち望んだ!『チェイサー』『哀しき獣』のナ・ホンジン監督、最新作。3月11日(土)公開『哭声/コクソン』の日本最速!ティーチイン付きプレミア上映会レポート!!
5年3ヶ月ぶりの来日となるナ・ホンジン監督と、日本を代表する俳優であり、本作では「よそ者」という謎の男で作品を引っ張る國村隼さんのQ&Aのコーナーを(ほぼ)全文レポートさせて頂きます! ※ネタバレを含む部分があります!該当部分には警告がございますので 注意の上ご一読頂ければ幸いです!! ザ・シネマでは3月、ナ・ホンジン監督の過去作『哀しき獣』と『哭声/コクソン』でもその演技で深い印象を残す、韓国映画界の大スター、ファン・ジョンミンが人気を不動のものにした『新しき世界』を特集放送。『哭声/コクソン』公開連動特集もお見逃しなく! 司会:では、ナ・ホンジン監督、5年3か月ぶりの来日となります。國村さんもいらっしゃっています。さっそくお呼びしようと思います。『哭声/コクソン』から、國村隼さん、そしてナ・ホンジン監督です。拍手でお迎えください。 ではまず、お二人にご挨拶を頂戴したいと思います。まず國村さんからお願いします。 國村隼(以下、國村):こんばんは。今日は本当にありがとうございます。映画をご覧になった後のお客さんの前に出てくると、ほんとにちょっとドキドキしますが、ちょっとホッとしました(笑)。この日本で、一番最初にこの『哭声/コクソン』をご覧になって下さった皆さんです。本当にもう嬉しくて、嬉しくて、皆さんお一人お一人をハグしたい気がします。今日は本当にありがとうございます! ナ・ホンジン監督(以下、監督):こんばんは、ナ・ホンジンです。お会いできて嬉しいです。足を運んで頂き誠にありがとうございます。映画の上映時間が結構長かったと思うのですが、お待ち頂き本当にありがとうございます。トイレとかは大丈夫でしょうか(笑)? シナリオから6年くらいをかけて作った映画なのですが、皆さんにお見せできるこの時間を迎える事ができて、本当に嬉しく思います。この後のQ&Aの時間もベストを尽くして挑みますので、よろしくお願い致します。 司会:ありがとうございます。では、お二人には(椅子に)おかけ頂いてお答えいただこうと思います。今日は立ち見のお客様もいらっしゃいます。ではさっそくいきましょうか。すでにリドリー・スコット監督の製作会社からリメイクのオファーが入ったとの事ですが、韓国サイドの代表の方が「この題材を撮れるのはナ・ホンジン以外いない」と明言されたとお聞きしました。もし、監督にハリウッドからリメイクのオファーが来たら、もう一度本作を撮ろうと思われますか?その場合、また國村さんを起用されますでしょうか?また、國村さんはハリウッドからリメイクのオファーがもし入ったらどうされますか? 監督:スコット・フリー(スコット・フリー・プロダクションズ※リドリー・スコットの製作会社)から連絡があったという事は聞きました。でも、対応の方が「演出できるのはナ・ホンジンしかいない」と冗談半分で言ったのだと思います。でも自分に要請が来たとしても、リメイク版を演出するつもりはありません。でも隼さんはこの映画に重要な方なので、必ず必要になると思います。ですのでオススメしたいと思います(笑)。 國村:あの…。オススメされてもやはり、ナ・ホンジンがメガホンを取らないのであれば、私もやることは多分ないんじゃないかと思います(笑)。 監督:では両方ともしないということにします(笑)。 司会:ここでやんわりお断わりが入りましたね(笑)。これまでのナ・ホンジン監督の過去作『チェイサー』や『哀しき獣』は、どちらかというと社会派サスペンスの様な作品だったと思いますが、本作はどちらかというと、ちょっと表現しにくいのですが「オカルト」の様な印象です。どちら(の作風)が監督が嗜好されていた作品、作りたいと思うものだったのでしょうか?教えて頂きたいと思います。監督:この『哭声/コクソン』という映画は、前2作を撮った後に、もう少し自分らしく、自由に、やりたい様に作りたいという意欲が昂ぶった時に作った作品なので、自分のスタイルのままに作った、ありのままに作った、よりやりたいものに近い作品だと思います。 司会:今回、監督が國村さんを起用された理由は何でしょうか?日本では非常にベテランの俳優さんで、悪役から非常に良い方の役まで演じてらっしゃいますが、一番の決め手は何だったのでしょうか?それと國村さんは、ナ・ホンジン監督の現場で一番印象に残っている事はなんでしょうか? 監督:シナリオが出来上がった時に、日本人の俳優が必要だということになり、國村さんと同年代の俳優さんを沢山調べました。既に國村さんという存在を存じ上げておりましたし、ずっと尊敬し続けていた俳優さんであったのですが、(探す過程で國村さんの)全作品を集中して見続けているうちに、ある特徴に気づきました。それはカットごとに自分の演技だけで既に編集され尽くされている様な演技をされるなぁという事でした。カットの中で、自由に演技をされているところが、とても素晴らしいと思ったのです。 で、この『哭声/コクソン』の中で、(國村さん演じる)「よそ者」という役は、お客さんに「この人物ってどういう存在なんだ?」という疑問を投げかける、とても重要な存在なんですね。その役をやり遂げるのはやはり隼さんしかいない、國村さんしかいないという確信を持って、日本に来てオファーをさせて頂きました。 國村:最初にオファーを頂いて、彼の前作『チェイサー』と『哀しき獣』そしてもちろん(本作の)脚本を読ませて頂き、もうその段階で「このナ・ホンジンという人はとんでもない才能だな」と実感していました。いざ、現場に入り一緒に撮影をしていく中で、最初に思っていた以上に「この人はもう才能のカタマリがそのまま人の形をしている様な人だな」と感じました。 というのは、現場でテイクを撮っていくんですが、この人はなかなか終わらないんです。1つテイクをとり終わった後、最初の基本のビジョンから新たにどんどんイメージが湧いていくタイプの方で、その自分の中で膨らむイメージを、「もっともっと」と、テイクを重ねる、という様な事がありました。 ただ、むやみやたらに重ねるのではないんです。自分の中のイメージの膨らみ、その膨らみこそがすごい才能だと思います。それを現場で目の当たりにして、やっぱり想像以上にすごい人だと、そういう風に思いました。 昨年、ソウルで『哭声/コクソン』を観させて頂きました。朝一で観たんですが、その日一日ブルーな気持ちになってしまいました(笑)。方言が難しくてあまり理解ができていなかったのですが、今日改めて拝見してさらにブルーになりました(笑) 司会:私は、ファン・ジョンミンさんのファンなのですが、國村さんは、現場でどの様なお話しをされましたでしょうか?何かエピソードがあれば教えて頂きたいです。 國村:ファンさんとは、画面の上でやり合ったりする事はなかったので、撮影の現場を一緒に過ごした事はあまりないのですが、その少ない中でも、彼はやっぱり、韓国の役者さんってみんなそうなんですが、映画の世界に来るまでにものすごく色々なスキルを重ねてらっしゃる。彼もまた、学生時代に演劇というものを始めて、それからこの世界に入り、映画の世界に行くまで様々な経験を重ねてらっしゃった様です。だから当然のごとく、経済的にもとても苦労した、という様な話しを、「ああ、なんかその辺は日本の役者の事情と非常に似ていて面白いな。一緒なんだな。」と思って。もちろんファンでいらっしゃるので、ご存知だと思いますが、韓国の大スターでらっしゃいます。けれども全然驕るところのない方で、本当に色々なキャラクターを演じられます。今回の役も明らかですが、どこかにファンさん自身の、物事に対する真摯な人柄みたいなものがちょこっ、ちょこっと出てくる。そのまんまの人です。あの人は。はい。 司会:ナ・ホンジン監督は、キャスティングに関して何か基準があれば教えて頂きたいと思います。 監督:一番その役にふさわしい(正しい)という役者さんを選びます。(出演する)それぞれの俳優さん達のバランスというのも一番注意する部分の1つです。それぐらいが自分の原則と言えるところです。 先ほどのファン・ジョンミンさんのエピソードに関して補足を入れさせて頂きますが、國村さんとファン・ジョンミンさんが映画の中で実際会うシーンは「ない」と言っても過言ではありません。もともとワンシーンだけ二人が会うシーンがあったのですが、それすら自分が編集の過程でカットしたので、映画の中で二人が会うシーンは無かったと思います。 司会:キム・ヨンソク(『チェイサー』主演)さんが、「甲板の上から飛び込みさせられたが、そのシーンがあまり映っていなかった」という様な事をおっしゃっていましたが、監督は國村さんの事をソンセンニム(先生)とお呼びになるほど尊敬されていらっしゃる様です。目上の方に結構無理な事をお願いするのは大変じゃなかったのかな?と思いました(笑)。韓国では年上の方に敬意を払われるので、裸にしてしまったり、結構いろんな事を、國村さんにさせてらっしゃるので(笑)。國村さんもそういう大変なシーンについては、どの様に思われているか教えて下さい(笑)。 監督:本当に申し訳なかったと思っております(笑)。ただ、シナリオがそういう風に出来上がっていたので、自分としてもどうしようもなかった、というほかありません。大変な思いをされるシーンが多かったことについては、撮影以外のところでなんとかケアをする為に、最善を尽くしたつもりであります。自分なりに頑張りました(笑)。今でも申し訳なかったと思っています。もしこの映画が日本で良い成績を残せなかったら、自分自身になんと言ったらよいかわかりませんが、良い結果を残せたらいいなと思っております。撮影を通して、沢山の事を、國村さんから学び、驚き、感嘆する事が多くありました。またそういった撮影の過程を通して、さらに尊敬し、大好きになりました。謝罪と感謝の気持ちをこの場でまた、述べさせて頂きたいと思います。 國村:なんか気恥ずかしいですね(笑)。 私もまさに監督が今おっしゃった様に、台本の中でもう、「こういう事をしなければいけない」という事が予め分かっていたので、それを理解した上でオファーを受けました。ただ一番引っかかったのは、「あれ?俺、ひょとして、このカメラの前ですっぽんぽんになることなんて出来るのかな?」という事でしたが、「この『哭声/コクソン』という作品の世界観はすごいな、そして、この男の役を僕以外の人がやっているのを見たくないな」、という気持ちが正直なところで、「観客の皆さんのご迷惑になる様なものを晒す事になっても、やってみよう」と思った次第です。ですから、監督に「ひどいことをさせられてる!」という意識は全くありませんでした。あくまで自覚的にその世界に自分から飛び込んだということです。 司会:韓国で賞もとられて、テレビで観ていてとても嬉しかったです!これからもご活躍をお祈りしております! 國村:ありがとうございます。 <場内拍手> 司会:ちなみに個人的にお聞きしたいのですが、ふんどし…姿じゃないですか? 國村:あ、言い忘れました!最初の脚本はすっぽんぽんだったんです! 司会:発案は國村さんからされたんですか? 國村:いえいえ。やっぱり韓国にも映倫に相当する様な組織があるらしく、やっぱりそらーまずかろうという(笑)それで「日本でいったらなんだ?」という事で、「そらふんどしだろう」と。劇中で、あるおじさんが「おむつ」って言ってますけど、多分見まがうという事もあったんでしょうね(笑) 司会:それじゃあ、日本で言ったら「ふんどし」だろうということで、あのセリフも付け加えられたんでしょうね。 司会:素晴らしい映画を有難うございました。監督に質問なんですが、この映画は観る側の想像に委ねる部分が沢山あると思います。監督の中で、國村さんが演じられた役については、細かい設定等は考えてあるのでしょうか?また、國村さんに質問なのですが、今回の役について、國村さんなりの解釈や背景は設定されて役作りをされたのでしょうか? 監督:映画を通して(國村さん演じる)「よそ者」はずっと観客に質問を投げかけ続ける立場にあります。これは映画そのものが観客に質問を投げかけるという設定なんですが、映画を観終えた方にもまだなお「「よそ者」をどう思いますか?」とずっと質問を投げかけ続ける映画であります。この「よそ者」というキャラクターはとても重要なのですが、その理由として、劇中の他の登場人物たちの「よそ者」に対する考えがどんどんどんどん変わってくるんです。「よそ者」に対するイメージが固まらない。まとまらないものが、まとまりつつある映画なんですが、その解釈が一人一人違うんですね。だから、「たった一つの解釈で定義するものではない」というのがこの映画の特徴であります。なので、自分自身もキャラクターを一言で定義することはできません。観客の皆さんがどんな解釈をしていようが、全ての解釈が合っていると、自分は思っています。この映画は観客の皆さんが自分で整理して完成させる。そういう映画であることを期待しております。 國村:「その男」をやるにあたって私が考えた事を申し上げます。良く言われる「役作り」という様なアプローチは機能しない、もっと言えばご覧になってわかる様に、 ※※ここからネタバレを含みますので、本編をご覧になる前の方は絶対にお読みにならないで下さい!!※※ あれは実在するものでないかもしれない。つまり、人でもなければ、何かのエネルギー体なのか、本当に存在するのか?確かな事は、「この男を見た」という奴の「噂」の中に、あの男がいるということです。最後、イサムという牧師の若者が、自分が見ている目の前の存在に、「お前はどう思う?」と逆に聞かれた時に、「お前は悪魔だ」と言った途端、すっとそこに悪魔として現れる。存在しているのかどうかもわからない、そういうイメージなんですね。ですから、その存在自体が本当に有るのかどうかも分からないものを、どう作ろう、なんてことは全く無理な話しであって、無理やり1つ何かを言葉を与え、自分の実感を伴ったイメージを与えようとした時に、このお話しの中で、あのキャラクターの「存在意義」というか「役割」というのは一体なんだろう?と。そこからアプローチした方がいいかなと思いました。 例えばですが、コクソンという片田舎の小さな町のコミュニティを池に例えて、そこにぽんっと放り込まれた、異物としての石ころ。その石ころが、ぽんっと池に投げ込まれる事によって起こる波紋。みたいなものだと。つまり無理やりに「(その男とは)なんだ?」と言われると、「池に投げ込まれる石」かもしれない。そんな事を注意しました。 司会:最後までドキドキする映画で、でもその中に笑いの要素もあり、そこが救いで良かったです。キャスティングも皆さん素晴らしかったですが、監督と國村さんから見た、現場でのチョン・ウヒさんの印象をお聞かせください。 國村:彼女も若いですが、舞台からの経験を積んで、素養をきっちりと身に付け、女優さんとして本当にクオリティが高いなと思いました。何より彼女は例えば「ムミョン」というキャラクターを自分がどういう風に捉えているかも含め、それをきちんと言葉にして喋る事ができる。やっぱり若いけどクオリティの高い女優さんである、というのが僕の印象です。 監督:たくさんの女優さんがオーディションを受けた中で、チョン・ウヒさんを選んだ理由というのは、彼女が最適な女優さんだからです。外部から見えるものではなく、その方が持つ『技』という面で、ものすごい力を感じました。私はこの役には「見せる力」があってほしいな、と思っていました。その理由としましては、2時間半の上映時間の中、全ての登場人物のバックグラウンドにあるものは「コクソン」という地名なんですが、その「コクソン」という地域の中に存在する、「神」というものを直接描写することはしなかったんです。しかし、観客に、無意識的に「神」という存在を感じさせる様な描写をしたかった。「神」を描写する手段としては、BGMや後ろの背景、時間や天気の変化を通して、観客にも届くのではないかと思っていました。チョン・ウヒさんを通して皆さんに伝えたかったんです。出演の場面もセリフも少ないのですが、映画の緊張を持続させる力がある役者が必要だと思っていたので、彼女を選びました。また現場では、すごくかわいらしい、妹の様な存在で、映画をご覧になった方はお分かりになると思いますが、期待以上にパワフルな演技をして下さいました。 司会:監督がなぜキャスティングも含めて、天気にそんなにこだわっていたのか、今の答えでもわかりました。「神」を感じさせるという。お時間の方が来てしまいましたので、公開は3/11なのですが、最速で観て頂いた皆さんにご挨拶を頂ければと思います。 國村:今日は本当にいらしていただいてありがとうございます。ほんとは最初に聞こうと思っていたのですが、どうでした? <場内拍手> ああ、良かった!!楽しんで頂けたなら本当に良かったと思います!で、ここからはお願いでございます。この『哭声/コクソン』という映画は今までには無かった映画だと思います。カテゴライズできない映画。映画の新たな楽しみ方が、この『哭声/コクソン』だと思います。ぜひお友達にこういう体験をさせてみたい、と思った方はお友達とまた一緒に観に来て下さいね。今日はありがとうございました! 監督:監督としての未練というのはあると思うのですが、この『哭声/コクソン』を作り上げた後に、「一抹の未練もない!」と言い切れます。ナ・ホンジンという監督の全てを注ぎ込んだ、未練が残らない作品と言えます。どんな評価を皆さんから頂こうが、それを全部受け止める所存であります。そんなナ・ホンジンという監督が6年をかけて全てを注ぎ込んで作った映画なので、周りのお友達に、「こういう監督が6年もかかって作った映画」だとお伝え下さい。長い間ご一緒頂きありがとうございました! 司会:ということで、ナ・ホンジン監督、國村隼さん、もう一度大きな拍手でお見送り下さい。ありがとうございました!!数日前にこの作品拝見して、どこか喉につかえたものがあったのですが、皆さんの質問、そしてお二人の回答によって、半分くらいは自分の中で咀嚼できたかなと思いました。そんな映画体験をさせてくれる作品というのは、今の上映作品の中でも珍しいと思います。3月11日公開ですが、公開後も応援して頂ければ幸いです。本日はご来場本当にありがとうございました。気を付けてお帰り下さい。 <終了> ■ ■ ■ ■ ■ 監督:ナ・ホンジン出演:クァク・ドウォン、ファン・ジョンミン、國村隼、チョン・ウヒ2016年/韓国/シネマスコープ/DCP5.1ch/156分©2016 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION配給:クロックワークス 公式サイト:http://kokuson.com/公式Twitter:@ kokuson_movie公式Facebook:https://www.facebook.com/kokuson0311 2017年3月11日、シネマート新宿他にて公開
-
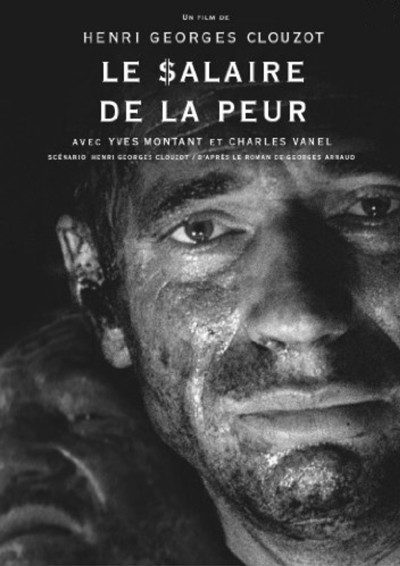
COLUMN/コラム2017.01.20
極限の緊張サスペンスに込めたクルーゾ監督の狙いと、それを継受した1977年リメイク版との関係性を紐解く〜『恐怖の報酬(1953)』〜01月10日(火)深夜ほか
わずかの振動でも爆発をおこす膨大な量のニトログリセリン(高度爆発性液体)を、悪路を眼下にトラックで輸送する--。それを耳にしただけでも、全身の毛が逆立つような身震いをもたらすのが、この『恐怖の報酬』だ。この映画が世に出て、今年で63年。その間、いったいどれほど多くの類似ドラマや引用、パロディが生み出されてきたことだろう。 だが一度は、それらを生み出したオリジンに触れてみるといい。先に挙げた設定をとことんまで活かした、観る者を極度の緊張へと至らしめる演出と仕掛けが、本作にはたっぷりと含まれている。 「この町に入るのは簡単さ。だが出るのは難しい“地獄の場所”だ」 アメリカの石油資源会社の介入によって搾取され、スラムと化した南米のとある貧民街。そこは行き場を失ったあぶれ者たちの、終着駅のごとき様相を呈していた。そんな“地獄の場所”へと流れてきたマリオ(イブ・モンタン)を筆頭とする四人の男たちは、貧困がぬかるみのように足をからめとる、この呪われた町から脱出するために高額報酬の仕事に挑む。その仕事とは、爆風で火を消すためのニトログリセリンを、大火災が猛威をふるう山向こうの石油採掘坑までトラックで運ぶことだった。 舗装されていないデコボコの悪路はもとより、道をふさぐ落石や噴油のたまった沼など、彼らの行く手には数々の難関が待ち受ける。果たしてマリオたちは無事に荷物を受け渡し、成功報酬を得ることができるのかーー? 仏作家ジョルジュ・アルノーによって書かれた原作小説は、南米グァテマラの油田地帯にある石油採掘坑の爆発と、その消火作業の模様を克明に描いた冒頭から始まる。その後は、 「四人が同じ地に集まる」 「ニトログリセリンを運ぶ」 と続く[三幕構成]となっているが、監督のアンリ・ジョルジュ・クルーゾはその構成を独自に解体。映画は四人の男たちの生きざまに密着した前半部と、彼らがトラックで地獄の道行へと向かう後半の[二部構成]へと配置換えをしている。そのため、本作が爆薬輸送の物語だという核心に触れるまで、およそ1時間に及ぶ環境描写を展開していくこととなる。 しかし、この構成変更こそが、物語をどこへ向かわせるのか分からぬサスペンス性を強調し、加えて悠然とした前半部のテンポが、どん詰まりの人生に焦りを覚える男たちの感情を、観る者に共有させていくのだ。 そしてなにより、視点を火災に見舞われた石油資源会社ではなく、石油採掘の犠牲となった町やそこに住む人々に置くことで、映画はアメリカ資本主義の搾取構造や、極限状態におけるむき出しの人間性を浮き彫りにしていくのである。 ■失われた17分間の復活 だが不幸なことに、クルーゾによるこの巧みな構成が、フランスでの公開から36年間も損なわれていた時代があったのだ。 今回ザ・シネマで放送される『恐怖の報酬』は、クルーゾ監督の意向に忠実な2時間28分のオリジナルバージョン(以下「クルーゾ版」と呼称)で、前章で触れた要素が欠けることなく含まれている。 しかし本作が各国で公開されたときにはカットされ、短く縮められてしまったのだ(以下、同バージョンを「短縮版」と呼称)。 映画に造詣の深いイラストレーター/監督の和田誠氏は、脚本家・三谷幸喜氏との連載対談「それはまた別の話」(「キネマ旬報」1997年3月01日号)での文中、封切りで『恐怖の報酬』を観たときには既にカットされていたと語り、 「たぶん観客が退屈するだろうという、輸入会社の配慮だと思うんですけど」 と、短縮版が作られた背景を推察している。確かに当時、上映の回転率が悪い長時間の洋画は、国内の映画配給会社の判断によって短くされるケースもあった。事実、本作の国内試写を観た成瀬巳喜男(『浮雲』(55)監督)が、中村登(『古都』(63)監督)や清水千代太(映画評論家)らと鼎談した記事「食いついて離さぬ執拗さ アンリ・ジョルジュ・クルゾオ作品 恐怖の報酬を語る」(「キネマ旬報」1954年89通号)の中で、試写で観た同作の長さは2時間20分であり、この時点でクルーゾ版より8分短かったという事実に触れている。 しかし本作の場合、短縮版が世界レベルで広まった起因は別のところにあったのだ。 1955年、『恐怖の報酬』はアメリカの映画評論家によって、劇中描写がアメリカに対して批判的だと指摘を受けた(同年の米「TIME」誌には「これまでに作られた作品で、最も反米色が濃い」とまで記されている)。そこでアメリカ市場での公開に際し、米映画の検閲機関が反米を匂わすショットやセリフを含むシーンの約17分、計11か所を削除したのである。それらは主に前半部に集中しており、たとえば石油の採掘事故で夫を亡くした未亡人が大勢の住民たちの前で、 「危険な仕事を回され。私たちの身内からいつも犠牲者が出る。死んでも連中(石油資源会社)は、はした金でケリをつける」 と訴えるシーン(本編37分経過時点)や、石油資源会社の支配人オブライエン(ウィリアム・タッブス)が、死亡事故調査のために安全委員会が来るという連絡を受けて、 「連中(安全委員会)を飲み食いさせて、悪いのは犠牲者だと言え。死人に口なしだ」 と部下に命じるシーン(本編39分経過時点)。さらにはニトログリセリンを運ぶ任務を負った一人が、重圧から自殺をはかり「彼はオブライエンの最初の犠牲者だ」とマリオがつぶやく場面(本編45分経過時点)などがクルーゾ版からカットされている。 こうした経緯のもとに生み出された短縮版が、以降『恐怖の報酬』の標準仕様としてアメリカやドイツなどの各国で公開されていったのである。 なので、この短縮版に慣れ親しんだ者が今回のクルーゾ版に触れると「長すぎるのでは?」と捉えてしまう傾向にあるようだ。それはそれで評価の在り方のひとつではあるが、何よりもこれらのカットによって作品のメッセージ性は薄められ、この映画にとっては大きな痛手となった。本作は決してスリルのみを追求したライド型アクションではない。社会の不平等に対する怒りを湛えた、そんな深みのある人間ドラマをクルーゾ監督は目指したのである。 1991年、マニアックな作品選定と凝った仕様のソフト制作で定評のある米ボイジャー社「クライテリオン・コレクション」レーベルが、本作のレーザーディスクをリリースするにあたり、先述のカットされた17分を差し戻す復元をほどこした。そしてようやく同作は、本来のあるべき姿を取り戻すことに成功したのである。この偉業によってクルーゾの意図は明瞭になり、以降、このクルーゾ版が再映、あるいはビデオソフトや放送において広められ、『恐怖の報酬』は正当な評価を取り戻していく。 ■クルーゾ版の正当性を証明するフリードキン版 こうしたクルーゾ版の正当性を主張するさい、カット問題と共に大きく浮かび上がってくるのは、1977年にウィリアム・フリードキン監督が手がけた本作の米リメイク『恐怖の報酬』の存在である。 名作として評価の定まったオリジナルを受けての、リスクの高い挑戦。そして製作費2000万ドルに対して全米配収が900万ドルしか得られなかったことから、一般的には失敗作という烙印を捺されている本作。しかし現在の観点から見直してみると、クルーゾ版を語るうえで重要性を放つことがわかる。 フリードキンは米アカデミー賞作品賞と監督賞を受賞した刑事ドラマ『フレンチ・コネクション』(71)、そして空前の大ヒットを記録したオカルトホラー『エクソシスト』(73)を手がけた後、『恐怖の報酬』の再映画化に着手した。その経緯は自らの半生をつづった伝記“THE FRIEDKIN CONNECTION”の中で語られている。 フリードキンは先の二本の成功を担保に、当時ユニバーサル社長であったルー・ワッサーマンに会い「わたしが撮る初のユニバーサル映画は本作だ」とアピールし、映画化権の取得にあたらせたのだ。 しかし権利はクルーゾではなく、原作者であるアルノー側が管理しており、しかも双方は権利をめぐって確執した状態にあった。だがフリードキン自身は「権利はアルノーにあっても、敬意を払うべきはクルーゾだ」と考え、彼に会って再映画化の支えを得ようとしたのだ。クルーゾは気鋭の若手が自作に新たな魂を吹き込むことを祝福し、『フレンチ・コネクション』『エクソシスト』という二つの傑作をモノした新人にリメイクを委ねたのである。 こうしたクルーゾとフリードキンとの親密性は、作品においても顕著にあらわれている。たとえば映画の構成に関して、フリードキンはマリオに相当する主人公シャッキー(ロイ・シャイダー)が、ニトログリセリンを輸送する任務を請け負わざるを得なくなる、そんな背景を執拗なまでに描写し、クルーゾ版の韻を踏んでいる。状況を打破するには、命と引き換えの仕事しかないーー。そんな男たちの姿をクローズアップにすることで、おのずとクルーゾーの作劇法を肯定しているのだ。 しかしラストに関して、フリードキンの『恐怖の報酬』は、シャッキーが無事にニトログリセリンを受け渡すところでエンドとなっていた。そのため本作は日本公開時、このクルーゾ版とも原作とも異なる結末を「安易なオチ」と受け取られ、不評を招く一因となったのである。 ところがこの結末は、本作の全米興行が惨敗に終わったため、代理店によってフリードキンの承認なく1時間31分にカットされた「インターナショナル版」の特性だったのだ。アメリカで公開された2時間2分の全長版は、クルーゾ版ならびに原作と同様、アレンジした形ではあるがバッドエンドを描いていた。にもかかわらず場面カットの憂き目に遭い、あらぬ誤解を受けてしまったのである。 そう、皮肉なことにクルーゾもフリードキンも、改ざんによって意図を捻じ曲げられてしまうという不幸を、『恐怖の報酬』という同じ作品で味わうこととなってしまったのだ。 さいわいにもクルーゾ版は、こうして自らが意図した形へと修復され、本来あるべき姿と評価をも取り戻している。なので、クルーゾ版の正当性を証明するフリードキン版も、多くの人の目に触れ、正当な評価を採り戻してもらいたい。それを期待しているのは、決して筆者だけではないはずだ。■ ©1951 - TF1 INTERNATIONAL - PATHE RENN PRODUCTIONS - VERA FILM - MARCEAU CONCORDIA - GENERAL PRODUCTIONS
-
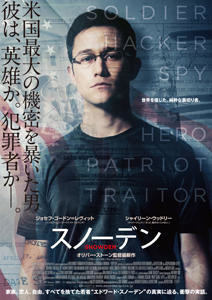
NEWS/ニュース2017.01.20
1月27日(金)公開最新作『スノーデン』。オリバー・ストーン監督来日記者会見レポート!
3年半ぶりの来日となるオリバー・ストーン監督のジャーナリスト精神に溢れ、この世界をより良いものにしたいという強い思いを感じる記者会見の模様を、(ほぼ)全文レポートさせて頂きます!監督の「スノーデン」という人物に対する深いリスペクトも感じる熱い会見となりました。 日時:2017年1月18日(水)会場:ザ・リッツ・カールトン東京司会:有村昆さん(以下:司会)通訳:大倉美子さん 司会:さてこれより1月27日の公開に先駆けまして、本作のプロモーションの為に来日中のオリバー・ストーン監督をお招きし、記者会見を行わせて頂きます。それでは皆様大きな拍手でお迎えください。オリバー・ストーン監督です。通訳は大倉美子さんです。よろしくお願い致します。 まずは、オリバー・ストーン監督からみなさんにご挨拶を頂戴したいと思います。 監督:今日は皆様、お集まり頂きありがとうございます。興味を持っていらして下さったと思うので、感謝しています。映画をご覧になった方は楽しんで頂けたら良かったのですが、そうでない場合はちょっとどう答えていいかわかりません。(笑) 今回、映画を携えての来日になりますので、なるべく映画の話し、あまり政治の話しにならない様になればいいなと思っていますが、基本的にはなんでもお答えしたいと思っております。どうぞよろしくお願い致します。 司会:ありがとうございます。それではまず私の方から代表して質問をさせて頂ければと思います。2013年に広島に1度訪れてらっしゃると思いますが、3年半ぶりの今回の来日、日本はいかがでしょうか? 監督:3年ぶりに訪れたという事ですが、変わっているかどうかはわかりません!だってこのホテルに詰め込まれてずっと取材だらけですから、過労死(カロウシと日本語で)状態です。日本にくるたびそうです! 司会:まさか、初めに出てきた日本語が「過労死」というのは驚きですね!それほど過密スケジュールとうい事ですが… 監督の過去作、『プラトーン』、『7月4日に生まれて』など、監督ご自身もベトナム戦争を体験されてそれを映画化されたり、アメリカ大統領を題材にされた『JFK』、『ニクソン』、『ブッシュ』などアメリカの国家そのものを描かれていると思うのですが、今回最新作では何故スノーデンをテーマにしようと思ったのかお聞かせください。 監督:まず僕自身、他のテーマにも興味がありますが、自分の時代(自分の生きた時代)に非常に興味を持って映画作りをしてきました。『オリバー・ストーンが語る もうひとつのアメリカ史』というシリーズを手掛けまして、そのプロモーションのために、最後に来日したわけですけれども、そのシリーズの中で、1890年から2013年の自国の歴史を扱ってきました。2013年というのはもちろん、オバマ大統領がリーダーとして監視社会を引っ張っている、その色合いを強めていた時代でした。その1月にこのシリーズをリリースし、その後、6月にエドワード・スノーデンが突然、あの様な形で告発を行ったわけです。 我々は『オリバー・ストーンが語る もうひとつのアメリカ史』の10章目で「監視社会」というテーマを扱っており、まさにテーマ通り「そうなのだ」と感じさせられたニュースが世界中の耳に届く事になりました。 驚いたことに、たまたま縁があって彼の物語を映画化することになりましたが、僕自身、スノーデンの告発に対しては素晴らしいと、拍手喝采しておりました。が、映画にしようという興味は全くなかったんです。 もともと作家として、ニュースを追いかけようというスタンスはありません。なぜならニュースというのはどんどん内容が変わっていくものですし、映画製作というのは時間がかかるものだからです。ただ、偶々、2014年の1月に、スノーデン氏の人権派弁護士の方から連絡を頂き、モスクワの彼に会いに来てくれないかと誘われ、2年間で9回に渡って彼に会う機会がありました。その中で、スノーデンの視点から語られる、彼の物語を映画にしよう、という気持ちにだんだんなっていった、というわけです。 司会:ここからマスコミの方からの質疑応答にうつらせていただこうと思います。 IWJ岩上安身編集長:3年半前に来日された時に、監督にお話しを伺った事があります。このスノーデンという作品には、日本に関わる重要なくだりがあります。スノーデンが横田基地に居た時の事を回想するシーンなんですが、アメリカの機関が日本に対する監視を実行し、日本の通信システムの次には、インフラも乗っ取り、ひそかにマルウェアを送電網やダムや病院にもしかけている。もし日本が同盟国でなくなった日には、日本は終わりだ、と証言するくだりがあります。 大変ショッキングで、スノーデンの告発は事実に基づいていると思います。このスノーデンの告白の後、監督は日本列島から電気が全部消えていくシーンを挿入されていますが、もしこのマルウェアがあらゆるインフラに仕掛けられ、そして作動すると日本のインフラの電源が失わることになります。もしこれが原発にしかけられていた場合、全電源喪失が行われる、ということも意味します。 このスノーデンの告発というのは、どの程度事実なのでしょうか?また、映画にするために非常に短くされたと思いますが、彼からどの様な事を聞いていますでしょうか? これこそは同盟国でなくなった途端、サイバー攻撃を仕掛けるという米国からの脅しと、我々日本国民としては思うわけですが、事実か事実でないか、もちろん事実でないということはないと思いますが、どの程度事実なのか教えて頂ければと思います。 監督:今この部屋の中で、目覚めていらっしゃっている方がいる事を嬉しく思います。今まで、アメリカ、ヨーロッパでこの話しをいろいろしてきたのですが、こういう聞き方をしてくださった方は初めてです。しっかりと目をひらいてらっしゃる方がいて、とても嬉しく思います。 さきほど申し上げた様に、自分がこう思う、ということは(映画の中には)一切いれておりません。すべてスノーデンが自分に語ってくれた内容を映画化させてもらったということを申し上げさせてください。実際製作中に、NSAと全く話すことはできませんでした。唯一話せたのは(NSAの)PR局で、パンフレットを渡され、それでおしまいでした。 そんな中、映画を作ったわけですが、もし彼が言っている事が間違いであるならば、ぼく自身の経験値、そして今までの自分の心で感じた部分から言うと、彼は最も世界で素晴らしい役者だと言える、つまり、僕は彼が言っていることは全て真実だと考えています。そして、もちろん彼が僕らに話せなかった事というものもあります。それは起訴につながってしまう様な事、そういった部分は映画にしていません。ドキュメンタリーではなく、ドラマ化している作品ですので、話せない内容に呼応する様なパラレルな出来事、という描き方をしています。 そして横田基地にいた2010年くらいの話しに戻りますが、彼自身から僕が聞いたのは、アメリカが日本中を監視したいと日本の諜報機関に申し出ましたが、日本側が「それは違法であるし、倫理的にもいかがなものか」ということで拒否した。しかし構わず監視をした。そしてご指摘があった様に、同盟国でなくなった途端にインフラをすべて落とすことができる様に、民間のインフラにマルウェアを仕込んである、という風なことです。 言及されていました核施設に関しては、彼自身の言葉で僕は聞いていないのですが、僕自身の勝手な考えでは、きっと核施設に関してはまた違った形(の監視体制)をとったのではないかなぁ、と思います。 スノーデンが言っていたのですが、日本のみならず、メキシコ、ブラジル、オーストリア、これは定かではありませんが、イギリスもと、言ってた気がします。その国々も、同じ様なことがされている。これはいわばサイバー戦争ですよね。 しかもそれがすでに仕掛けられていて、そもそもの発端は2007年から2008年頃から、イランにマルウェアを仕込んだ事から始まります。2010年くらいにこれが成功し、イランのいくつかの核施設にウィルスを送り込む事に成功しました。ですがその数か月後にはあのウィルスがそこから中東に、そして世界へと広がっていきました。 当時の諜報機関のトップの方にいた、マイケル・ヘーデン氏がこの事を公言してしまったんですね。「イランという敵をこういう形でやり込める事が出来て良かった」という様な趣旨の事をちょっとにやにやしながら。この時のウィルスは、スタックスネット(stuxnet)というウィルスなのですが、イスラエルとアメリカがイランに仕掛けたものです。非常に醜い物語です。 そしてこのウィルスが発端となって、世界中が「ウィルス攻撃できるんだ」と、サイバー戦争というものが始まっていった。そもそも戦線布告なしに、イランに(ウィルスを)仕掛けたことがサイバー戦争に突入した行為と同義だと、これはすごい事だと思っています。 今、フェイクニュース(偽のニュース)が沢山、特にサイバー関係では流れてきます。特にアメリカから発信されるニュースというのは、皆さんも少し疑いの気持ちをもって見て頂きたいんですね。サイバー戦争に関して言えば、アメリカがリーダーなわけですから。大きなプログラムを持っているのもアメリカです。当然そこから出てくる、ロシア関係がどうだの、攻撃されただの、もちろん証拠があるものもありますが(中国の民間企業への監視など)ほとんどのものには証拠がなく、勝手に出て来ているニュースです。 そういったすべての事に、スノーデンは我々が注目するきっかけを作ってくれました。しかし、サイバー戦争の実態というのは表面しか判っていません。これは新しい戦争ですし、僕にとっては1945年に原子爆弾が日本に落とされた事も、また新しい戦争の始まりだったといます。「サイバー戦争」は新しい戦争の形であり、それはすでに始まっています。それが、この映画に描かれている、世界に対する監視システムの体制というものと共に、確かに存在することを知って頂きたいのです。 そしてもう1つだけ。法的な定義を鑑みても、今行われているサイバー攻撃的なものは、戦争行為だと思います。先ほど同盟国のことに関して質問して頂きましたが、アメリカにとって日本は同盟国ではありません。人質になっている、いう風に僕は考えています。もし日本が、中国でもいいですし、他の経済圏と協力関係を持とうとし、そしてこの同盟関係から離れようとした場合、脅迫されたり、この(仕込まれた)マルウェアなどが人質になる、そういう非常にシリアスな問題だと受け止めて頂きたいのです。 僕が見たいのは、一人でも多くの日本のジャーナリストが防衛相に行って「これは本当なのか?」と聞いて頂くこと。(笑みを浮かべながら)どう答えられるかはわかりません。もしかしたら「知らない」と否定するかもしれません。 もちろんアメリカの場合、NSAは否定します。スノーデン自体を「大したランクの人間ではなかったと」と言って、問題を小さくしようとしている事からもわかります。しかし彼は、これだけの膨大な情報を我々に提供しているわけですから、そんなことはないわけです。 これは日本だけではなく、マルウェアが仕込まれてると言われている全ての国、例えばメキシコ、ブラジル政府に対して、(ジャーナリストたちが)意見を求めるという事を、僕は見たいと望んでいます。ですが、アメリカでは一切ジャーナリストからこういった質問が出なかったことに、むしろ驚いています。こういった問題に対するアカウンタビリティー(説明責任)が一切ないということが、世界の大きな問題の1つだと思います。 司会:とういことで、サイバー戦争はすでに水面下で行われているとうい事実を語っていただきました。 スターチャンネル・加藤氏:主演のジョゼフ・ゴードン=レヴィットはとてもハマリ役だと思いました。なぜ彼を選んだのでしょうか?ちなみに彼が出演を決めた理由は、監督があなた(ストーン監督)だからだそうです。 監督:2014年にスノーデン氏に会って、実はすぐにジョセフには連絡をしました。まだ脚本もない段階で「興味があるか?」と聞いたら、「すごく興味がある」と答えてくれました。モスクワにも連れて行って、実際にスノーデン氏に会ってももらいました。二人は同世代なんです。そしてジョセフはスノーデンに対して非常に敬服しているところがありました。スノーデンの動き、物腰、全て模倣する様な、そういった演技になっていたと思います。 この『スノーデン』という映画では、典型的な「オリバー・ストーン・ヒーロー」を描いていないよね、ということで批判も受けたんです。いわゆる、行動を起こす、アクティブな主人公が今まで多かったせいなのかもしれません。対してスノーデンは非常に受け身なところがありますし、物静かで非外交的、どちらかというと一歩引いた、口数が少ない方なんです。 そしてシャイリーン・ウッドリー演じるリンゼイさんですが、むしろ彼女の方が積極的に行動を起こすタイプです。なのでスノーデンはこの関係性においても非常に抑圧されているのかなというのが僕の印象でした。ですが、お互いに違うところを持っているからこそ惹かれ合い、特にずっと人を監視しなければならないという機関で仕事をしている方というのは、どんどん人間性が失われていくと僕は思うんですね。そんな中でもスノーデンが人間性を保つことができたのは、彼女の存在が大きいと思いました。 司会:ジョゼフ・ゴードン=レヴィットさんに対して、監督は演技指導はされたんでしょうか? 監督:ジョセフは非常に自分自身を律することができるタイプの役者さんです。ですから、自分で決めて演技をすることが出来ますし、非常に頑固なところもあります(笑)。 僕自身は役者との関係はいつも「ギブアンドテイク」そして「トライアルアンドエラー」といった感じで、戦いつつ、そこから何かが生まれてくる、という感じなんです。 今回の彼の演技は大絶賛をされましたし、非常に説得力があるものだったと思います。けれども派手さがそんなにないのは、ご本人のエドワードが自分のことを「インドア・キャット(室内猫)」とおっしゃっていることからもわかる様に、なんと一日の75%を、夜間、コンピューターの前で過ごしてらっしゃる。日本で言うとちょっと引きこもりに近いコンピューターオタク、でもあるからなんですね。 しかし、そんなスノーデンは、この監視社会に対する警鐘を止めてはいけないと、ロボットだったり、テレカンファレンス(遠隔会議)だったり、衛星電話を通じて、非常に饒舌に語り続けていますよね。 ENECT編集長・平井氏:重要な映画をありがとうございました。日本では、昨年4月に電力の自由化が実現しましたが、原発事故を起こした東電から電力を(購入を民間に)変えたのは、人口の5%以下という状況です。劇中、スノーデンの「僕は選択肢を市民に提示したかった」というセリフがあります。監視されるか、されないか、選択肢を委ねられた市民の反応はどんなものでしたか? 監督:そもそも「セキュリティー対プライバシー、あるいは自由」という等式が間違っている、と僕は考えているんですね。映画の中でも描いている大きな部分なのですが、それぞれの意識だったり、魂といったものをきちんと持つ事が重要で、それを大きな、例えば主役的な国家などに明け渡してはいけない、ということです。例えばNSAの様な存在に。ですから「選択肢を委ねられた~」という形で質問して下さいましたが、それは間違ったものであって、だってアメリカ自体はアメリカ国民に安全を与える事なんでできないんです。 今までもたくさんの失敗をしてきました。例えば、一番顕著なのが9.11です。 NSAはテロリストを把握していました。イエメンにあるセーフハウスも把握していました。また、通信も傍受していました。CIAもFBIもそれぞれ同様に情報を持っていました。そしてサンディエゴにテロリスト達が到着した時には、FBIがそのことを把握していながら、他の機関に連絡しなかったり、あるいはパイロットの訓練というのがアメリカ中で行われていましたけれども、CIAはそれを把握していて上にあげ、ワシントンにも伝えられていたのですが、官僚主義の穴に落ちてしまい、それがちゃんと他の機関に伝わる事がなかった。失敗という意味ではイラク戦争もそうです。大量の殺戮兵器があるという「情報」で動いたというのは周知の事実です。 もっと歴史を紐解けば、ケネディ大統領のピッグス湾の事件もそうです。また、ベトナム戦争も最初から最後までCIAが作り上げた情報によるものでした。諜報機関から間違った情報しか与え続けられていないにも関わらず、アメリカ国民は、未だにその諜報機関というものをすごく大切なものだと思っていて、最近で言うと、ロシアにハッキングされたという様な事を諜報機関が言っていますけれども、証拠が一切ないわけなんですね。これはアメリカに限らずですが、世界の諜報機関がちょっと政治的になりかけてしまっている。そんな風に思います。 ですから9.11の後、アメリカは何十億ドルも費やして、安全のための機関というのを増やしました。けれども安全性はより低くなってると思いますし、よりカオスが強まってきていると思います。ですからさっき申し上げた様に、セキュリティとフリーダム、安全と自由という等式というのがそもそも間違っている。だってそもそも与えられない様なものなのだから。しかし、セキュリティは正しい形で用いれば、(監視システムというものも)効果的だとも考えています。これはスノーデンの映画の中にも何度も登場しますし、彼も言っていることです。ターゲットを選択した方法での監視システムというのは有効だと思います。きちんとした疑いを持つ相手だけを監視し、ネットワークに目を光らせるという形。先ほどのターゲットを決めた監視体制(ターゲティッド・サベーランス)に対して、アメリカは、マスに向けた監視体制(マス・サーベランス)を行っているわけなんです。これは全員に対する監視システムだと考えて頂いて構いません。非常に巨大なものになりますが、今のテクノロジーでは可能です。しかしそのことによって、モンスターの様な国になっていきますし、悪夢の様な世界が生まれています。 これはすなわち、個人、企業、機関、銀行、世界中全ての情報がアメリカによって掌握されている、という事に他ならないわけです。何故かというと、こういったサイバー戦争において、アメリカが一番大きなシステムを持っていて、一番大きなお金を費やしているからです。当然一番多くの情報を手にしているわけです。これは非常に危険な事だと思います。個人のみならず、企業、国までも変えることができる。そういう力を持っているからです。そういった意味でも、国家を不安定にさせ、政権を変えさせるという様なことは、クリントン、オバマ政権下でも行われていました。 最近で言えば、ブラジルでのクーデター。あれも僕からすれば全くの作り事だと思います。様々な介入によって左派候補をつぶしてしまった。またブラジルに関して言えばアメリカは、長年に渡ってテトログラスという会社をずっと監視し続けています。また、ルセフ大統領の事ももちろん監視し続けてのあの結果であります。「ここまで」というリミットがない状況なんですね。ウクライナ、イラク、そしてリビアでは成功、シリアでは不成功でしたけれども、他の国においても、政権の交代をいろんな形で図ろうというアメリカがいます。そのことにより中東はよりカオスの状態に追い込まれ、アメリカがすべてをコントロールしようとするこの動きは、止められていない状況です。 また、ロシアにおける政権交代というのをアメリカは長年望んで、図ってはいますけれども、まだ叶ってはいません。こういう状況は非常に危険だと思います。 それに対してアメリカの言うことなんて聞かないよ、と言っているのが、例えば中国であったりロシアであったり、イランだったりするわけなんですが、アメリカはしかし「帝国」状態なわけです。しかしその独裁的な帝国というのは、カオスを産むだけ。世界をより危険なものにするだけです。このままではいけない、と僕は考えています。 昔、20世紀のヨーロッパの警察の活動を見るだけでも、きちんとテロ対策はできているわけですよ。ですから、非常に男性的な「アメリカン・マッチョ」みたいなやり方、例えば、他の国に軍隊を送り込めばいいんだ!という様な考えは間違っている、他のやり方があるのではないか、と考えています。 そして、最後になるかもしれませんが、この『スノーデン』という映画はアメリカ資本が一切入っていません。フランス、ドイツなど、スノーデンを非常にリスペクトして下さっている国からの出資で作られています。もちろん、アメリカのメジャースタジオさんにもお話しはしましたが、全て断られています。理由はわかりません。おそらく僕が思うに、自分達で自己検閲したか、または恐怖心を感じた、そいういうことだったのかもしれません。 アメリカでの配給も小さな配給会社Open Road Filmsさんが配給して下さることになりました。製作する事も、いろいろな国でお見せすることも大変困難な作品になってはいるんですが、日本ではショーゲートさんが配給して下さるということで非常に感謝しておりますし、日本の方にもぜひ観て頂き、この問題の巨大さ、複雑さをぜひ考えてみて頂きたいと考えています。 司会:多くの方にご覧頂きたい1本です! ※フォトセッション終了後、監督退場 司会:Thank you very much! ありがとうございました!オリバー・ストーン監督でした!今一度、大きな拍手をお送りくださいませ!『スノーデン』は、1月27日(金)からTOHOシネマズ、みゆき座他にて全国ロードショーとなります。<終了> ■ ■ ■ ■ ■ 監督:オリバー・ストーン 脚本:オリバー・ストーン、キーラン・フィッツジェラルド 原作:「スノーデンファイル 地球上で最も追われている男の真実」著 ルーク・ハーディング (日経BP社)出演:ジョセフ・ゴードン=レヴィット、シャイリーン・ウッドリー、メリッサ・レオ、ザカリー・クイント、トム・ウィルキンソン、リス・エヴァンス、ニコラス・ケイジ 2016年/アメリカ・ドイツ・フランス/原題:SNOWDEN 配給:ショウゲート 公式HP:www.snowden-movie.jp ©2016 SACHA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
-

COLUMN/コラム2017.01.14
個人的に熱烈推薦!編成部スタッフ1人1本レコメンド 【2017年2月】飯森盛良
シン・シティ1&2は短編集みたいな映画で、それぞれのエピソードはユルくつながってる。けど、時系列が映画も、原作コミックでさえもメチャクチャで、わかりづらい。そこで、時系列順で見るならこうだ!という懇切丁寧なガイドをここに発表! まず①1のブルース・ウィリス主役のエピソード前後編をセットで ↓②2のアバンタイトル、ミッキー・ロークがホームレス狩りしてる調子コイてる大学生どもをシバくくだり ↓③2のエヴァ・グリーンがファム・ファタル無双のノワールなお話 ↓④2のジョゼフ・ゴードン=レヴィット主役の前後編セット ↓⑤2ラストの、逆襲のジェシカ・アルバ ↓⑥1のミッキー・ロークが一発ヤラせてくれたマブい女の仇を討つお話 ↓⑦1のクライヴ・オーウェン主役エピソード と、いう順番なんです実は。これでもう安心ですね?2本丸ごと録画して、ぜひ2度目はこの順番で再生してみてください。当方で編集してこう流すと著作権侵害で訴えられそうなのでゴメン無理! ©2014 Maddartico Limited. All Rights Reserved.
-

COLUMN/コラム2016.12.29
極限の緊張サスペンスに込めたクルーゾ監督の狙いと、それを継受した1977年リメイク版との関係性を紐解く〜
わずかの振動でも爆発をおこす膨大な量のニトログリセリン(高度爆発性液体)を、悪路を眼下にトラックで輸送する--。それを耳にしただけでも、全身の毛が逆立つような身震いをもたらすのが、この『恐怖の報酬』だ。この映画が世に出て、今年で63年。その間、いったいどれほど多くの類似ドラマや引用、パロディが生み出されてきたことだろう。 だが一度は、それらを生み出したオリジンに触れてみるといい。先に挙げた設定をとことんまで活かした、観る者を極度の緊張へと至らしめる演出と仕掛けが、本作にはたっぷりと含まれている。 「この町に入るのは簡単さ。だが出るのは難しい“地獄の場所”だ」 アメリカの石油資源会社の介入によって搾取され、スラムと化した南米のとある貧民街。そこは行き場を失ったあぶれ者たちの、終着駅のごとき様相を呈していた。そんな“地獄の場所”へと流れてきたマリオ(イブ・モンタン)を筆頭とする四人の男たちは、貧困がぬかるみのように足をからめとる、この呪われた町から脱出するために高額報酬の仕事に挑む。その仕事とは、爆風で火を消すためのニトログリセリンを、大火災が猛威をふるう山向こうの石油採掘坑までトラックで運ぶことだった。 舗装されていないデコボコの悪路はもとより、道をふさぐ落石や噴油のたまった沼など、彼らの行く手には数々の難関が待ち受ける。果たしてマリオたちは無事に荷物を受け渡し、成功報酬を得ることができるのかーー? 仏作家ジョルジュ・アルノーによって書かれた原作小説は、南米グァテマラの油田地帯にある石油採掘坑の爆発と、その消火作業の模様を克明に描いた冒頭から始まる。その後は、 「四人が同じ地に集まる」「ニトログリセリンを運ぶ」 と続く[三幕構成]となっているが、監督のアンリ・ジョルジュ・クルーゾはその構成を独自に解体。映画は四人の男たちの生きざまに密着した前半部と、彼らがトラックで地獄の道行へと向かう後半の[二部構成]へと配置換えをしている。そのため、本作が爆薬輸送の物語だという核心に触れるまで、およそ1時間に及ぶ環境描写を展開していくこととなる。 しかし、この構成変更こそが、物語をどこへ向かわせるのか分からぬサスペンス性を強調し、加えて悠然とした前半部のテンポが、どん詰まりの人生に焦りを覚える男たちの感情を、観る者に共有させていくのだ。 そしてなにより、視点を火災に見舞われた石油資源会社ではなく、石油採掘の犠牲となった町やそこに住む人々に置くことで、映画はアメリカ資本主義の搾取構造や、極限状態におけるむき出しの人間性を浮き彫りにしていくのである。 ■失われた17分間の復活 だが不幸なことに、クルーゾによるこの巧みな構成が、フランスでの公開から36年間も損なわれていた時代があったのだ。 今回ザ・シネマで放送される『恐怖の報酬』は、クルーゾ監督の意向に忠実な2時間28分のオリジナルバージョン(以下「クルーゾ版」と呼称)で、前章で触れた要素が欠けることなく含まれている。 しかし本作が各国で公開されたときにはカットされ、短く縮められてしまったのだ(以下、同バージョンを「短縮版」と呼称)。 映画に造詣の深いイラストレーター/監督の和田誠氏は、脚本家・三谷幸喜氏との連載対談「それはまた別の話」(「キネマ旬報」1997年3月01日号)での文中、封切りで『恐怖の報酬』を観たときには既にカットされていたと語り、 「たぶん観客が退屈するだろうという、輸入会社の配慮だと思うんですけど」 と、短縮版が作られた背景を推察している。確かに当時、上映の回転率が悪い長時間の洋画は、国内の映画配給会社の判断によって短くされるケースもあった。事実、本作の国内試写を観た成瀬巳喜男(『浮雲』(55)監督)が、中村登(『古都』(63)監督)や清水千代太(映画評論家)らと鼎談した記事「食いついて離さぬ執拗さ アンリ・ジョルジュ・クルゾオ作品 恐怖の報酬を語る」(「キネマ旬報」1954年89通号)の中で、試写で観た同作の長さは2時間20分であり、この時点でクルーゾ版より8分短かったという事実に触れている。 しかし本作の場合、短縮版が世界レベルで広まった起因は別のところにあったのだ。 1955年、『恐怖の報酬』はアメリカの映画評論家によって、劇中描写がアメリカに対して批判的だと指摘を受けた(同年の米「TIME」誌には「これまでに作られた作品で、最も反米色が濃い」とまで記されている)。そこでアメリカ市場での公開に際し、米映画の検閲機関が反米を匂わすショットやセリフを含むシーンの約17分、計11か所を削除したのである。それらは主に前半部に集中しており、たとえば石油の採掘事故で夫を亡くした未亡人が大勢の住民たちの前で、 「危険な仕事を回され。私たちの身内からいつも犠牲者が出る。死んでも連中(石油資源会社)は、はした金でケリをつける」 と訴えるシーン(本編37分経過時点)や、石油資源会社の支配人オブライエン(ウィリアム・タッブス)が、死亡事故調査のために安全委員会が来るという連絡を受けて、 「連中(安全委員会)を飲み食いさせて、悪いのは犠牲者だと言え。死人に口なしだ」 と部下に命じるシーン(本編39分経過時点)。さらにはニトログリセリンを運ぶ任務を負った一人が、重圧から自殺をはかり「彼はオブライエンの最初の犠牲者だ」とマリオがつぶやく場面(本編45分経過時点)などがクルーゾ版からカットされている。 こうした経緯のもとに生み出された短縮版が、以降『恐怖の報酬』の標準仕様としてアメリカやドイツなどの各国で公開されていったのである。 なので、この短縮版に慣れ親しんだ者が今回のクルーゾ版に触れると「長すぎるのでは?」と捉えてしまう傾向にあるようだ。それはそれで評価の在り方のひとつではあるが、何よりもこれらのカットによって作品のメッセージ性は薄められ、この映画にとっては大きな痛手となった。本作は決してスリルのみを追求したライド型アクションではない。社会の不平等に対する怒りを湛えた、そんな深みのある人間ドラマをクルーゾ監督は目指したのである。 1991年、マニアックな作品選定と凝った仕様のソフト制作で定評のある米ボイジャー社「クライテリオン・コレクション」レーベルが、本作のレーザーディスクをリリースするにあたり、先述のカットされた17分を差し戻す復元をほどこした。そしてようやく同作は、本来のあるべき姿を取り戻すことに成功したのである。この偉業によってクルーゾの意図は明瞭になり、以降、このクルーゾ版が再映、あるいはビデオソフトや放送において広められ、『恐怖の報酬』は正当な評価を取り戻していく。 ■クルーゾ版の正当性を証明するフリードキン版 こうしたクルーゾ版の正当性を主張するさい、カット問題と共に大きく浮かび上がってくるのは、1977年にウィリアム・フリードキン監督が手がけた本作の米リメイク『恐怖の報酬』の存在である。 名作として評価の定まったオリジナルを受けての、リスクの高い挑戦。そして製作費2000万ドルに対して全米配収が900万ドルしか得られなかったことから、一般的には失敗作という烙印を捺されている本作。しかし現在の観点から見直してみると、クルーゾ版を語るうえで重要性を放つことがわかる。 フリードキンは米アカデミー賞作品賞と監督賞を受賞した刑事ドラマ『フレンチ・コネクション』(71)、そして空前の大ヒットを記録したオカルトホラー『エクソシスト』(73)を手がけた後、『恐怖の報酬』の再映画化に着手した。その経緯は自らの半生をつづった伝記“THE FRIEDKIN CONNECTION”の中で語られている。 フリードキンは先の二本の成功を担保に、当時ユニバーサル社長であったルー・ワッサーマンに会い「わたしが撮る初のユニバーサル映画は本作だ」とアピールし、映画化権の取得にあたらせたのだ。 しかし権利はクルーゾではなく、原作者であるアルノー側が管理しており、しかも双方は権利をめぐって確執した状態にあった。だがフリードキン自身は「権利はアルノーにあっても、敬意を払うべきはクルーゾだ」と考え、彼に会って再映画化の支えを得ようとしたのだ。クルーゾは気鋭の若手が自作に新たな魂を吹き込むことを祝福し、『フレンチ・コネクション』『エクソシスト』という二つの傑作をモノした新人にリメイクを委ねたのである。 こうしたクルーゾとフリードキンとの親密性は、作品においても顕著にあらわれている。たとえば映画の構成に関して、フリードキンはマリオに相当する主人公シャッキー(ロイ・シャイダー)が、ニトログリセリンを輸送する任務を請け負わざるを得なくなる、そんな背景を執拗なまでに描写し、クルーゾ版の韻を踏んでいる。状況を打破するには、命と引き換えの仕事しかないーー。そんな男たちの姿をクローズアップにすることで、おのずとクルーゾーの作劇法を肯定しているのだ。 しかしラストに関して、フリードキンの『恐怖の報酬』は、シャッキーが無事にニトログリセリンを受け渡すところでエンドとなっていた。そのため本作は日本公開時、このクルーゾ版とも原作とも異なる結末を「安易なオチ」と受け取られ、不評を招く一因となったのである。 ところがこの結末は、本作の全米興行が惨敗に終わったため、代理店によってフリードキンの承認なく1時間31分にカットされた「インターナショナル版」の特性だったのだ。アメリカで公開された2時間2分の全長版は、クルーゾ版ならびに原作と同様、アレンジした形ではあるがバッドエンドを描いていた。にもかかわらず場面カットの憂き目に遭い、あらぬ誤解を受けてしまったのである。 そう、皮肉なことにクルーゾもフリードキンも、改ざんによって意図を捻じ曲げられてしまうという不幸を、『恐怖の報酬』という同じ作品で味わうこととなってしまったのだ。 さいわいにもクルーゾ版は、こうして自らが意図した形へと修復され、本来あるべき姿と評価をも取り戻している。なので、クルーゾ版の正当性を証明するフリードキン版も、多くの人の目に触れ、正当な評価を採り戻してもらいたい。それを期待しているのは、決して筆者だけではないはずだ。■
-

COLUMN/コラム2016.12.17
ゾンビ映画ファンだけでなく、ゾンビ嫌いな人にも観て欲しい、2人の愛を見せつけられる秀作ドラマ『ゾンビ・リミット』
ちょうど1981年~1985年は、リターンドと名づけられた未知のウィルスが発見され、多数の死者を出した第1次流行期にあたる。そのウィルスの感染者はリターンドと呼ばれた。感染者が出血した場合、他者は決して血に触れてはならないし、感染者をそのまま放置すれば、数日後には意識を喪失し、生肉と血に飢えたゾンビのように凶暴性を発揮する。 これは現代史において人類最大の悲劇となり、現在まで世界中の犠牲者は1億人以上とされる。第1次流行期から治療を研究しはじめて10年後、リターンド(感染者)の髄液から採取した“リターンドたんぱく質”により大きな希望がもたらされた。そして第2次流行期以後は、多くの人を救うことができた。 でも全てのリターンドを完治できるわけではなく、感染後、36時間以内に薬“リターンドたんぱく質”を注射し、効果があらわれた者だけしか助からないし、助かった者も一生、薬をうち続けなければならない。国はリターンドに薬を配給し、患者を管理していた。 一方、リターンドへの反発は徐々に大きくなり、反リターンド派のみならず一般市民による差別やデモが相次ぎ、各地でリターンドが襲撃される暴行死傷事件が起きていた。そのため、リターンドは密かに暮らし、周囲にカミングアウトすることはなかった。 ゾンビのような凶暴化した人間を生み出す新種のウィルスに対する反応を、多少のシミュレーション風に描いたものでは、『28日後…』(02)の続編『28週後…』(07)が思いだされる。感染者の恐怖とそれに対する社会(世界)の対応が描写されていたが、見せ場のメインは、ゾンビのような感染者が人間に襲いかかる光景だった。 でも『ゾンビ・リミット』では、未知のウィルスに感染したリターンドが徐々に増殖してゆき、それに対する社会と人間たちの様々な反応を描いたドラマであって、ゾンビのように凶暴化したリターンドが人間に襲いかかる描写はほんのわずかしかない。だから、そのテの凄惨な残酷描写を期待するファンにとっては、最初は肩すかしを喰らった感があるかもしれないが、それでも徐々に見応えある作品世界に没入してゆくハズ。 ゾンビ映画をリスペクトしつつも、ゾンビ映画の見どころの一つ、感染者の人間襲撃場面を極力排している。でも筆者は、それでも本作が大好き。愛すべき作品である。しかしこの邦題は、あまり好きじゃない。原題は“THE RETURNED”で、未知のウィルス名、およびその感染者を指すが、RETURNEDだけなら「戻ってきた」という意味がある。薬“リターンドたんぱく質”の効果によって、ゾンビ化から戻ってくるという意味もあるためか、邦題は劇場公開やレンタル・ビデオ市場を考慮し、分かりやすいゾンビの語を使用し、ゾンビ化への限界点を意味するだろう『ゾンビ・リミット』と名づけたのかもしれない。 主人公は、ミュージシャンでギターの講師もするリターンドのアレックスと、その恋人のリターンド治療医師のケイト。 6年前のある日、アレックスがショップで倒れている中年男性を助けようとしたところ、実は彼がリターンドとは分からず、指を咬まれてしまう。アレックスを診察したのがケイトで、2人はリターンドと担当医師という関係を超えて愛を育むことになる。 ケイトは、日々リターンド患者を診察し、彼らに対して慌てさせないよう優しく接する。感染した幼い子供をもつ両親が、「“リターンドたんぱく質”の在庫はあとわずかという噂が流れているが……」と質問されると、ケイトは「根も葉もないデマよ」とキッパリ。国はリターンドをできる限り増やさないよう、感染者に“リターンドたんぱく質”を配給し続けているのだから、必然的にそれを採取できる感染者は減少してくる。それを早くから察知していた国側は、“リターンドたんぱく質”の代わりになる、人工開発された“合成たんぱく質”の研究開発に着手するが、未だ完成にいたっていない。 ケイトはその事実を知っていても、優しい女医を演じて嘘をつき続け、しかも自分の勤務病院の薬品管理部の女性を通じて、アレックスのために密かに“リターンドたんぱく質”を高額で横流ししてもらっている。ケイトはエゴにはしってしまい、リターンドの治療医師にあるまじき行為を取っていた。アレックスも、彼女の行為をありがたいと感じながらも反道徳的な行為に対して何も言わない。2人の部屋の冷蔵庫には、手に入れた“リターンドたんぱく質”のアンプルがたくさん隠してある。 そんな2人の姿を見ていると人間の本性を感じ取ると同時に、この世界観に説得力が増してくる。ケイトは、アレックスさえ今のままでいてくれれば、他の感染者=リターンドがどうなってもいいと考えているわけじゃない。ケイトがまだ子供だった頃、両親がリターンドとなり、哀しい出来事を体験した……だからこそ彼女は、リターンドの治療医師になったと推測できるし、かつて愛する者を救えなかった後悔が、アレックスのために横流しをさせたと理解できる。 しかも、ケイトのリターンドに対する気持ちが、前半のこんな場面で力強く迫ってきた。ある日ケイトが勤務する病院に、黒い目だし帽を被った反リターンドの過激派が銃を持って襲撃した! 彼らはケイトに銃をつきつけ、「いかれているな、ゾンビのお世話か?」と揶揄した。するとケイトは、「彼らは、リターンドよ」と気丈に言い返した。怒った過激派は、更に「(彼らを)ゾンビと言え」と銃を向けていきがるが、彼女は決して「ゾンビ」とは言わなかった。 だからケイトは、たとえ社会や民衆がリターンドをゾンビと表現しようとも、自身の中ではあくまでリターンドという思いが強い。このケイトの思いを感じ取れる人なら、邦題の『ゾンビ・リミット』には少々抵抗があるハズだ。 そして、ケイトの病院に入院中だったリターンド患者は、過激派によって全員射殺され、リターンド=感染者の名簿を奪われてしまう。 過激派によるリターンド患者殺害の衝撃は、2016年7月に起きた「相模原障害者施設殺傷事件」の加害者のように傲慢だが、それは彼らだけではなかった。感染者=リターンドは社会の弱者でありマイノリティで、“リターンドたんばく質”の在庫薄が明らかにされると、リターンドの社会の風当たりは一層強くなっていく。 反リターンド派によって、“リターンドたんぱく質”配布所や病院が続けざまに襲撃され、しまいには病院そのものが軍の統治下に置かれた。そして国側がついに発令。「リターンドは、3日以内に監視センターに出頭しなければ逮捕する」と。大型バスに乗り込むリターンドたちの姿は、まるで第二次大戦でユダヤ人らがナチの強制収容所に運ばれる様とダブッてくる。 筆者も彼らをゾンビとは言いたくない……リターンド患者が増えてゆく世界を、リアル・シチュエーション風に描きつつ、アレックスとケイトの2人の愛と葛藤のドラマが展開する(それについての詳細は、ここでは書かないでおきます)。どうか本作を観て欲しい。もしゾンビ化させるようなウィルスが蔓延したら?……それをシリアスに捉えた危機的社会として描写しているからこそ、アレックスも、ケイトも、真に迫る魅力を発する。 国から“リターンドたんぱく質”の配給が停止されようとした時、アレックスは、25年来の親友にリターンドであることをカミングアウトしたことで、予想外の事態に陥ってしまう。そして、反リターンドの過激派が感染者名簿を入手してリターンド狩りをはじめる。更に出頭しないリターンドを捜査する警察の手も迫る。是非、追いつめられてゆく2人の姿を目に焼きつけて欲しい。■ © 2013 CASTELAO PICTURES, S.L. AND RAMACO MEDIA I, INC.. ALL RIGHTS RESERVED.
-

COLUMN/コラム2016.12.07
日本中が笑顔の魔法にかかった!11/23(祝)公開『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』ジャパンプレミア&スペシャル・ファン・ナイト★レポート
11/21(月)六本木ヒルズアリーナで開催されたジャパンプレミア、そして22(火)スぺシャル・ファン・ナイト、11/23(水・祝)初日舞台挨拶と3日間連続で集まったファンの前に登場。会場は大勢のファンたちの大歓声に包まれました。 今回、この「ジャパンプレミア」と「スペシャル・ファン・ナイト」の取材にザ・シネマ特派員もち米が行って参りました!「行きたかった!」そんな皆様のために、スペシャル動画と写真付レポートで当日の会場の熱気と感動をお届けできたなら幸いです。 集まったファンの掛け声で、会場は美しくブルーにライトアップ!遂に、エディ・レッドメインらキャストたちがレッドカーペットに登場しました。「I love you!」「Eddie!」割れんばかりの大歓声の中、傘を片手に登場したのは本作の主人公ニュート・スキャマンダー役のエディ・レッドメイン。 見てください、この姿。雨の中でも絵になる!まさに水も滴るいい男。気品溢れる佇まいに、穏やかな笑顔。さすが、英国紳士。寒空の下、この瞬間を待ちわびていた大勢のファン1人1人の元へと歩み寄り、丁寧にサインするファン想いな姿に会場のファンはもちろん、シャッターを切っていた筆者も思わずうっとりしてしまいました。 続いて登場したのは、アメリカ魔法省に務めるティナを演じたキャサリン。スクリーンで見るよりも、更にスラリと背が高く、美しい!ドレスの上にコートを羽織って登場されたのですが、生まれてこの方、あんなにロングコートの似合う美女を見たことはありません・・! 凛としたオーラが素敵でした。 最後に登場したのはティナの妹クィニー役のアリソン・スドル。 そして、本作のメインキャラクター4人の中で唯一の「ノーマジ」(いわゆる“マグル”)のジェイコブを演じたダン・フォグラー。 天使のようなニコニコ笑顔のアリソンに、シャッターを切りながら思わず「可愛い!」と叫んでしまった筆者なのでした(笑)。思わず釣られてしまう屈託のない笑顔はずっと見ていたくなるほど超キュート! そして、ユーモアたっぷりにファン達を盛り上げ一緒に写真撮影に臨むのはダン。映画の中からそのまま出てきたような優しいダンの周りには、笑顔が広がっていました○ こうして、会場にさっそく笑顔の“魔法”をかけたキャスト一行が次に向かったのは…メインステージ。そこへニュートさながらトランク片手に登場したのは、本作の宣伝大使を務めるDAIGOさん。 そっとトランクをステージの中央に置くと煙が立ちこみ… トランクの中からエディが再び登場!映画の世界さながらの粋な演出に会場は割れんばかりの大歓声!背後の扉に向けて「アロホモーラ!(開け)」とエディが唱えると次々にキャストが登場!大熱狂のステージの模様はこちらの➡動画でチェックしてみてくださいね✔ ≪11/22(火) スペシャル・ファン・ナイト≫前日のジャパン・プレミアの興奮冷めやらぬままザ・シネマ特派員もち米が次に向かったのは、ファンとキャストたちが交流できるという、夢の「スペシャル・ファン・ナイト」! グリフィンドールやハッフルパフ、「ハリー・ポッター」の寮生に扮する方から、ドビーのお面をかぶった方まで、思い思いの「ハリー・ポッター愛」に溢れたコスチュームで集った色とりどりのファンで会場はいっぱい。大歓声の中、満を持して登場したエディらも、ファンの姿を見るなり大興奮!「こんな熱い応援があるからこそ、次への映画の閃きが生まれます」とデイビット・イェーツ監督からも感謝の言葉が。 キャストたちが、会場のファンからの質問に直接答えるQ&Aコーナーでは、「お子さんにかけたい魔法は?」、「日本のどんな所に魅力を感じましたか?」、「ニュートのトランクに入ったら中で何をしてみたいですか?」など、粋な質問が。そして3人の回答が、これまたとっても素敵なんです☺ なかでもアリソンの回答には日本人として、思わずうるりと来てしまいましたよ・・・詳しくは是非、動画で見てみて下さいね! イベントもいよいよ終盤になると、キャスト自らが賞品を手渡しする夢の様くじ引きタイム!さらに、写真撮影ではキャスト自らがファンたちに駆け寄り、ハグするという感動的なシーンも。見ていて思わず目頭が熱くなりました。なんて暖かな光景!ファンの皆様にとって、きっと一生忘れらない1日になったことでしょう○ こうして、笑いあり!涙あり!の熱い、熱いスペシャル・ファン・ナイトは惜しまれつつ幕を閉じました。ファンの皆さんの真っ直ぐな情熱を間近で見ていて、「ハリー・ポッター」がこの世界にかけた魔法の美しさに改めて感動。同時に、「映画」が大勢の人を結びつけることの素晴らしさも改めて感じる2日間でした! 『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』は、間違いなく今年観るべき1本!新しい魔法の始まりを、ぜひぜひ映画館で目撃してください☺ 座席で仰け反ってしまうほどの迫力の映像はファンタスティックな魔法世界に連れて行ってくれるでしょう!■(特派員 もち米)
-

COLUMN/コラム2016.10.15
【ネタバレ】奇才ヴァーメルダム監督が描く、シッチェス・カタロニア映画祭グランプリ受賞作『ボーグマン』に見えてくるもの!
日本ではほとんど知られていない俳優たちばかりが出演し、静かに淡々とした映像が映し出されていくが、ミステリアスで得体のしれない人間を見るのは、実に興味深くて魅きつけられる。それが1人ではなく、どこからともなく集まってくるような恐ろしい集団となれば、なおさらだ。なんとも不気味で刺激的、且つアーティスティック、とはいえ最後まで飽きさせないエンタメ性も感じさせながら、シュールなテイストに満ちたオランダ=ベルギー=デンマーク合作の秀作スリラー(その不可思議なセンスからは、デヴィッド・リンチ風の匂いも感じ取れる)。 他人の土地に、無断で幾つも穴倉(ねぐらみたいなもの)を掘り、そこにホームレスのような人々が秘かに暮らしている。そんな彼らを察知した地元の人々が追い出しにかかると、一斉に穴倉から出てきて逃げ出す。 逃げる集団のリーダー格の1人は、乱れた長髪に無精ひげを生やし、大きな庭がある邸宅にやってきて、「あなたの奥さんを知っている……汚れているから、なんとか風呂を貸して欲しい」とおかしなことを強引にねだる。「妻を知っている」とテキトーなことを言う男に怒り狂った夫リシャルトは、その男を暴力的に叩きのめして追い帰してしまう。 この最初の事件が起きる前、すなわち冒頭にこんな字幕が出ていた。「そして彼らは、自らの集団を強化するため、地球へ飛来した」と……なんなんだ、この意味は!? その“彼ら”を、全編を観て分かったことを要約してみれば、他人の土地に無断侵入して、仲間と連絡を取りあって狡猾に策略を弄し、俗物的な人間を次々と殺しては、仲間(信奉者)を増やしてゆく殺人集団である。でも、どう見ても、“地球へ飛来”してきたような生物には見えない。 そして題名のボーグマンとは、謎のホームレス集団のリーダー格に見える男、或いは幹部相当の男なのか……自らをカミエル・ボーグマンと名乗っていた。「イエスは自己中のクソ野郎だ」と言い放つ彼は、大天使ミカエルを嘲笑したような名になっているのも、当然偽名だからだろうか。 ならば“地球へ飛来した”は、何らかの比喩なのか。高級住宅地に住むような富裕層を嫌う集団のようにも見えるが、リシャルト家の庭師夫婦……平凡だが性格が良さそうな人を殺害したり、リシャルト家に庭師の面接に訪れた中産階級の男たちを襲ったりしていた。そう考えると、ボーグマンらは、人間社会から逸脱し、金品や権力や名声に固執しない自由奔放さに生きつつも、彼らなりの決まりごとが確かに存在しているようだ。 カミエル・ボーグマンは、映画が始まって早々、次の標的にリシャルトと妻マリナに絞っていた。カミエルがマリナと過去に出会っていたか否かは不明だが、マリナはリシャルトが暴力で傷めつけたカミエルを気遣い、夫がいない間に風呂に入れ、大きな庭の離れにある小屋を数日間貸してあげる。カミエルは外部にいる仲間と携帯電話で連絡を取り合い、「時は来たか?」の問いに対し「まだだ」と応えていた。そしてカミエルは、秘かに邸宅に侵入しては様子を窺っていた。不思議なことに、悪夢を見て泣いていたマリナの娘イゾルデに接し、なにやら話しを聞かせていたのだ。 このイゾルデがかなり変わった子で、クマのぬいぐるみの体を裂いて中の詰め物を抜いて、代わりに土を入れていた。更に(庭師の面接にやってきた)暴力で叩きのめされた男の顔面に向け、トドメとばかりに大きなブロックを振りおろしたのだ。まるで子供が矮小な生物をいじめ、殺してしまうかのように。 すべては、カミエル・ボーグマンの悪影響なのか。それを感じさせるのが、マリナのこのセリフ。「何かに囲まれている。時々忍び込んでくるの。その温かさは心地いいけど、私たちを惑わせる……悪意を秘めているの。私には、そう感じる。後ろめたいの。私たちは、あまりにも恵まれている。罰を受けるわ」 マリナは、カミエル・ボーグマンを怖れていても、彼には抗えないほど魅かれてしまう何かがあると思っている。夫リシャルトとは180度異なり、何を考えているのかも分からないし、裕福な生活を与えてくれるわけでもない。なのに、彼のどこがいいのだろうか? やがてカミエルの肉体をも欲するようになる。彼には、女性の心を手玉に取る魔力があるのかもしれない。 リシャルト家の周辺で、ボーグマンらによって人々が殺されていくが、死体はすべて、ある池の底に遺棄されていた。謎の集団は黙々と作業をこなすように死体を処理する。死体の頭部をバケツに入れてコンクリート詰めにし、乾いたらその死体を自動車で運んで池に沈めるのだ。池の底には、コンクリート詰めのバケツの重量で、池の底に頭部が着いた逆さ死体が幾つも並んでいる。ちょっと見、水の流れに揺れる大きな水草のようにも見えるが(笑)、全て死体。これが不気味! 観終わって思うのは、カミエル・ボーグマンらカルト犯罪集団は、格差社会が生んだ恐怖の象徴なのか、富裕層に対する怒りを表現した何かか、それとも人間の代表的な欲を排してダークサイドに傾倒した人間を描きたかったのか、その意図は全くもって不明である。 従って、この映画が描きたかったことも不明瞭に映るかもしれないが、本作の魅力はそこにあると思う。観る者の想像力に刺激を与え、“地球へ飛来した”の解釈も、観た者によって異なってくるはず。筆者はこう解釈した。地続きの国の人々が抱く不安……それは外国人(英語表記だと、ALIEN)の移民や難民の流入によって、格差社会がより一層明確になっていく。移民とは感情を交わすことができないまま、貧富の格差社会が生まれるが、やがては彼らによって土地が奪われ、職を奪われ、犯罪が起きるという危惧を、ボーグマンという集団の姿を借りて表現した社会派ホラーのように見えた。まずは頭をまっさらにして、奇才アレックス・ファン・ヴァーメルダム監督が描くユニークな秀作に触れて欲しい。■ © Graniet Film, Epidemic, DDF/Angel Films, NTR
-
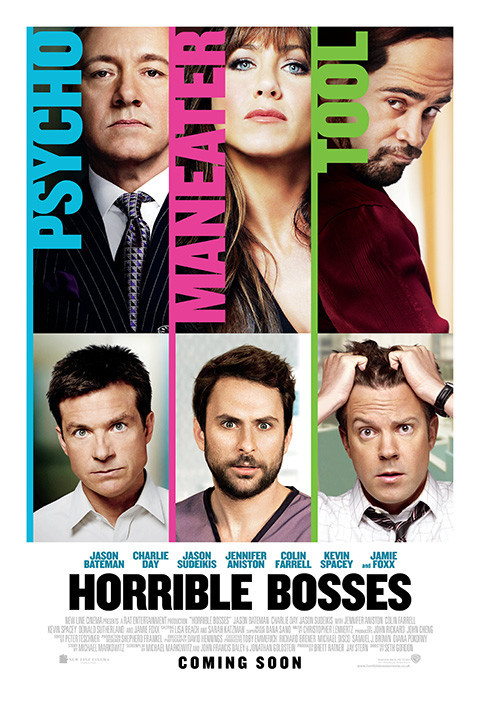
COLUMN/コラム2016.08.16
モンスター上司
「アメリカでは自分は自分、人は人」 これは和製ミュージカル映画としてカルト的な人気を誇る『君も出世ができる』で、アメリカ帰りの合理主義者に扮した雪村いづみが歌う「アメリカでは」という挿入曲の歌詞の一節だ。1964年公開作なので、今から半世紀以上も前の映画だけど、日本人がアメリカ企業について思い浮かべるイメージはあまり変わっていないんじゃないかと思う。 ところが、そんな幻想を粉々に打ち砕くコメディ映画がアメリカには存在する。『モンスター上司』がそれだ。テレビコメディで活躍していたマイケル・マーコウィッツが草稿を書き、『BONES』の精神科医ランス・スイーツ博士役で知られる俳優ジョン・フランシス・デイリーとジョナサン・ゴールドスタインのコンビが仕上げた同作の脚本(アメリカの映画界ではよくリレー形式で脚本が書かれる)は、ブラックリスト(映画化が決まっていない脚本で有望と目されているもの)として扱われ、各社が争奪戦を繰り広げたそうだ。では、その内容はというと…。 主人公はニック(ジェイソン・ベイトマン)とデール(チャーリー・デイ)とカート(ジェイソン・サダイキス)の三十代男子3人。親友同士の彼らは、立場はちがってもヒドい上司に悩まされているという共通点があった。金融業界で働くニックの上司デビッド(ケヴィン・スペイシー)は、朝6時から深夜まで部下をこき使うパワハラ野郎。しかも妻の浮気をやたらと疑うサイコ的な性格を持つヤバい男だった。歯科助手のデールの上司の歯科医ジュリア(ジェニファー・アニストン)は、デールに婚約者がいながらセクハラ攻撃をしかけてくる色情狂。職場で始終迫られ、デールの忍耐は限界に達していた。化学薬品会社の経理マンを務めるカートは、ドラッグ中毒の社長の息子ボビー(コリン・ファレル)が直上司なことに手を焼いていた。それでも社長がいい人だったから耐えていたものの、彼の急死によってボビーが社長に。リストラや環境廃棄物の第三世界への投棄を推し進めるのを目の当たりにして、怒りのゲージが振り切れてしまう。 かくして追いつめられた3人は、場末のバーでムショ帰りの謎めいた男ディーン(ジェイミー・フォックス)の指導を受け、互いの上司を暗殺する計画に乗り出すのだった。そのためには敵の弱点を掴むのが大事と、3人は上司たちの留守中に家宅侵入するものの、それだけで罪の意識を覚えてしまい計画をうち切ろうとする。ところが、デビッドの部屋にボビーのスマホを置き忘れたことが原因で、妻の浮気を疑うデビッドが、ボビーを射殺するという事件が勃発してしまう。現場の近くにいた3人は警察にマークされはじめ、殺人を考えていただけで殺人容疑で逮捕されるという絶対絶命のピンチに陥ってしまう! 今作の監督を任されたのはセス・ゴードン。超名門イェール大学を卒業したあと、国連のケニア支援プロジェクトに従事。そこからドキュメンタリー映画のプロデューサー兼監督に転じ、そこでの演出の腕が見込まれてヴィンス・ヴォーンとリース・ウィザースプーン共演のクリスマス映画『フォー・クリスマス』(08年)で長編映画デビュー。いきなり1億ドル以上のメガヒットを記録してしまったという変わり種監督だ。 この監督の人選で分かる通り、当初はヴィンス・ヴォーンやオーウェン・ウィルソンらがキャスティングの候補にのぼっていたらしい。しかし最終的には中堅俳優で固める布陣に落ち着いた。このキャスティングこそが、本作成功の最大のファクターになったと思う。主人公がスター俳優すぎると、職場でのイジメにリアリティがなくなってしまうからだ。 その点、本作のジェイソン・ベイトマン、チャーリー・デイ、ジェイソン・サダイキスのトリオは絶妙なところを突いていると思う。ベイトマンについては他作品の記事で、何回か書いているので、ここでは残り2名について書いておこう。チャーリー・デイとジェイソン・サダイキスはドリュー・バリモアとジャスティン・ロングが共演したロマンティック・コメディ『遠距離恋愛 彼女の決断』(10年)でロングの友人役として共演しており、そこでのコンビネーションが認められて本作で再共演することになったと思われる。 デイは76年生まれ。アメリカでは、2005年から放映が開始され、今も続いている人気シットコム『It's Always Sunny in Philadelphia』の主演俳優兼脚本家として知られている。映画俳優としては、怪獣の撃退方法を偶然発見する科学者に扮した『パシフィック・リム』(13年)でのコミカルな演技が記憶に新しい。 ジェイソン・サダイキスは75年生まれ。セカンド・シティやアップ・シチズン・ブリゲイドといったコメディ劇団を経て、03年に『サタデー・ナイト・ライブ(SNL)』のライターに採用。05年からパフォーマーとして出演するようになり、13年の卒業まで8シーズンにわたって活躍し続けた。09年からはセス・マクファーレンが手がけるアニメシリーズ『The Cleveland Show』(09〜13年)にも声優として出演。『SNL』は基本的に出演者にはテレビ番組の掛け持ちを許されないので、これは異例のことだ。 コメディアンとしてはアイディア一発で笑わすというより、巧みな演技で笑わせるタイプのため映画進出も早く、『SNL』のレギュラー昇格直後にデヴィッド・ウェイン監督の『幸せになるための10のバイブル』(07年)に出演。前述の『遠距離恋愛 彼女の決断』を経て、ファレリー兄弟の『ホール・パス/帰ってきた夢の独身生活<1週間限定>』(11年)ではオーウェン・ウィルソンとダブル主演を果たした。そして本作やウィル・フェレル主演作『俺たちスーパー・ポリティシャン めざせ下院議員!』(12年)を経て、本作でも共演しているジェニファー・アニストンとリユニオンして、堂々主演を務めた『なんちゃって家族』(13年)が大ヒット。名実ともにスター俳優となった。 アニメ『アングリーバード』(16年)では主人公レッドの声を務めたほか、『栄光のランナー/1936ベルリン』(16年)といったシリアス物から、レベッカ・ホール共演の『Tumbledown』(15年)やゲイリー・マーシャルの遺作『Mother's Day』(16年)といったロマンティック・コメディまで幅広く出演している。本作を含めて、特別イケメンというわけでもないのにモテ男を演じることが意外と多いのは、私生活の反映なのかもしれない。サダイキスのパートナーは、テレビドラマ『Dr.HOUSE』や『トロン: レガシー』(10年)で知られる美人女優オリヴィア・ワイルドなのだから。 そんな実力はあるけど、まだ「知る人ぞ知る」状態の彼らをイジメまくるのが、『アメリカン・ビューティー』(99年)でアカデミー主演男優賞を獲得し、近年は『ハウス・オブ・カード 野望の階段』(13年〜)で悪の大統領フランシス・アンダーウッド役で知られるケヴィン・スペイシー、国民的人気を誇ったテレビ・シットコム『フレンズ』(94〜04年)のレイチェル役でブレイクし、以後もロマンティック・コメディ界の頂点に君臨し続ける鉄人ジェニファー・アニストン、そして『ヒットマンズ・レクイエム』(08年)でゴールデン・グローブ賞をゲットし、超大作『トータル・リコール』(12年)からオフビートな『ロブスター』(15年)まで幅広い活躍を続けるコリン・ファレルといったスター俳優たちだ。この「格差」があるからこそ、イジメが実感を持って伝わってくるのだ。 というわけで、主人公3人がこの「格差」をどのようにひっくり返すのかを、ワクワクしながら観て欲しい。 © New Line Productions, Inc.