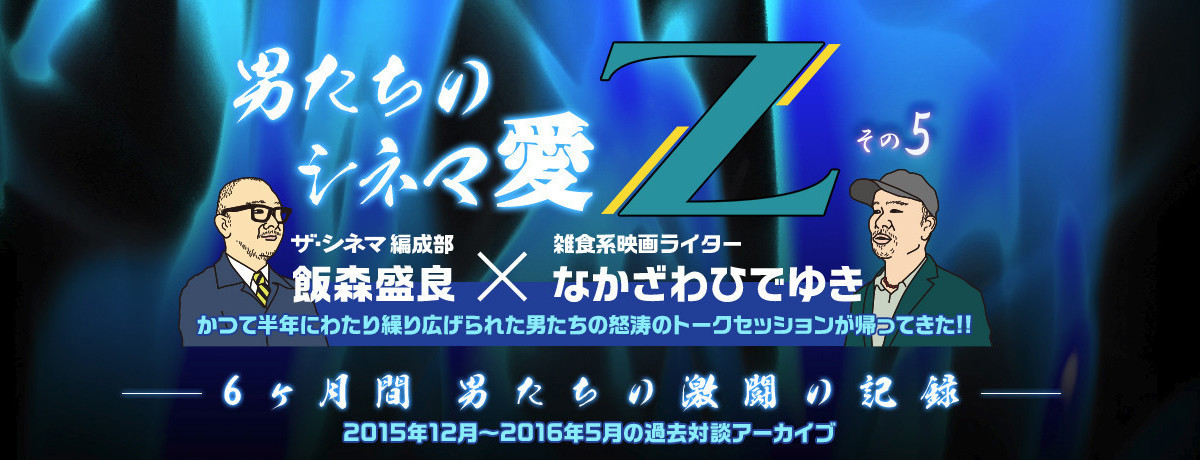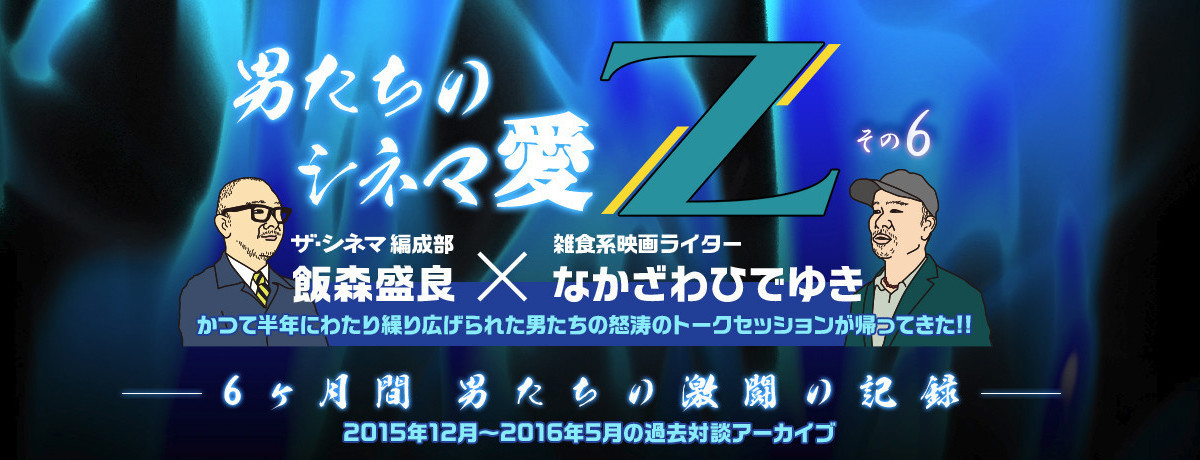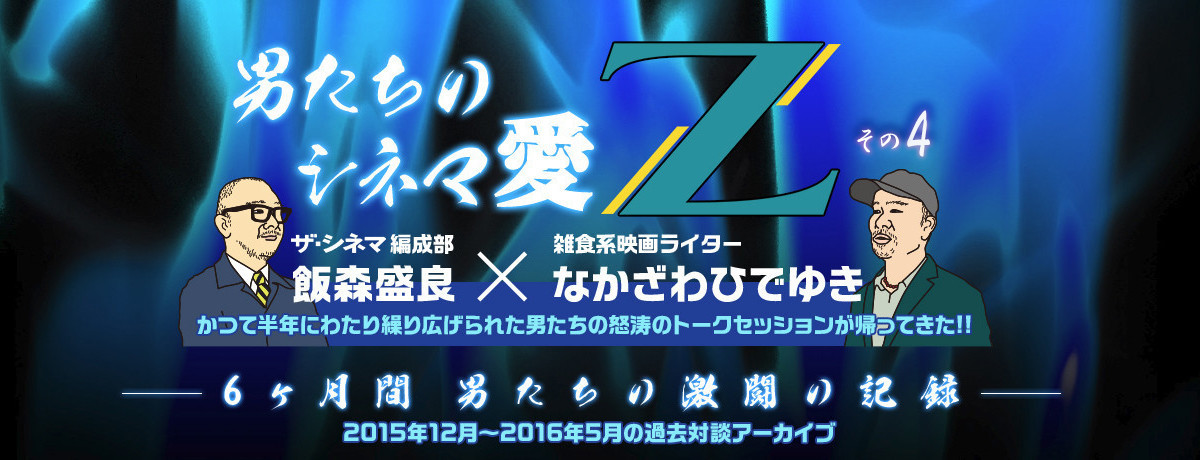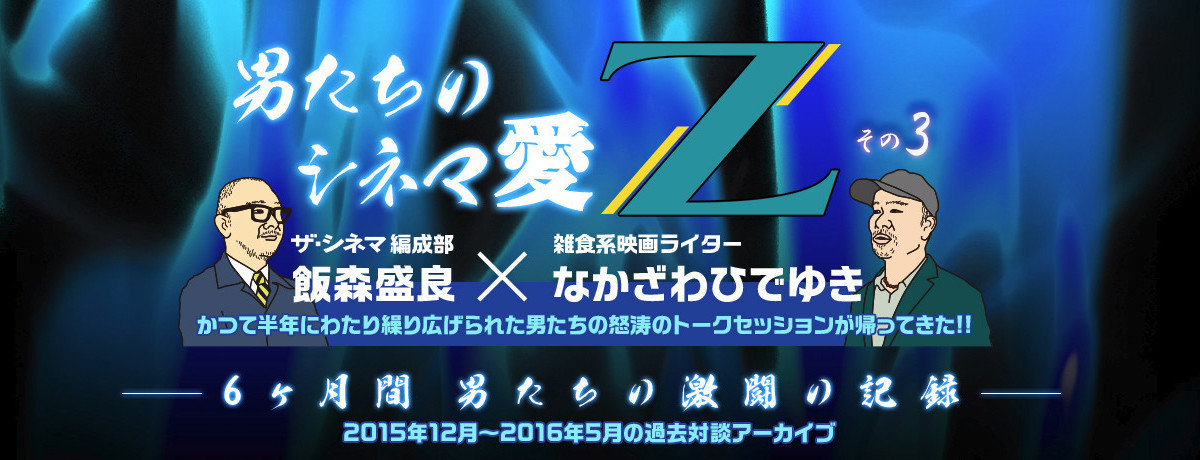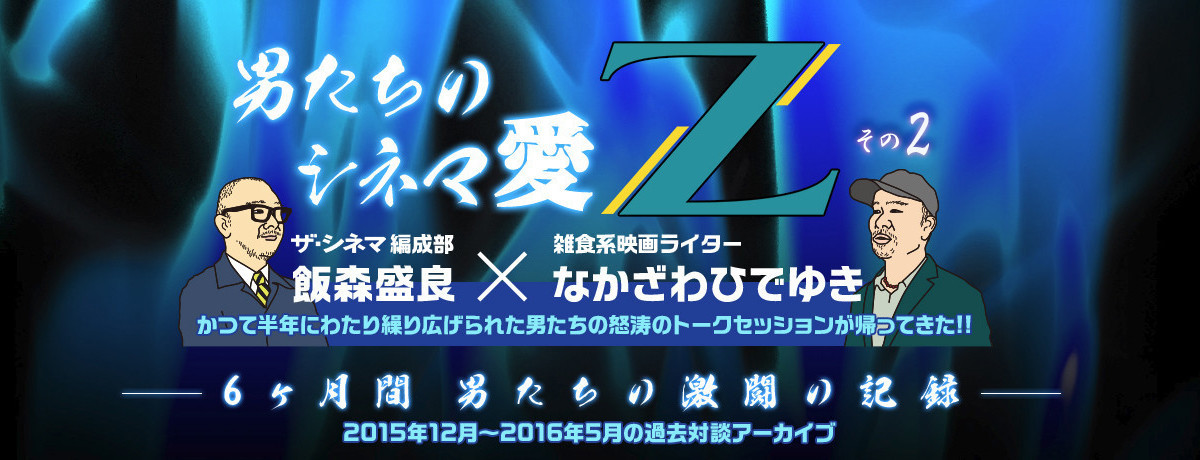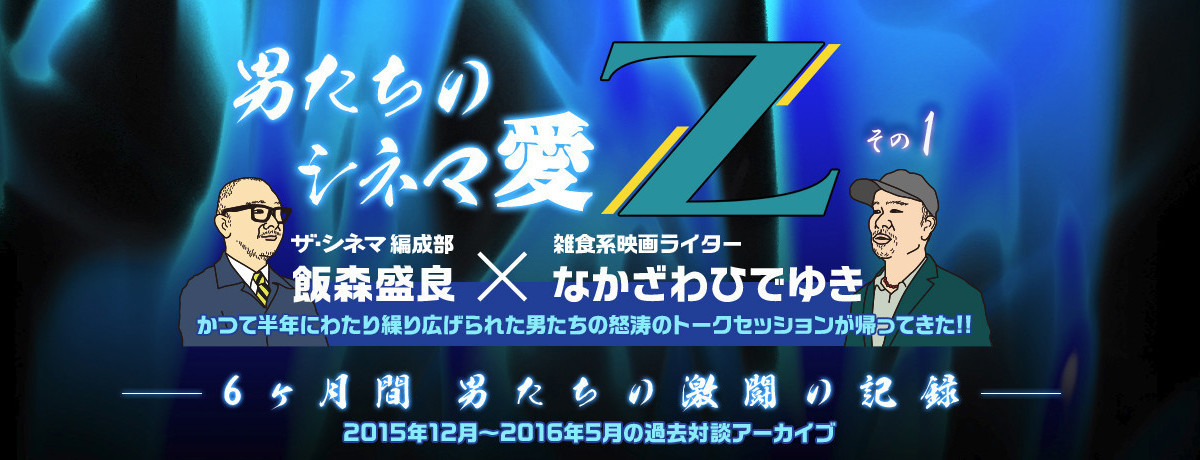なかざわ:で、最後は『ハーロー』ですね。
飯森:これぞ、まさに、ゲスの極み(笑)。
なかざわ:正真正銘のハリウッド・バビロン(注15)ですね。ただ、これをジーン・ハーローの伝記映画として額面通りには受け取って頂きたくない。
注15:1965年に出版された、オカルトに傾倒しているアングラ映画監督ケネス・アンガーによる著書。すぐに発禁となったその過激な内容とは、映画黎明期以来のハリウッドの最もダーティーなゴシップとスキャンダルの数々。後に発禁は解かれ、今では邦訳版がAmazonで古本で手に入る。
飯森:そうなんですか?脚色があるってこと?
なかざわ:結構あります。そもそも、本編中でジーン・ハーローは本名だと言っていますけれど、これがまず違っていて、ジーン・ハーローというのは彼女の母親の名前を拝借した芸名なんです。本人の本名はハーリーン・ハーロー・カーペンターっていいます。
飯森:それって事実誤認なんですかね?それともわざと?
なかざわ:そこは分からないです。ただ、彼女ほどの大スターで有名人であれば、本名くらいの個人情報は普通に知られていたと思うんですけれどね。あとは、この作品の中ではハーローとその家族、そしてマネージャーと夫ポール・バーン以外のキャラクターは、全員実在の人物を基にした架空の人物です。映画会社の名前もそうですね。まあ、マジェスティック・ピクチャーズなんてMGMが元ネタだってバレバレですけれど(笑)。
飯森:でもまあ、話があまりにゲス過ぎて実名では描けませんよね。
なかざわ:あとは、劇中だとポール・バーンが最初で最後の夫みたいな描かれ方をしていますが、実際彼女は3回結婚していて、ポールは2度目の旦那なんですよ。
飯森:それは僕も知っていました。デビューする前のかなり若い頃、15歳とかで結婚していますよね。
なかざわ:そう、しかもかなりの大富豪と結婚してビバリーヒルズで暮らしていたんですよ。
飯森:そうなんですか!?映画の中だと、安普請の平屋の団地で貧乏暮らししてたイメージですけれど。
なかざわ:まだ有名になる前に最初の旦那と離婚していて、その後は売れない無名女優として母親と継父の家に同居していたらしいので、そこは必ずしも間違ってはいません。とはいえ、最初の結婚期間中は一時的にせよ、セレブリティの生活を経験しています。
飯森:そうなんだ!映画だとかなり底辺にいた人が、どんどんとのし上がっていって成功し、そこで心のバランス感覚が狂っちゃう、という毎度お馴染みの転落ドラマになっていますけれど…。
なかざわ:必ずしもそうではないです。
飯森:でもそうすると、とんでもないビッチというか、15歳とか16歳とかで金持ち爺さんをこましてセレブ生活を送ったような、大したタマなんだ。
なかざわ:いえ、最初の旦那って大富豪は大富豪でも、さほど年齢の違わない御曹司なんですよ。
飯森:なるほど!そうすると、世間を知らない金持ちのボンボンをうまいこと篭絡したわけね(笑)。いいっすねー!やっぱ大したタマだよ。映画より実人生の方が全然すごいな!
なかざわ:あとは、本人にもともと映画女優になる意思がなかったという描写は本当なんですけれど、劇中だと強欲でゲスい継父に無理強いされてみたいな話になっているのは違っていて、実際は母親の強い要望だったみたいですね。
飯森:お母さんって、映画の中だと旦那に言われるがままのポケーッとした感じですよね。
なかざわ:実はお母さんがもともと女優志望で、実際にチャレンジもしたんだけど挫折しているんですね。なので、自分の夢を娘に託したんですよ。
飯森:そうなんですか。そりゃまたありがちな、おなじみのステージ・ママの話だ。そういえば、これも映画では描かれていなかったですけれど、お母さんはある種の宗教の影響も娘に及ぼしましたよね。とある宗旨に厳格な信仰心があって、確か病気の娘を医者に診せることを宗教的理由から拒んだって言われてますよね?
なかざわ:あ、それは後になって出てきたゴシップで、実際はちゃんと医者に診せているんですよ。通院記録も残っていますし。ただ、担当医が彼女の体調不良の原因を誤診したらしいんですね。これはネタバレになりますけれど、映画だと肺炎で死んだことになっていますが、実際は腎臓病なんですよね。
飯森:大丈夫、この映画にネタバレはないです。ジーン・ハーローが若くして死んでいるということは周知の事実ですから。幾つでしたっけ?
なかざわ:26歳です。
飯森:若い!それは若すぎますね!とにかく、彼女はこの映画の中ではどん底から這い上がってきて映画スターとなり、セックス・シンボルとして持て囃されてハリウッドの泥沼にずぶずぶとハマっていきアッというまに若死にする、一本道な物語なわけですけれど、今お伺いしたお話だと、現実の方がさらに紆余曲折、波乱万丈だったわけだ。まさにハリウッド・バビロンを地で行く人ですよね。あとは、旦那絡みの話ですか。これが一番ヤバいんだ!
なかざわ:この映画にも出てくるポール・バーンのことですよね。
飯森:この映画だと、ポール・バーンと結婚初夜にHなことをしようとしたら、旦那のナニがダメだったという話でしたよね。
なかざわ:インポテンツだったということですね。それを責められて旦那は逆上してジーンに暴力を振るうわけですけれど。
飯森:それで彼女はマネージャーの家に泣きながら逃げてくる。あのシーンって、僕はこの映画の最大の問題で、あそこはまるっきしリアリティが無いように思うんですよ。男子たる者、ちょっと萎えちゃったって、そりゃ誰でもある話じゃないですか。体調だったりとか、酒だったりとか、年齢だったりとかで。それに対して、最初のたった1回で、あんな激越なリアクションを返す女の人っているの!?って。私を見て勃たない男なんてありえない!私の結婚は台無しよ!この辱めをどうしてくれるの!みたいな。リアリティに欠けますよ。
なかざわ:しかも、この結婚のために貞操を守って来たのに!みたいなこと言うじゃないですか。
飯森:今までの我慢が丸損よ!こんなことだったらもっと前にヤッてたのに!みたいな。そんなこと言う自称処女がこの世にいるのかと。あれって実際は結構違うんですよね。
なかざわ:はい、実際にインポテンツだったという事実はないみたいですね。
飯森:あの旦那はインポどころか相当いろんな女を食いまくっていて、長年の事実婚みたいな妻までいたらしいんですよね。それにもかかわらずジーン・ハーローと正式に結婚しちゃったんで、嫉妬に狂った内縁の奥さんに殺されたという説もあるみたいですし。
なかざわ:マフィアに殺されたという説もありますしね。その辺はね、MGMが事実を揉み消して葬り去ってしまったとも言われていて、真相は闇の中なんですけれどね。
飯森:これはアメリカで信じられている俗説だということで僕も読んだことがあって、どこまで信ぴょう性があるかは分かりませんが、インポだったポール・バーンがディルドを買ってきて股間に装着し、ごめんね、勃ちはしないんだけど今日はこれでやろう♥と言った時に、ジーン・ハーローが憐れむような、蔑むような高笑いをして、それにカチンときた旦那が自殺しちゃったというような話も、ものの本には書いてあったりするんですけれどね。いやはや、いよいよゲスの極みになってまいりました。
なかざわ:ただ、MGMといえば当時ハリウッドで最大の映画スタジオですよね。そこの幹部にまで上り詰めたような人生の成功者が、インポをバカにされたくらいで全てを捨てて自殺するとはちょっと考えられないかなとも思いますけれどね。
飯森:まあ、この映画が一番リアリティが無い、「こんな女いねえよ!」という状態になっちゃってるんですけれど、その次に信じがたいのがこのペニバン説ですね。マフィア説とか内縁の妻犯行説の方がリアリティはあるでしょう。で、実はポール・バーンの遺書というのが残されているんですね。
「最愛の人へ。僕が君に対して犯した恐ろしい過ちを償い、僕自身の軽蔑すべき屈辱を拭い去るには、残念ながらこれしか方法がないんだ。愛しているよ。ポールより。
追伸:昨夜のことはほんの冗談だったんだ」
と書き残して、風呂場で真っ裸で頭を拳銃で撃ち抜いたんですよ。思わせぶりな内容ですよね。いったい前の晩に何やらかしたんだ!?と。この遺書のあることが、いろんな妄想や都市伝説など全ての元凶ですね。
なかざわ:あらぬ妄想を掻き立てますもん。
飯森:そういったドロドロでグチャグチャな話なんですが、この映画が諸説の中で一番嘘くさく思えるというのは、逆に言うと強引にでもセーフに描こうとしているんじゃないかな。要するに、一番エグい話、大人のオモチャまで飛び出してくるような話とか、そういう毒々しいところまで踏み込まないためにも、リアリズムを犠牲にした。そうじゃないと本当にゲスの極みになり過ぎて映画作れませんから!この頃まだヘイズコード(注16)ありましたからね。
注16:1934〜1968年まで続いたアメリカの映画検閲制度で、宗教的・道徳的見地から様々な描写に対して規制がかけられ、当然エロは真っ先に槍玉に挙げられた。実は1934年以前の方がエロ描写(今の基準では全然大したことない、“お色気シーン”程度のもの)は許されており、それはYoutube上で「pre code」と検索すれば著作権切れの作品で容易に見ることができる。
なかざわ:それにしても、この作品は当時酷評されたというのも分からないではない。
飯森: 酷評されたんですか?
なかざわ:そうなんですよ。おかげで主演のキャロル・ベイカー(注17)は、これを最後にハリウッドを去ってイタリアへ都落ちすることになりましたから。
注17:1931年アメリカ出身の女性。本作でジーン・ハーローになりきる。渡欧後はお色気系路線で活躍。特に日本人にとっては『課外授業』(1975)の、イタリアで働くアメリカ人熟女教師役で知られる。主人公の童貞少年が憧れる美人音楽教師だが、実は別の少年にヌード写真を盗撮され脅迫を受けており、ノーブラで教壇に立たせられる、少年にワキ毛を剃らさせてあげる等のセクハラ羞恥プレイを強制されていたのだが、主人公によって救われ、お礼に彼の筆下ろしをしてあげる、という童貞喪失もの。特定世代の男性にとっては忘れがたき性春映画の不朽の名作で、そのヒロインとしてキャロル・ベイカーは一番知られている。
飯森: 要するに、西部劇大作なんかに出演していた第一級の大物女優がこの映画に出演することでキワモノ扱いされ、イタリアへ行って本物のキワモノになっちゃったってことですか(笑)。
なかざわ:当時彼女のバックについていた大物プロデューサーのジョセフ・E・レヴィン(注18)という人が、彼女をセックス・シンボルとして祀り上げようとしていたんですけれど、どうもそれが気に入らなかったみたいですね。
注18:宣伝プロモーションの手腕の冴えで伝説的に語られる、ショーマンシップ溢れる映画製作者。イタリアのサンダル史劇『ヘラクレス』(1958)を買い付けてきて、TVスポットを打ちまくるなど現代に通じる宣伝キャンペーンを発明して大ヒットに導き、主演のスティーヴ・リーヴスも大スターにし、幼い日のスタローンやシュワ、ロック様にとってのアイドルに仕立てた。また『ふたりの女』(1960)も買い付けてきてソフィア・ローレンをイタリアン・セックス・シンボルではなく徹底的に演技派として宣伝。非英語作品であるにもかかわらず彼女にアカデミー主演女優賞を獲らせた。その手腕でキャロル・ベイカーのことも売ろうとしたのだが…。
飯森: なんか映画の中の話と混同してしまいそうですよね。『ハーロー』という映画自体が、無理やり映画会社にセックス・シンボルに仕立てられて、嫌なんだけど次第に諦めてその役回りを受け入れていく女優の話でしょ?まんまじゃないですか。
なかざわ:そうなんですよ。ただ、キャロル・ベイカーがそれでも我慢して続けていたところ、この『ハーロー』が興行的にも批評的にもコケてしまったもんだから、もう私やってられない!みたいな感じでキレちゃったみたいなんですよ。
飯森: ちょっと待ってください!?セックス・シンボルを嫌がったわりに、イタリアへ行ってからはお色気女優みたいになってますよね!?
なかざわ:そうなんですよ。というのも、彼女は契約を巡ってジョセフ・E・レヴィンを訴えた結果、パラマウントから解雇されてしまったんですね。それでハリウッドを干されてしまったせいで、ヨーロッパへ行かざるを得なくなったわけです。
飯森: 最近の日本で言うとMUTEKIに行くパターンですね。
なかざわ:そうです(笑)。だから、イタリアでジャーロとかソフトポルノとかで脱ぐ仕事をするようになったのは、背に腹は代えられなかったからなんですよ。本当に、キャロル・ベイカーとジーン・ハーローのキャリアは被ってくるんです。
飯森: すごいのは、この映画が出来た段階ではまだキャロル・ベイカーのその転落は始まってもいないってことですよ。これが出来てから、これのせいで転落しちゃうんだから。映画の中でハーローという役を通じて、もうじき自分自身も体験することになる転落を、予行演習しちゃってたんですね。予言的というかなんというか…。
なかざわ:事実は小説よりも奇なりですね。
飯森: でもキャロル・ベイカーが幸いだったのは、セックス・シンボルになっても彼女自身がジレンマに陥ることなく輝き続けたことでしょうね。それこそラウラ・アントネッリかキャロル・ベイカーかというポジションをあの時代には築いて、性春映画のスターとして一世を風靡したわけじゃないですか。映画の中のジーン・ハーローはセックス・シンボルとしてのイメージに翻弄されて自分を見失い、最後はサセ子というか、行きずりの男にもすぐヤラせちゃうみたいなところまで堕ちて病んじゃいましたけど、キャロル・ベイカーはそうはならずに、あくまで演じているだけということで虚と実を切り離して考えられたんだ。メンタル強いですよね。
なかざわ:ただ、確かにこの映画だと旦那が自殺した後、ジーン・ハーローはアル中になって男をとっかえひっかえして自暴自棄になるという描かれ方がされていますけれど、実際はそうでもなかったんじゃないかなと思うんですよね。
飯森: 身持ちが最後まで固かったと?
なかざわ:いやいや、そういうことではなくて、あんな風に荒れて自暴自棄になったりはしなかったんじゃないかと。というのも、ちゃんとその後も映画の仕事をしていますし、3度目の結婚もしていますし。しかも映画の中では、そうした荒んだ生活の結果、肺炎になってしまったと描かれていますけど、もともと彼女は腎臓に持病があったらしいんですよね。それが悪化して死んじゃったんです。
飯森: あの病死に関しても諸説ありますよね。例の大人のオモチャ亭主が勃たないのを嘲り嗤われた初夜にDVをふるって、その時に内臓破裂で腎臓にダメージを負った、なんて都市伝説までありますけど、まぁそれは、ゲスの勘ぐりもここに極まれりみたいな話で、信ぴょう性は無さそうですね。
なかざわ:あと、この作品で気に入っているのは、これって1930年代が舞台じゃないですか。でも、この作品に出てくるファッションやインテリアのゴージャス感って、1960年代初頭のものなんですよね。それが特に端的に現れているのが音楽。ニール・ヘフティ(注19)の手掛けた音楽スコアって、まさに’50~’60年代にかけてのイージーリスニング・サウンドなんですよ。マントヴァーニ楽団(注20)とかパーシー・フェイス楽団(注21)みたいな。もしくはヘンリー・マンシーニ(注22)。ボサノバのリズムまで使われていますし。どれも1930年代には存在しない音です。まあ、実際ニール・ヘフティ自身がイージー・リスニング畑の作曲家ですしね。1930年代の社交界のことを「カフェ・ソサエティー」と呼ぶのに対し、60年代は自家用ジェットで飛び回るリッチな人々という意味で「ジェット・セット」と呼ばれたんですけれど、この作品の雰囲気は明らかに後者です。個人的に大好きというか、憧れる文化なんですよね。
注19:アメリカの作曲家、ジャズミュージシャン。映画音楽も手がけ、『ハーロー』以外ではジャック・レモンの『女房の殺し方教えます』(1964)、ナタリー・ウッドとトニー・カーティスの『求婚専科』(1964)、レッドフォードとジェーン・フォンダの『裸足で散歩』(1967)、ご存知ジャック・レモン×ウォルター・マッソー『おかしな二人』(1968)などの音楽を手がける。60年代の洒脱なラブコメなどに軽妙なオシャレ感を添えた。
注20:イギリスの編曲者・指揮者マントヴァーニの楽団。誰もが知る有名映画音楽や有名ヒット曲をマントヴァーニ流に華麗にアレンジし自身が率いる楽団で演奏。我々がイメージするTHEムード音楽、THEイージー・リスニングに換骨奪胎した。イギリス人(生まれはイタリアだが)音楽家としては、ビートルズに次ぐレコード・セールス記録を持つ。
注21:アメリカの編曲者・指揮者パーシー・フェイスの楽団。その代表曲「夏の日の恋」はムード音楽を代表する一曲でもあるが、もともとは映画『避暑地の出来事』(A Summer Place, 1959)のテーマ曲だった。「夏の日の恋」というタイトルは日本人が付けたもので原題はただのTheme from A Summer Placeという。さらにはオープニング曲ですらなく劇中の一曲だったが、パーシー・フェイスのアレンジしたバージョンの方が普及し、記録的ヒット。グラミーまで受賞した。
注22:アメリカの映画音楽家。『ティファニーで朝食を』(の「ムーン・リバー」、1961)、『酒とバラの日々』(同名主題歌、1962)ほかでアカデミー歌曲賞に輝く。他にも、『ハタリ!』(の「子象の行進」、1962)、『シャレード』と『ピンクの豹』(1963)、『ひまわり』(1970)、『スペースバンパイア』(1985)など。TVドラマでは『ピーター・ガン』や『刑事コロンボ』など、一々挙げだしたら枚挙に暇が無い。最も曲が知られている映画音楽家の一人かもしれない。
飯森: なるほど。60年代的解釈における上流階級イメージということですね。ジーン・ハーローのメイクなどもそうですよね。僕は彼女の映画って1本くらいしか見たことないんですけど、マレーネ・ディートリッヒみたいな物凄い眉型をしているんですよね。今見ると「ピエロか!」みたいな。2~3mmくらいの細い線で半円を描いたような眉毛ね。当時はそれがオシャレだったのかもしれないけれど、それこそ日本の昔のお歯黒と殿上眉(注23)みたいなもんで、今となっては怖いですよ。その流行が過ぎ去ってしまうとむしろ笑えるか怖いか、っていうくらいの変さで、あれはそのあと’70年代のフェイ・ダナウェイの頃ぐらいにもう一回リバイバルしただけで、全然定着しなかった。あまりに変すぎて。なんですけれども、この映画の中ではそんな変な’30年代風メイクは一切していないんですよね。
注23:お雛様とか能面の、例のアレ。
なかざわ:ヘアスタイルも当時のものをベースにはしていますけれど、そのまんまじゃなくて’60年代のアレンジが加わっている。
飯森: ’60年代の映画に見えますもんね。
なかざわ:ちなみに音楽について補足しておくと、ニール・ヘフティは’60年代のテレビ実写版『バットマン』のテーマ曲を書いた人です。この作品では劇中の挿入曲として書いた「ガール・トーク」というインストゥルメンタル・ナンバーがとても有名で、ジュリー・ロンドンやトニー・ベネットが歌詞を付けて歌っているんですよ。これもゆったりとしたエレガントなイージー・リスニング系バラードで、とても大好きな曲です。
飯森: そう考えると、『誘惑』といい『三文オペラ』といい、今回のセレクションは映画音楽的にも見どころが多いかもしれませんね。ちなみに、『ハーロー』で笑ったのはエンディングの歌ですね。映画のテーマを全部歌詞にしている。そのまんま。メタファーとか一切ナシで「彼女はシルクやサテンをまとった孤独で可哀想な女の子でしたとさ〜♪」みたいな、ひねりのない歌詞でね(笑)。
なかざわ:確かに!あれを歌っているのはボビー・ヴィントンですね。あの「ブルー・ベルベット」で有名なクルーナー歌手。ただ、これは「ガール・トーク」みたいなスタンダードにならなかった。
飯森: ジーン・ハーローの伝記映画にしか使いようがない、つぶしのきかない歌詞ですからね。でもこの映画って、キャンプというかドラァグというか、オカマな雰囲気があるように思いますね。この歌にしても。この感じはえもいわれぬ魅力ですよね。
なかざわ:まさにその通りですよ。
『誘惑』COPYRIGHT (c) 2017 BY PARAMOUNT PICTURES CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. 『三文オペラ』TM & Copyright (c) 2004 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. 『肉体のすきま風』TM, (r) & (c) 2017 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. 『ハーロー』TM, (r) & (c) 2017 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. CHARLIE BUBBLES (c) 1967 Universal City Studios, Inc. Copyright Renewed. All Rights Reserved. GETTIN' SQUARE (c) 2003 Universal Pictures. All Rights Reserved. THE GIRL FROM PETROVKA (c) 1974 by Universal Pictures. All Rights Reserved.