“シビル・ウォー=Civil War”という言葉は、アメリカでは、奴隷制度廃止などを巡って、1861年から65年に掛けて行われた内戦“南北戦争”を指す。近未来のアメリカが再び、血みどろの“内戦”に突入したという設定の本作『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(2024)の、脚本・監督を担当したのは、イギリス人のアレックス・ガーランド。
彼にとっては、4本目の長編監督作品に当たる本作は、2016年にその発想のオリジンがある。この年アメリカでは、ドナルド・トランプが大統領に当選。イギリスでは、ボリス・ジョンソンらの扇動で、ブレグジット=EU離脱が、国民投票で可決されてしまった。
ジョンソンは後年、イギリス首相の座に就く。それ以外にも、イスラエルのネタニヤフやブラジルのボルソナーロなど、世界各国で強権的なポピュリスト政治家が台頭するようになっていった。
こうした世界の変化に思いを巡らせたガーランドは、2020年頃に本作の脚本を執筆。製作・配給会社のA24に諮ると、すぐに映画化が決まったという。
*****
強権的な大統領の下で分断が進んだ、アメリカ合衆国。連邦政府から19の州が離脱し、テキサス州とカリフォルニア州の同盟からなる“西部勢力”と、“政府軍”の間で、“内戦”が勃発した。
戦闘は長期化したが、やがて西部勢力がワシントンD.C.への侵攻を窺う情勢となり、大統領が率いる政府軍の敗色は、日に日に濃くなっていく。
戦場カメラマンのリーと相棒の記者ジョエルは、もう14ヶ月間もマスコミの前に姿を現してない大統領への単独取材の計画を立てる。ニューヨークからD.Cまで1,379㌔。リーの恩師である黒人ジャーナリストのサミーと、リーに憧れる若手カメラマンのジェシーを乗せて、車の旅が始まった。
戦火が渦巻くアメリカで、過酷な“内戦”の実相を目撃していく一行。折々危険に曝され、遂には仲間の1人を失ってしまう。
そうした中で、大統領が立て籠もるホワイトハウスに、西部勢力の攻勢と共に、足を踏み入れる瞬間がやってくるが…。

*****
ガーランドは政治漫画家の息子で、子どもの頃は、父の友人のジャーナリストに囲まれて育った。彼の名付け親も、その内のひとり。
少年時代の経験から、当初はジャーナリストになることを夢見たガーランドは、20歳の頃、世界各地を旅して特派員の真似事をした。彼はそこで見聞きしたことを、ルポルタージュにまとめることを試みたが、失敗。ジャーナリストになることをあきらめた経緯がある。
方向性を変えたガーランドは、小説を執筆。その小説がダニー・ボイルによって、『ザ・ビーチ』(2000)として映画化されたことが縁となって、映画界に身を投じた。ボイル監督の『28日後…』(02)で脚本家デビューを果し、2015年には『エクス・マキナ』で、監督としてもスタートを切った。
そんなガーランドが、日頃強く感じていたのが、「政府とジャーナリズムは本来、両方ともバランスをとる役割があるけれど、共に今は正常に機能していない」ということ。
自由な国には自由な報道が絶対的に必要なのに、今やジャーナリズムには、昔のような力はなくなった。ジャーナリストたちも、必要な存在と見なされなくなってきている。
1970年代には、「ワシントン・ポスト」紙の2人の記者が、“ウォーターゲート事件”の真相を暴いたことによって、ニクソン大統領を、任期途中での辞任に追い込んだ。しかし今や、ニクソンなどより遥かに多くの悪事を為しているであろうトランプに、報道がトドメを刺すことなど、極めて困難な事態となっている…。

本作では、テキサス州とカリフォルニア州が組んで、大統領の圧政=ファシズムに対抗するという構図になっている。アメリカ政治の知識がある方には自明だが、テキサスはいわゆる“赤い州”。現在トランプが支配している共和党が、圧倒的に強い地域。一報カリフォルニアは“青い州”で、トランプと敵対する、野党民主党の金城湯池である。
というわけで現状に鑑みれば、テキサスとカリフォルニアが組んで、ファシズムに対抗するなどという事態は、非常に想像しにくい。ガーランドが敢えてこうした設定にしたのは、観客に特定のイデオロギーを感じさせないためだたったと思われる。
とはいえ強権的な大統領の振舞いは、イヤでもアメリカの現状を想起させる。本作では“内戦”が起こった原因は、直接的には描かれていないが、大統領が何をやったかは、端的に語られる。
まず注目すべきは、この大統領は、現在“3期目”を迎えているということ。アメリカの憲法では、大統領の任期は“2期=8年”までと、明確に定められている。ということは、何らかの手段を以て、憲法を無視する挙に出て、大統領の椅子に居座り続けているということである。
またこの大統領は、FBI=アメリカ連邦捜査局の解体に踏み切っている。即ち政府の暴走や大統領の犯罪的行為を取り締まる機関が、存在しなくなったというわけだ。また連邦国家であったアメリカに於いて、州を跨いでの犯罪捜査が不可能になってしまい、治安の悪化にも繋がっている。
そしてこの大統領は、アメリカ市民への空爆を実施したことが、語られる。アメリカの三権分立は空文化し、大統領が己の保身と抵抗勢力を踏み躙るためには、「何でもあり」の状態になってしまっているのだ。
この作品がアメリカで公開されたのは、昨年=2024年4月。トランプが大統領選2度目の勝利を収める、7ヶ月も前のこと。元々トランプは、“3期目”を目指すことを、折りに触れては滲み出していたが、今年1月に正式に大統領の座に返り咲くと、FBI長官に己の意のままになる者を就け、大幅な人員削減に着手。トランプ関連の捜査を行っていた、スタッフの首切りを実施している。
そしてトランプは、“治安維持”をお題目に、ロサンゼルスやメンフィス、首都ワシントンなど、野党民主党の勢力が強い都市に、次々と州兵を送り込んでいる…。
恐ろしいほどに、トランプ2期目の今のアメリカと、情勢が重なってくるのだ!

本作の主役と言えるのは、戦場カメラマンの2人の女性。ベテランのリー・スミスと、新人のジェシー・カラン。この2人の名は、ガーランドが尊敬する2人の戦場カメラマン、リー・ミランとドン・マッカランに因んでいる。
キルスティン・ダンストは「(本作の)脚本を読んでドキドキ」し、翌日には監督とミーティングを行っている。そしてリーの役を、「絶対に演じたい」、リスペクトするガーランドと「仕事をしたい」と、強く思ったという。
ジェシー役に抜擢されたのは、ガーランド監督のTVシリーズ「DEVS/デヴス」などに出演していた、若手女優のゲイリー・スピーニー。
ガーランド監督は、ジャーナリストを目指していた頃の若き日の自分を、ジェシーのキャラクターに反映。リーのモデルとなったのは、その当時にガーランドが親しくしていた、経験豊富なジャーナリストだという。
撮影現場では、ダンストとスピーニーは、本作に於けるリーとジェシーのように、日々を絆を深めていった。過酷な撮影の中で、スピーニーはダンストの家に行っては、その家族との交流の中で、癒されていたという。
ダンストにとってスピーニーは、「妹のような存在」となり、ある時に友人であるソフィア・コッポラ監督に紹介。それがきっかけとなって、スピーニーはコッポラの『プリシラ』(23)で、プリシラ・プレスリーを演じることとなった。
リーの相棒ジョエル役には、TVシリーズ「ナルコス」で、実在の麻薬王パブロ・エスコバルを演じた、ワグネル・モウラ。黒人の老ジャーナリスト、サミー役は、スティーヴン・マッキンリー・ヘンダーソンが演じた。
さて1シーンだけの出演だが、強烈な印象を残すのは、“虐殺”を主導する正体不明の民兵を演じるジェシー・プレモンス。
彼が放つ一言「What kind of American are you?(お前はどういう種類のアメリカ人だ?)」は、本作を象徴する強烈な名台詞となっているが、一体どんなシチュエーションで吐かれるかは、観てのお楽しみとしておきたい。
実はプレモンスの役は、当初別の俳優が演じることになっていたが、直前に降板。代役に思い悩むガーランド監督に、ダンストが、自分の夫であるプレモンスを、推挙したという流れだった。
撮影5日前に急遽出演が決まったプレモンスは、限りある時間で徹底的にリサーチ。兵士の話を聞きまくったという。因みに彼が掛けている赤いサングラスは、自ら用意した10種類ぐらいのメガネから、現場でピタッとハマったものを選んだという。

ガーランドは、絵コンテなどは用意せず、現場で起こることに即応して、撮影を進めていくタイプの監督。本作では小さな手持ち撮影のカメラを多用したという。
本作の軍事顧問を務めたのは、アメリカ海軍の特殊部隊ネイビー・シールズ出身のレイ・メンドーサ。彼の指導の下、画面に登場する兵士たちは、実際に従軍経験のある者ばかりだった。
クライマックスのホワイトハウス突入のシーンで、監督として兵士役の者たちに伝えたのは、カメラのことは気にしないで「普段通りに行動して」ということだけだったと。セリフも、兵士同士の普段の会話のため、ガーランドは、ドキュメンタリーを撮っているような感覚に陥ったという。
サウンド・デザインで銃器の怖ろしさを表現する工夫を施した本作は、アメリカでは163年前に“南北戦争”が勃発した、2024年の4月12日を選んで、公開。製作・配給のA24作品史上、最高のオープニング興収を樹立し、2週連続で興行ランキング1位を獲得する大ヒットとなった。
日本では大統領選直前の10月に公開となったが、それから1年余。現実を鑑みると、いま観た方が、更にゾッとする展開になっている。■
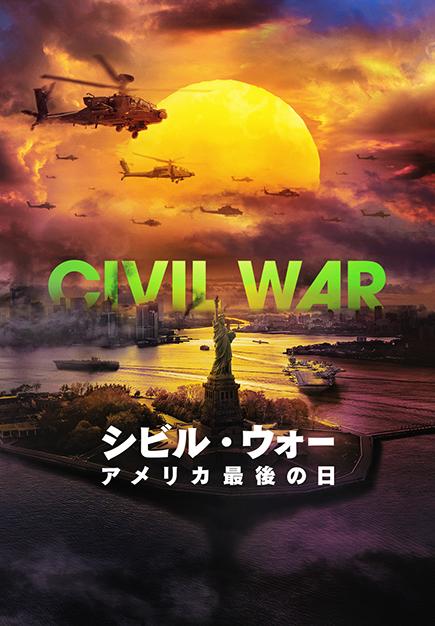 『シビル・ウォー アメリカ最後の日』© 2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.
『シビル・ウォー アメリカ最後の日』© 2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved.








