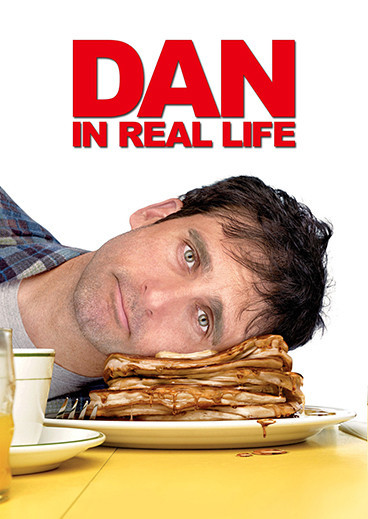カナダのモントリオール郊外。歯科医のオズ( マシュー・ペリー)はシカゴ出身でありながら、妻の父が起こしたセックス&脱税絡みのスキャンダルによって愛する地元にいられなくなり、仕方なくこの街の病院で働いていた。それなのに、妻ソフィ(ロザンナ・アークエット)の浪費癖は改まることなく家計は破綻寸前。公私ともども冴えない彼は、病院の受付嬢ジル(アマンダ・ピート)にも同情される有様だった。
そんなある日、オズの隣家にジミー(ブルース・ウィリス)と名乗る男が引っ越してくる。オズは、彼がシカゴを牛耳るマフィア組織の一員で、ボスを警察に売り渡して予定よりも早く出所することに成功したヒットマン“チューリップ”ことテュデスキの世を偲ぶ仮の姿だということに気づく。だが意外にも気さくな彼とウマが合い、友情らしきものを築くのだった。
しかしいよいよ破産寸前となったオズは、ソフィから「ジミーをマフィアのボスの息子ヤンニに引き渡せば大金を貰えること間違いなし。成功したら離婚してあげる」と迫られ、ヤンニの部下と接触するためにシカゴに行く羽目に陥ってしまう。
しかしオズの留守中にソフィが向かったのはテュデスキの家だった。彼女はオズが彼を売り渡そうとしていることをあっさり打ち明けてしまう。そう、ソフィの真の狙いはオズにかけた多額の生命保険金だったのだ。彼女のオズ殺害計画を知ったテュデスキは、ヤンニの部下で、実はテュデスキの親友フランキー( マイケル・クラーク・ダンカン)を介して「心配するな、俺たちの友情は壊れない」とオズを励ます。
だがオズは手放しでは喜べなかった。というのも、ヤンニのアジトで出会ったテュデスキの妻シンシア(ナターシャ・ヘンストリッジ)と恋に落ちてしまっていたからだ。シンシアはボスの秘密資金1000万ドルを預かっており、現金化するには彼女とテュデスキ、ヤンニ三人のサインもしくは死亡証明書が必要だった。大金を獲得するためならヤンニはもちろん、テュデスキも自分を殺すことを躊躇わないだろうと語るシンシア。果たして小市民のオズは、自分とシンシアに降りかかった絶体絶命のピンチを乗り切れるのだろうか……。
プロットをざっと書いてみるだけでも分かる通り、『隣のヒットマン』(2000年)は複雑な設定と、二転三転するストーリーによって、観る者のテンションを最後までマックス状態に維持し続けるクライム・コメディだ。
凝りに凝った脚本を書いたのは、これがデビュー作だったミッチェル・カプナー。それをモンティ・パイソンのエリック・アイドルが主演した『ナンズ・オン・ザ・ラン 走れ!尼さん』 (1990年) やメリサ・トメイにオスカーをもたらした『いとこのビニー』 (1992年) で知られる英国出身のコメディ職人ジョナサン・リンがタイトに仕上げている。
主演は、ブルース・ウィリス。このとき既にアクション映画界のスーパースターだった彼だけど、出世作だったテレビドラマ『こちらブルームーン探偵社』(1985〜89年)は探偵モノでありながら、パロディとマシンガン・トークを売りにしたコメディ仕立てのものだった。映画本格進出作の『ブラインド・デート』(1987年)にしてもブレイク・エドワーズ監督のロマ・コメだったし、スターダムに押し上げた『ダイ・ハード』(1988年)も実はアクションと同じくらいウィリスの軽口を楽しむ映画である。『隣のヒットマン』はそんな彼のコメディ・サイドをフューチャーするのにピッタリの企画であり、最初にキャスティングされたのも彼だった。そんな製作サイドの要望に忠実に、ここでのウィリスはシリアスとコミカルの狭間を行き交う演技で観客を惹きつけてみせる。
そんなウィリスが、相手役(そしてストーリー上は主人公)であるオズ役に当初から熱望したのがマシュー・ペリーだったという。当時のペリーは、驚異的な高視聴率を記録していたシットコム『フレンズ』 (1994〜2004年)のチャンドラー役でノリに乗っている時期であり、ウィリスは彼が持つ勢いを作品に持ち込めれば映画の成功は間違いないと思ったのだろう。
こうした彼の目論見にペリーは見事に応えている。リアクションがいちいち絶妙。しかも等身大のキャラを得意とする彼だからこそ、映画冒頭の冴えない姿から後半のヒーローへの変貌に、観客が喝采を叫べるというわけだ。またその活躍があくまで歯科医という設定を活かしたものであるところにも唸らされてしまう。
ウィリスとのコンビネーションという意味では、超能力者に扮したフランク・ダラボン監督作『グリーンマイル』(1999年)における演技が絶賛されたマイケル・クラーク・ダンカンも印象的だ。ダンカンはウィル・スミスをはじめとするハリウッド・スターのボディ・ガードから俳優に転じた変わり種。そんな彼をウィリスは『アルマゲドン』(1998年)で共演して以来、高く評価しており、本作は『ブレックファースト・オブ・チャンピオンズ』(1999年)に続く3度目の共演作にあたる。もし2012年に心筋梗塞で急死していなかったら、もっと共演を重ねられたのではないかと思うと、残念でならないけど、ウィリスとのプライベートの交流がそのまま反映された本作の彼は心の底から楽しそうだ。
女優陣もそれぞれ健闘。オズのどうかしている妻ソフィを演じているのは、『マドンナのスーザンを探して』(1985年)などコメディで抜群の冴えを見せるロザンナ・アークエット。フランス語訛りのヘンなセリフ回しが最高におかしい。そんな彼女とは対照的に、『スピーシーズ 種の起源』(1995年)のエイリアン役でお馴染みのナターシャ・ヘンストリッジがフィルム・ノワール的なクール美女シンシアになりきってみせる。
とはいえ、女優陣のMVPはジルを演じたアマンダ・ピートだろう。リアルタイムで本作の彼女を観たときの衝撃ときたら無かった。テレビにはそこそこ出演していたものの、それまで映画で大きな役をひとつも演じたことが無かった彼女は本作でも病院の受付嬢という一見チョイ役で登場する。だが濃すぎる顔立ちは存在感がありすぎるし、セリフは非常識なものばかり。
「彼女は一体何者なんだ?」そんな疑問が観客の中にじわじわ湧き上がっていき、それが沸点に達した瞬間に正体が明かされる。何とジルの正体はテュデスキを崇拝する殺し屋志望の女子だったのだ。映画後半の彼女の大活躍ぶりは、大スターのウィリスとペリーのそれを霞ませるほどのもの。こんな美味しい役をブレイク前の若手女優に与えた本作の製作陣にはどれほど賞賛を送っても送り足りないと思う。
本作でブレイクしたピートは、血も涙もないサイコな悪女に扮した『マテリアル・ウーマン』(2001年)でジェイソン・ビッグス、ジャック・ブラック、スティーブ・ザーンという3人のコメディ男優を向こうに回して映画を引っ張りまくり、『17歳の処方箋』(2002年)でもキーラン・カルキン扮する主人公を翻弄するフリーダムな女子を怪演。コメディ女優として一時代を築いたのだった。2006年に『ゲーム・オブ・スローンズ』のショーランナー、デイヴィッド・ベニオフと結婚して以降は上昇志向が収まったのか、普通の演技派女優になってしまったのがコメディ好きとしては本当に残念である。というわけで、映画ファンは、本作の続編『隣のヒットマンズ 全弾発射』(2004年)を含めて、この時期ならではのギラギラしたアマンダ・ピートの魅力に脳天を撃ち抜かれてほしい。
WHOLE NINE YARDS, THE © 2000 METRO-GOLDWYN-MAYER DISTRIBUTION CO.. All Rights Reserved